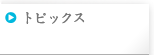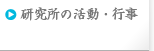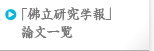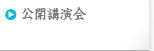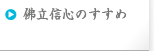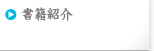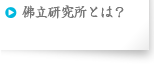-
- 2019
2016
12015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
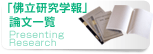
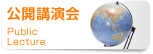
- ㊱「憶持不忘(おくじふもう)」と「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」(2)
- 2016年1月27日(水)
―「忍難弘経(にんなんぐきょう)」を覚悟の受持(じゅじ)―
○苦難を覚悟して持(たも)つ
前回は、「提婆達多(だいばだった)こそ善知識(ぜんちしき)」という見出しで、法華経提婆達多品第12や、日蓮聖人の『種種御振舞御書(しゅじゅおんふるまいごしょ)』の一節などをいただきつつ、特にお役中は、自分に対し、敵対し、迫害を加える人や逆境こそが、自分を鍛え向上せしめる「善知識」だと頂戴させていただくことが大切である旨申しました。
そして、その際注意すべき心得として、「いわゆる独善に陥(おちい)らぬよう、謙虚な自省心も忘れないように」とも記しました。開導聖人も「自見(じけん)によらば必ず謗法を起(おこ)す也」(一講一紙要談抄・扇全8巻106頁)とお誡(いまし)めのごとく、仏祖のみ教えをいただいているつもりが、実は凡夫の我見をまじえたものとなっていたら、それは誤りであり、周囲の反発はその誤りに対する当然の批判であって、それならその批判の方が正しいのですから、その場合は謙虚に批判を受け止め、自身が反省・改良せねばならないはずです。つまり謙虚さや柔軟性も大切なのです。
にもかかわらず、自分は常に正しいと思い込み、批判はすべて「善知識」であり、いわば「法難」だから、「これに屈せず一層頑張ろう」などと奮起されるのは、周囲にとっては実に迷惑な話です。
日蓮聖人にとっての「善知識」は、あくまでも正法たる法華経の教え、み仏の金言(きんげん)に随順し、常にそのみ教えに自身を照らし合わせながらのものでした。
例えば佐渡ご流罪中に認(したた)められた『開目抄』(文永9年・数え51歳・於塚原三昧堂)では次のように仰せです。
「又云(またいわ)く『数数見擯出(さくさくけんひんずい)』等云云、日蓮法華経のゆへに度度(たびたび)ながされずば、数数(さくさく)の二字いかんがせん。(乃至)末法(まっぽう)の始(はじめ)のしるし恐怖悪世中(くふあくせちゅう)の金言のあ(合)ふゆへに但日蓮一人(いちにん)これをよめり。(乃至)此等皆仏記(これらみなぶっき)のごとくなりき。(乃至)当世法華の三類(さんるい)の強敵(ごうてき)なくば誰(たれ)か仏説を信受せん。日蓮なくば誰をか法華経の行者として仏語をたす(助)けん。(乃至)経文に我身普合(わがみふごう)せり。御勘気(ごかんき)をかほ(蒙)ればいよいよ悦(よろこび)をますべし」(開目抄(上)・昭定560頁)
「数数見擯出」とは法華経勧持品(かんじほん)第13の中に「数数見擯出(さくさくけんひんずい) 遠離於塔寺(おんりとうじ)」(数数擯出[しばしばひんずい]せられ塔寺[とうじ]を遠離[おんり]せん)(開結365頁)とあり、「数数」は「しばしば」、「擯出」は「流罪」の意ですから「何度も流罪せられ、お寺から追い出される」という意です。「恐怖悪世中」というのも同じ勧持品の中に「於仏滅度後(おぶつめつどご) 恐怖悪世中(くふあくせちゅう)」(仏の滅度の後[のち] 恐怖悪世の中に於て)(開結363頁)とあり、「仏滅後の末法悪世の恐るべき時代においては」との意です。
つまりみ仏が法華経勧持品の中にその金言(仏語、仏記)として、「末法悪世は恐るべき時代であり、そこで妙法を弘通せんとする法華経の行者には必ずや『三類(さんるい)の強敵(ごうてき)』(①俗衆増上慢[ぞくしゅうぞうじょうまん] ②道門[どうもん]増上慢 ③僭聖[せんしょう]増上慢の三類。「俗衆」は世門世俗の人々、「道門」は仏門の僧侶、「僭聖」は世に聖人・生き仏等と尊崇されながら内実はそうではない権勢ある高僧のこと)に怨(あだ)まれ怨嫉迫害(おんしつはくがい)が相次ぐことが明記されているのです。
日蓮聖人は、この法華経の金言の一つ一つに、自身を重ね合わせ、それらの仏語のすべてに自身の迫害の種類や内容が合致するかどうかを検証されるのです。そして、「すでに他の迫害(悪口罵詈刀杖瓦石[あっくめりとうじょうがしゃく]、三類の強敵等)のすべてが経文通りに現実のものとなっており、ただ一つ残っていた『数数見擯出』も、先年経験した伊豆伊東の流罪に加えて、今回の佐渡流罪によって『数数』の二字を満たした。これで確かに仏の金言として法華経に記された全ての迫害を、経文通りに身に受けたのだから、これでまさしく日蓮が末法の『法華経の行者』だと申すことができる」、と仰せなのです。
「経文に我身普合(わがみふごう)せり。御勘気をかほ(蒙)ればいよいよ悦(よろこび)をますべし」とあるのは、まさしく、聖人ご自身が「これで勧持品の仏語のすべてに合致(普合とは普[あまね]く合致する意)した。それも今回幕府の怒り(勘気)によって、竜(たつ)の口(くち)の首の座から佐渡流罪となったことによって経文に普合することができたのだから、これは実に喜悦(きえつ)すべきことなのだ」と仰せになっているのです。
このように、日蓮聖人はすべてを法華経に示されたみ仏の金言に引き合わせ、検証を重ねておられるのです。「法華経の行者」と名乗られるのもその上でのことです。しかもなおその上で、さらに次のように仰せです。
「但し世間の疑(うたが)いといい自心(じしん)の疑ひと申し、いかでか天扶(てんたす)け給(たまわ)ざるらん。諸天(しょてん)等の守護神は仏前の御誓言(ごせいごん)あり。法華経の行者には〈乃至〉早早(そうそう)に仏前の御誓言をとげんとこそをぼすべきに、其義(そのぎ)なきは我身(わがみ)法華経の行者にあらざるか。此疑(このうたがい)は此書(このしょ)の肝心、一期(いちご)の大事なれば、所所(しょしょ)にこれをかく上(うえ)、疑を強くして答をかまうべし」(開目抄(上)・昭定561頁)
「法華経の行者を昼夜に守護すると、諸天善神がみ仏にお誓いをしている(諸天昼夜常為法故而衛護之[しょてんちゅうやじょういほうこにえいごし]―諸天は昼夜に常に法の為の故に而(しか)も之(これ)を衛護す・安楽行品第14・開結382頁)のに、日蓮とその弟子信者がこれほどの大難・迫害にさらされているのを、なにゆえ諸天は放置し救けてくれないのか。世間の疑いも、日蓮自身の心の疑念もそこにある。これは日蓮が真実の法華経の行者ではないということであろうか。この疑念(を晴らすことができるかどうか)はこの書(開目抄)の肝心であり、日蓮一期の大事であるから、このことに関してはこの書の随所に記するから、読む者も強く疑問を持ちつつ、日蓮が示す答えに相い対してほしい」との意です。
ご承知のように、日蓮聖人は上行所伝の妙法こそが末法の一切衆生を救済する唯一の大法だとの確信のもとに32歳で立教開宗をされ、以来20年間妙法弘通の一筋に邁進(まいしん)してこられました。けれども開宗以来のご生涯は文字通り相次ぐ迫害の連続であり、聖人ご自身はもとより聖人を信じ随(したが)ってきた弟子信者も怨嫉の中に身をさらし続けてきたのです。もちろん迫害を覚悟の上でのご奉公でしたが、今度の迫害は聖人の命(いのち)はもとより、教団そのものの壊滅をも企図するもので、文字通り教団全体に対する強権による大弾圧だったのです。しかもこの期に及んで諸天の守護も顕れないのであれば、それがもし聖人が真正の法華経の行者でないためだとすればこれほどの大事はありません。ご自身が誤ったことによって、弟子信者はもとより多くの人びとをも誤りに導き、徒(いたず)らに迷わせ苦しめてしまったことになります。「我身法華経の行者にあらざるか。此疑は此書の肝心、一期の大事なれば」と明記され、さらに「疑を強くして答をかまうべし」とのお言葉には、聖人の偽らぬ率直なお心が吐露されていると拝します。
少し長くなりましたが、ここで申しあげたいのは、聖人は決して独善的・狂信的な宗教者ではなかったということです。いやむしろ真摯(しんし)な求道(ぐどう)によって得た確信を以て開宗され、ご弘通をされた聖人であればこそ、真率かつ謙虚な自省心を持ち続けておられたのです。こうしたご自身に向けた疑念への真摯な問いかけを通じてこそ、それを超克しての本当のさらなる前進があるのだと拝察されるのです。『本尊抄』が「法開顕(ほうかいけん)の書」とされるのに対してこの『開目抄』が聖人の「人開顕(にんかいけん)の書」であり、「上行自覚(じょうぎょうじかく)」(本化[ほんげ]上行菩薩の後身[ごしん]だとのご自覚を示される)の書だとされるのも、この疑問を率直かつ真摯に自己に受けとめられ、厳しくその検証を重ねられる過程が如実に記され、そしてその上での新たなゆるぎない確信が示されているからに他ならないと存じます。
○「深い謙虚さ」と「ゆるぎない誇り」の兼備を
聖人は、もとより自らは「石中(いそなか)の賎民(しずたみ)が子」(善無畏三蔵抄)、「海辺の旃陀羅(せんだら)が子」(佐渡御勘気抄)、「片海(かたうみ)の海人(あま)が子」(本尊問答抄)であって、罪根甚重の凡夫であるとのご自覚を生涯にわたってお持ちでした。このいわば「凡夫日蓮」の自覚を持ちながら、同時にその一方で自己に対する厳しい内省と検証を重ねつつ「法華経の行者」、「地涌(じゆ)の菩薩」、「上行後身の如来使」との自覚を確立・開顕してゆかれるのです。聖人ご自身がこのような姿勢であられたということも、私共は決して忘れてはならないと存じます。
聖人は、『開目抄』(文永9年2月)の直後に記された『佐渡御書』(同3月)で、次のようにも仰せです。
「日蓮も、又かく責めらるるも先業(せんごう)なきにあらず。〈乃至〉何(いか)に況(いおう)や日蓮今生(こんじょう)には貧窮下賎(びんぐげせん)の者と生まれ、旃陀羅(せんだら)が家より出(い)でたり。心にこそ少し法華経を信じたる様なれども、身(み)は人身(にんしん)に似て畜身(ちくしん)也。〈乃至〉又過去の謗法を案ずるに誰(たれ)かしる。〈乃至〉宿業(しゅくごう)はかりがたし。鉄は炎打(きたえう)ちて剣(つるぎ)となる。〈乃至〉我が今度(こんど)の御勘気(ごかんぎ)は世間の失一分(とがいちぶん)もなし、偏(ひとえ)に先業の重罪を今生に消して、後生(ごしょう)の三悪(さんなく)を脱(のが)れんずるなるべし」(昭定614頁)
このように聖人は定業堕獄の凡夫との自覚を明確に持ち、過去の謗法の罪障をこの度の大難を受けることによって消滅し、後生に三悪道(地獄・餓鬼[がき]・畜生の三悪道)に堕することを脱することができるのだ、と受けとめておられるのです。
私共が『妙講一座』の「随喜段」(「あゝ有難や」の御文)の中で、先に「あさましや我身の上をかへりみれば(乃至)三毒強盛なり」と唱えつつ後に「本化上行の流類(りゅうるうい)読持此経(どくじしきょう)是真仏子(ぜしんぶっし)といはれ」と言上申しあげるのも同じ意です。ここには「三毒強盛の凡夫」でありながらも、こうして妙法を信受する佛立信者とならせていただいた身の上は「本化上行の流類・是真仏子」の大果報を頂戴している存在でもあるのだ、との悦びが表白されているのですから。ここにも「罪障の深い凡夫」の自覚と「上行流類・是真仏子」の自覚とを同時に持つべきことの大切さが明記されているのです。どちらか一方に偏(かたよ)るのではなく双方の自覚を同時に持つことが大切なのです。一方に偏るのは卑屈と傲慢(ごうまん)のどちらかに陥ることに他ならないのですから。苦難を真の「善知識」として受けとめつつ、双方の心を同時に持ち、それをいつも忘れない、そこにこそ「真の謙虚さ」と、苦難にもゆるがない「強固な誇り」との両者を兼ね備えた法華経の菩薩の姿があるのです。
実は、日蓮聖人が仰せになる「憶持不忘(おくじふもう)」の意も、「難に値(あ)うことを覚悟して妙法を受持する」ということが土台となっています。
○値難(ちなん)を覚悟の「憶持不忘(おくじふもう)」
『岩波仏教辞典』によれば、「憶持(おくじ)」とは「記憶して心に持(たも)つこと。心に記憶して忘れないこと。翻訳語としては憶念(おくねん)と同一。(中略)しかし、中国・日本で、憶念と区別して理解される場合、憶持には〈受持して忘失しない〉というニュアンスが濃い」とあります。
出典としては、法華経の結経(けっきょう)である『観普賢菩薩行法経(かんふげんぼさつぎょうほうきょう)』に「爾(そ)の時に行者、普賢の深法(じんぽう)を説くことを聞いて、其(その)の義趣(ぎしゅ)を解(げ)し、憶持して忘れじ。(解其義趣[げごぎしゅ] 憶持不忘[おくじふもう])」(開結610頁)があります。つまり「教えを聞き、理解して忘れない」という意味です。
「憶持不忘」の基本的な意味は右の通りですが、日蓮聖人の示される「憶持不忘」はそれだけではありません。「苦難・迫害に値(あ)っても妙法を受持し、決して退転しない」ということですから、通常の「憶持不忘」に「値難を覚悟して」の意が加わるのです。
日蓮聖人は四条金吾に宛てた御消息(ごしょうそく・お手紙)に次の如くお示しです。
「此経難持(しきょうなんじ)事。〈乃至〉此経(このきょう)をききうくる人は多し、まことに聞受(ききうく)る如くに大難来(きた)れども憶持不忘の人は希(まれ)なる也。受(うく)るはやすく持(たもつ)は難(かた)し、さる間(あいだ)成仏は持(たもつ)にあり。此経(このきょう)を持(たもた)ん人は難に値(あう)べしと心得て持(たも)つ也。〈乃至〉三世(さんぜ)の諸仏の大事たる南無妙法蓮華経を念ずるを、持(たもつ)とは云(いう)也。〈乃至〉天台(てんだい)大師の云(いわく)『信力(しんりき)の故(ゆえ)に受(う)け、念力の故に持(たも)つ』云云。又云『此経(このきょう)は持(たも)ち難(がた)し、若(も)し暫(しばら)くも持(たも)つ者は我即(われすなわ)ち歓喜(かんぎ)す、諸仏も亦然(またしか)なり』云云。火にたきぎ(薪)を加(くわう)る時はさかん也。大風吹(ふか)ば求羅(ぐら)は倍増する也。〈乃至〉法華経の行者は火と求羅との如し、薪と風とは大難の如し。〈乃至〉此より後(のち)は此経難持の四字を暫時(ざんじ)もわすれず案じ給べし」 (四条金吾殿御返事・昭定894頁)
この御消息は文永12年(建治元年)3月6日付ですから、日蓮聖人は54歳、前年の春赦免(しゃめん)されて佐渡から帰還し、身延へ入山された直後です。なお付言すれば、前年の文永11年10月には聖人の諫言(かんげん)通り、第一回目の蒙古襲来(文永の役[えき])が起こっています。
「信力の故に受(う)け、念力の故に持(たも)つ」の文は、天台大師の『法華文句(ほっけもんぐ』(第8・大正蔵34巻107頁C)の中の「信力故受念力故持(しんりきこじゅねんりきこじ)」の訓(よ)み下(くだ)しです。これは法華経の法師品(ほっしほん)第10に示される「五種法師(ごしゅほっし)」[受持(じゅじ)・読(どく)・誦(じゅ)・解説(げせつ)・書写(しょしゃ)のこと]の第一「受持」の義を釈したものであり、「此経難持」の御文は、法華経見宝塔品(けんほうとうほん)第11の結文(けちもん)となる偈文(げもん)で『妙講一座』にも採録されており、ご引用の「諸仏も亦然なり」云云の後には、「如是之人(にょぜしにん) 諸仏所歎(しょぶつしょたん) 是則勇猛(ぜそくゆみょう) 是則精進(ぜそくしょうじん)」(是[かく]の如[ごと]きの人[ひと]は諸仏の歎[ほ]めたまふ所なり。是[こ]れ則[すなわ]ち勇猛[ゆみょう]なり。是れ則ち精進[しょうじん]なり)と続きます。そしてさらに、そのような行者こそ「即(すなわ)ち為(こ)れ疾(と)く無上(むじょう)の仏道を得たり、〈乃至〉是(こ)れ真(しん)の仏子、淳善(じゅんぜん)の地(じ)に住(じゅう)するなり」(即為疾得(そくいしっとく) 無上仏道(むじょうぶつどう)〈乃至〉是真仏子(ぜしんぶっし) 住淳善地(じゅうじゅんぜんじ)と説かれているのです。
また「求羅(ぐら)」とは「迦羅求羅(からぐら)」の略で、想像上の虫の名であり、風を受ければ受けるほど大きく成長し、ついにはすべてを呑み込むとされます。『上野殿母御前返事』に「からぐらと申す虫は風を食(しょく)とす。風吹かざれは生長せず。〈乃至〉仏も亦(また)かくの如く法華経を命とし、食とし、すみかとし給なり」(昭定1817頁)とも仰せです。先の御消息では「法華経の行者はあたかも火と求羅のようなものだ。薪と風とは大難のようなものだ。だから法華経の行者は大難に値(あ)えば値うほど大きく成長するのだ」と仰せになり、「だからこそ『此経難持』の御文を常に忘れないようにせよ」と結ばれているのです。
日蓮聖人のみ教えにおける「憶持不忘」は「値難(ちなん)を覚悟」しなければならず、その意味で「此の経は持(たも)ち難い」けれども、そこを堪えて忍難弘経(にんなんぐきょう)を貫(つらぬ)く行者こそが「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」の真の法華経の行者であり、速やかに成仏を遂げる「是真仏子」なのだということです。
このように「値難を覚悟」し「此経難持」を前提とした「憶持不忘」は、実は同じく佐渡で著された『如説修行抄』に示される「されば此経(このきょう)を聴聞(ちょうもん)しはじめん日より思ひさだむべし。況滅度後(きょうめつどご)の大難三類(だいなんあんるい)甚(はなはだ)しかるべしと」(第1段)、あるいは「唱死(となえじに)」(第6段)
と示される決定(けつじょう)の信心と同義だということがわかります。
○「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」も難(なん)に屈せず貫(つらぬ)くこころ
「精進」とは梵語で「ビリヤ」といい、元の意に「勇気」という意味も含んでいます。ですから「勇猛精進」は「嫌気(いやけ)ささず、投げ出さず貫き通すこと」を意味しているのです。
法華経にも随所に見える語で、そのいくつかを挙げれば次のようにございます。
「勇猛精進」(序品[じょほん]・開結66頁)、「勤加(ごんか)精進」(信解品[しんげほん]・同187頁)、「昼夜(ちゅうや)常(じょう)精進」(従地涌出品[じゅうじゆじゅっぽん]・同408頁)、それに先の見宝塔品(けんほうとうほん)の「是則勇猛 是則精進」(同340頁)等です。「精」は「クワシク」、「進」は「ススム」とも解されますから、心をこめ、念を入れて進み続ける意でもあります。ただし、日蓮聖人の「勇猛精進」は「憶持不忘」「忍難弘経」の「勇猛」であり、「精進」なのだということを忘れてはなりません。
最後に開導聖人の御教歌と御指南もいただいておきます。
開導日扇聖人御教歌
○わすれてはおもひ出(いだ)して
はげめどもをこたりがちに成(なる)ぞくやしき
(本尊抄会読(三)・扇全6巻141頁)
○題・信者の一心の家の内に信謗(しんぼう)の二人主(あるじ)を争ふ
わすれぬをたもつといへば法華経の
かたきを責(せめ)よおのが心の
(十巻抄(一)・扇全14巻370頁)
御指南
「賞罰現証に感じて、本尊並(ならび)に尊像(そんぞう)を生身(しょうじん)にていますものと決信(けっしん)して月年(つきとし)を送れども忘れぬ。同じ調子なる人、諸組の中に随分あり。又日々(ひび)に遠ざかるは忘るゝ也。〔ワスルヽハ〕信心のゆるむ也。あさまし」(開化要談 用・扇全13巻403頁)
○せめて「心内の三類」に負けぬように
現代では憲法で「信教の自由」が保障されており、妙法を弘通したからといって強権の弾圧・迫害にあうことはまずありません。せいぜい身内や周辺からの反発がある程度でしょう。もちろん、それはそれで大変苦しい場合もありますが、せめてそれくらいの苦難は覚悟し、信心を決定(けつじょう)してご弘通に精進させていただきたいものです。また、それにも増して忘れてはならないのは、いわゆる「心内の三類」であり「おのが心の敵」です。凡夫持ち前の貪・瞋・癡(とん・じん・ち)の三毒(さんどく)や、疑迷(ぎめい)・不信(ふしん)・懈怠(けだい)の心に負けて信心を忘れ、精進を忘れて懈怠の謗法に陥らぬよう、お役中自身はもとより、ご信者相互に折伏し合い、励まし合う努力が求められているのです。
「無始已来」の御文で「今身(こんじん)より仏身(ぶっしん)に至(いたる)まで持奉(たもちたてまつ)る」と言上し、「宗風」の第2号【受持(じゅじ)】で「受持の一行に徹する」と教えられながら、御指南のごとく、たとえ現証によって一度は信心が決定(けつじょう)できたとしても、年月を経るとともに信心がゆるみ、御法から心が離れ、ついに忘れてしまうことが多いのも凡夫の常です。「憶持不忘」「勇猛精進」を、「せめて心内の三類に負けず受持(じゅじ)せよ」と誡めておられる教えとして頂戴するのは、現代のお互いに即しての、いわば「せめてものいただき方」ではないでしょうか。

佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.