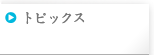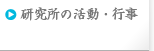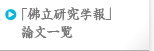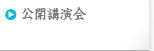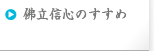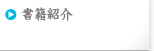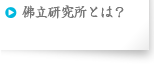-
- 2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
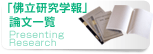
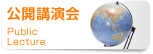
- 仏教のススメの過去の記事
- 2016年 3月
- 2016年 1月
- 2015年 12月
- 2015年 11月
- 2015年 10月
- 2015年 8月
- 2015年 7月
- 2015年 6月
- 2015年 5月
- 2015年 3月
- 2015年 2月
- 2014年 12月
- 2014年 11月
- 2014年 10月
- 2014年 8月
- 2014年 7月
- 2014年 5月
- 2014年 4月
- 2014年 3月
- 2014年 2月
- 2014年 1月
- 2013年 12月
- 2013年 9月
- 2013年 8月
- 2013年 7月
- 2013年 6月
- 2013年 5月
- 2013年 2月
- 2012年 12月
- 2012年 11月
- 2012年 8月
- 2012年 4月
- 2012年 3月
- 2012年 2月
- 2012年 1月
- 2011年 10月
- ㊲育成の大事
- 2016年3月14日(月)
―育成に「手入れ」の感覚・観点を―
○「佛立菩薩を増やそう」のスローガンで
前回まで2回にわたって、「『憶持不忘(おくじふもう)』と『勇猛精進(ゆみょうしょうじん)』」のテーマで、日蓮聖人の「善知識(ぜんちしき)」の把(とら)え方や、当宗の「受持(じゅじ)」(憶持不忘)が、難に値(あ)うことを覚悟しての受持であり、そのように持(たも)ち難い[此経難持(しきょうなんじ)]にもかかわらず、不退転で忍難弘経(にんなんぐきょう)に励ませていただくところに「勇猛精進」の真骨頂があることを、『開目抄』や『佐渡御書』、そして『如説修行抄』の御文をいただきながら拝見いたしました。そして開導聖人の御教歌・御指南によりつつ、「憶持不忘」と「勇猛精進」を現代のお互いに即していえば、「おのが心の敵(かたき)」である「心内の三類」[貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)]の三毒(さんどく)や疑迷(ぎめい)・不信・懈怠等の謗法)に打ち克ち、信心を忘れぬように信行に勤(いそし)ませていただくことが、いわば「せめてものいただき方」ではないか、と申しあげました。
なお、「憶持不忘」(受持)については次のような御指南もありますので紹介させていただきます。
「信心起(おこ)りて持(たも)ち奉る時は、唱へ死(じに)と思ひ定むるなり。持つとは暫(しばら)くも心にわすれずあるを云(いう)也。忘るゝ間なきを持つと申すなり。(乃至)忘るゝ間なくば懈怠起(おこ)らず、悪念おこらず、悪友にさそはれず。(乃至)持つは、うち任せ奉る也。故に忘れだにせずば時々(じじ)御守護也」
(御抄教拝見二・扇全11巻189頁)
さて、今回は「育成」がテーマです。このテーマに関連するものとしては、このシリーズの⑱(平成15年6月号)「法燈相続の大事(1)」―「あとつぎづくり」と「信教の自由」―で、いわゆる法燈相続を念頭に置いて記しており、また③(平成14年1月号)の「不軽菩薩の心をいただく」(2)―「相手に対する真の尊敬」と「自ら求め続ける心」を大切に―も関係します。併せてご覧いただけたらと存じます。当然重なる部分もあるわけですが、できるだけ重複は避けたいと存じます。
さて本年(平成17年)は「佛立開講150年」の奉賛ご奉公も第三年度、ご正当の前年にあたり、「本山記念参詣」(今年は7布教区)も始まります。
すでにご承知のごとく、宗門は目下、ご開講の本旨を体し、「御講から弘まる」をメインテーマに、「弘まる御講」となるべく宗門を挙げて“御講の改良実践”に努めているところですが、新年の『年頭のことば』で講有上人は次のごとく仰せです。
〈佛立信仰の原点は「祈り」であり、(中略)その祈りは「菩薩の祈り」「ご弘通の祈り」でなければなりません。(中略)
佛立開講150年奉賛ご奉公の「御講の改良実践」も、「佛立菩薩を増やそう」とのご奉公も、すべて「口唱の改良」にかかっていることを肝銘(かんめい)し、(中略)〉云々。
そして次の開導聖人の御指南を頂かれます。
「妙法五字は日蓮が神(たまし)ひと仰(おおせ)られたり。我等御弟子旦那等(おんでしだんなとう)此(この)菩薩行の御流(おんながれ)をくまん者、此要法五字(このようぼうごじ)を弘めんが為に身(み)を労(ろう)し、心を尽(つく)して、唱死(となえじに)にしぬるを、真実の御弟子旦那の見識(けんしき)と思ひ定むべき也」
(暁鶏論〈ぎょうけいろん〉上・扇全11巻95頁)
因(ちな)みに今年の宗門の「弘通方針」では「佛立菩薩を増やそう」をスローガンに掲げつつ次のように記されています。
〈「御講から弘まる」というメインテーマには、“御講の改良実践によって弘まる御講になり、それによって御法の弘め手が生れれば自(おの)ずとご弘通は進捗(しんちょく)する”という心がこめられています。(中略)
“御講の改良実践”については①「参詣者を増やす」こと、そして、目ざすべき“ご弘通の成果”とは②「教化」(新しい教化親を増やす運動)と、③「育成」(新しい役中を生み、育てる運動)そして④「法燈相続」(法燈相続を確実にする運動)の実(じつ)をあげることと申せましょう。〉
また「宗務方針」でも山内宗務総長が、〔2〕の「弘通活動について」の中で、〈御講の改良実践を通じて、参詣者を増やし、新しい教化親を増やし、新しい役中を生み育て、法燈相続を確実にするご奉公を展開してまいります〉と記し、また〔3〕の「役中後継者養成と青少年の育成対策」でも、〈後継役中の養成と青少年の法燈相続は宗内の永遠の課題ですが、何としてでも実質的成果が上がるよう、リーダー研修会等を実施して促進をはかります〉と記し、さらに〔4〕では「教務の研修と意識改革」の大切さにも言及されているのです。
そもそも「教化」の語は「法華経」の中でも50回も使用されているという一事によってその重要さがわかります。その意は「教育感化(きょういくかんか)」「教導転化(きょうどうてんげ)」等だとされますから、本来の意に「教え育て、感化せしめる」「教え導くことによって人格を転じ変化せしめる」という意味があります。
特に「従地涌出品(じゅうじゆじゅっぽん)第15」には「教化」はもとより「化」「化度(けど)」の語が多出し、「教化衆生」(開結397頁)「教化令発心(りょうほっしん)」(同413頁)、「教化示導(じどう)」(同410頁)等と頻出します。仏の真実の教法たる妙法の教えによって衆生を感化し、発心せしめ、菩提・成仏へと導くことを指す語であるわけです。それはまさしく凡夫たる衆生を、凡夫ながらに菩薩へと転化せしめる営為に他なりません。つまり、妙法の受持信唱によって「凡夫を菩薩へと生まれかわらしめる」、これが「教化」の中身に他ならないわけです。このように、「教化」と「育成」は本来が一体不可分のものなのです。したがって「佛立菩薩を増やそう」とのスローガンは、当然ながら、教化と育成の両意を含むものであり、育成も重んじる本来の教化(菩薩行)の大切さを改めて提唱しているものだとも申せます。当宗の教えの内容はつまるところ「妙法の自唱他勧による菩薩行」であり、その目的は「菩薩行による自他の成仏、皆帰妙法・浄仏国土の顕現」です。そしてこのことは『妙講一座』の「五悔(ごげ)の要文(ようもん)」が「凡夫が菩薩(如来使)へと生まれかわる姿」を示すものであり(シリーズ⑬「懺悔[さんげ]の大事」(1)参照)、「宗風」が「弘通・教化に資し、浄仏国土顕現を期せんとする佛立信者のあるべき姿、佛立菩薩像を規範として宣明している」(シリーズ②参照)こととも通底します。
「育成」は、こうした「教化・菩薩行」の本意をよく踏まえ、これにそったあり方でなくてはならないわけです。
○「育成」に「手入れ」の感覚・観点を
「育成」に関する御教歌・御指南は実に多くあり、また観点・心得等も多岐にわたりますが、ここではまずその代表的なものをいくつか挙げさせていただきます。
御教歌
(1)「教弥実位弥下(きょうみじついみげ)」の心で
題・教弥実位弥下の六字に心をとゞめてこれを案(あん)ずべしと四信五品抄にあるを※「これを案ずべし」は「宝暦版」の文章か?
○奥深くわくる達者も足弱(あしよわ)の
ためには戻れ法(のり)の山口(やまぐち)
題・四五抄 教弥実位弥下の御(み)こゝろ
○中々にあゆまれぬ子はせなにおひ
つれてゆくこそおや心なれ
(2)甘やかさず厳しく折伏し鍛えよ
○愚(おろか)なる親は己(わ)が子をかあいとて
あまやかすのはにくむ也けり
○かあいさに気随(きずい)きまゝにそだておく
子の身ばかりの不仕合(ふしあわせ)なし
○折伏をせずにおくのは無慈悲なり
せめたればこそ信者とはなれ
○よしや子がうらまばうらめおやなれば
気随気侭(きずいきまま)にそだてぬがおや
(3)お世話(手入れ)の大事
題・折伏は慈悲第一
○捨(すて)おかばおのれそだちにわるうなる
弟子も植木もせは(世話)しだいなり
○我宿(わがやど)の捨(すて)そだちなる菊の花
さかとんぼりにをどりてぞさく
○すておきて教える人もあらぬ子の
遊ぶをみれば悲しかり鳧(けり)
開導日扇聖人御指南
○「仏教に随自(ずいじ)・随他(ずいた)の二門あり。随自の時は、人の意(こころ)をかんがみて気入(きにい)り、いひたき事も云(いわ)ぬと云(いう)やうの事をせず。俗に曰(いわく)、づけ/\物いふ也。仏説のまゝを守る也。我(われ)をほめられ、世に用(もち)ひられんとするやうの弱きへつらひ少しもなし。(乃至)いやならおきな。頼んで持(たも)たす法でなし。頼むとならば授くべし。なれども幼稚に教ふることなれば、ことをわけて、おこ(怒)らぬやうに程よく論(ろん)[諭](さと)すべし。これ大慈大悲也」
(末法折伏の時也の事・扇全17巻10頁)
※随自意(ずいじい)…み仏がご自身のご本意に随い真実を説くこと。〔折伏〕
※随他意(ずいたい)…み仏が衆生(他人・相手)の心に合わせ随って説くこと。〔摂受(しょうじゅ)〕
○「持(たも)ち始(はじめ)は小児をそだつるが如し。気随気侭(きずいきまま)をさせぬやう、行儀よく謗法をあらたむべし」
(講談要義上下・扇全3巻268頁)
○「当機相応談(とうきそうおうだん) すてそだちの子にかしこきはなし。身を持(も)ちたる者まれ也。(乃至)愚人(ぐにん)をたらし育てにせしは悞(あやまり)也」
(鶏鳴暁要弁〈けいめいあかつきようべん〉下・扇全10巻156頁上欄)
○「当宗は折伏宗也。慈悲の最極(さいごく)也。
師匠はきびしきがよい。たらし随他に育(そだて)たる信者は皆経力(みなきょうりき)をしらず。親の教へは厳重なるが子の為也」
(和国陀羅尼〈やまとだらに〉・扇全14巻313頁)
○「物を教へるのには心をしづめてゆる と教へる事。(乃至)信徒に教へ置(おき)もと思ひて、心のみいら(焦)れすれども、かためて一度(に)教へていくものではなし。故に一口宛(ひとくちあて)、とっくりと合点(がってん)のゆく迠(まで)教へねば、生教(なまおし)へにては教へぬも同じ事也」
(名字得分抄(中)・扇全14巻131頁)
○「楠正成(くすのきまさしげ)の語に、ほめるときには必ずいましめの言(げん)をまぜよ」
(開化要談(宗)・扇全13巻368頁)
○「当講内は初心(しょしん)の人をそだつるを第一と心得(こころう)べき也。初心が後心(ごしん)になるもの也。謗法あらばあらく呵責(かしゃく)せず、よくわけのわかるやうに説き示すべし。謗法を見かくし聞(きき)かくしはする事叶(かな)はず。開山(かいさん)曰、謗法人たりとて憎むにあらず。地獄に落(おつ)るをあはれと思ふよりの折伏ならば、只強気(ただつよき)にいひはり、問答ごし(腰)になりて追ひちらすにあらず。其(そ)れ時による事也。もとの慈悲をわするゝ事なかれ」
※「開山」…門祖日隆聖人
(青柳厨子〈せいりゅうずし〉法門抄第二・前書・扇全3巻11頁)
○「されば堅信(けんしん)の行者より、堅信の子を生み出(いだ)す事肝要也」
(法場必携・扇全8巻233頁)
○「植木の性(しょう)、その地により、せわやきてかひあるとかひなきと、捨置(すておき)てよくそだつものとそだてにくきと種々(しゅじゅ)也。地も相応不相応あり。植木の性によりて同じやうにはいかぬ。(乃至)植(うえ)かへて付(つ)くまでが大事也。 信者教化も講元(こうもと)組長は植木やの如し。勉強し下(たも)ふべき也」
(誡勧〈かいかん〉両門・扇全5巻281頁)
こうして拝見させていただくと、新入の教化子やご信者、法燈相続の対象たる弟子に対しては、根本に慈悲の折伏の心(随自意)を踏まえながらも、親が子に対する親心で、親身になり、また初心者で未熟な相手の能力や性分(機根〈きこん〉)に合わせ、「位弥下の心」(シリーズ⑨⑩)で易しく少しずつ教え導き、育成していくことが大切であることがよくわかります。つまるところ「植木の性によりて同じようにはいかぬ。(乃至)植木やの如し。勉強し下ふべき也」ということです。植木屋は、植木の性分に応じて「世話」をし「手入れ」をして育てるのが仕事です。ところがこの「手入れ」の大切さを見失いつつあるのが現代人なのです。養老孟司(たけし)氏は、そのことを近著の中で次のように言っています。
〈「手入れ」は、自然とつきあうときにだけ必要なのではない。身づくろい、化粧、子育てなど、日常生活のあらゆる場面に関わって、いる。(中略)心の底に「手入れ」という気持ちがあるかどうかで、小さな判断すら変わってくる。「手入れ」とは、まず自然という相手を認めるところから始まる。(中略)自然は予測不能だと述べた。子供の将来を予測することは完全には出来ない〉
〈勿論「手入れ」というのは、だから加減がむずかしい。(中略)相手のおかれている状態を知り、これからどのように変化するのかを、あるていど予測しなければならない。それには対象と頻繁(ひんぱん)に行き来し、相手のようすに合わせて手の加え方を決めていく必要がある。(中略)「手入れ」と「コントロール」は違う〉
(『いちばん大事なこと』集英社新書100~102頁)
氏の言う「コントロール」は機械的な完全制御のことであり、換言すれば、こちらの思惑通りに相手を型にはめようとすることです。これに対して「手入れ」は、相手の特性を認め、現在の状態を見極め、さらに今後の変化も予測しつつ、しかるべき手を加えていくあり方です。人間も自然の一部ですから、当然そうあるべきだというわけで、この姿勢・観点は開導聖人が仰せの「植木の世話」「植木屋の勉強」と相通ずると存じます。「捨置き」「捨育ち」はいわば「手つかずの自然」「素っぴんの顔」であり、「コントロール」は「人工植林の杉山」や「整形の顔」に、「手入れ」は「里山」や「程よく化粧された顔」に当たるでしょう。「手入れ」を「育成」で申せば、いきなり、無理にこちらの思惑通りの信者の型にはめようとするのではなく、まず相手の資質や能力を認めつつ、その中に眠っている資質(仏性)を啓発し、自覚を促すよう、適切なお世話(手入れ・折伏)をして、次第に佛立信者へ、菩薩へと育ててゆくということになるでしょう。ただしここで注意すべきは、基本に慈悲の折伏心を忘れず、摂受(しょうじゅ)に流されないことです。
また適切な「手入れ」には、相手の情況の把握が不可欠です。「頻繁な行き来」の大切さはそこにあります。
さらに付言すれば、育成し、信心をつかませる要諦は「経力・現証」を感得させることです。そのためには「助行」に連れ参詣させることも効果的です。しかし何にせよ、実際に一つひとつ手を取って教えることが基本です。元来が「手入れ」には「努力・辛抱(棒)・根気」が求められるのです。参詣・お給仕・ご有志の仕方はもとより、お塔婆の申し込み方、祈願の仕方等々を、相手に付きそって一つずつ現場で教え導いていくことが大切なのです。「庭訓(ていきん)」というのは「家庭の教訓。躾(しつけ)」の意ですが、元は、孔子が庭を横切ってゆく息子の伯魚(はくぎょ)を呼びとめ、その都度一つずつ訓導していったことに由来する語だとされます(論語・季氏第16の第13段・岩波文庫377頁参照)。ご信者の育成にも、親が子に折りに触れてその都度一つずつ指導・訓育していく「庭訓」の姿勢、現場でまめに教えていくあり方が求められているのです。
最後に、近代になって作られたとされる諺(ことわざ)を一つ紹介しておきます。いわく
「三つ叱(しか)って五つ褒(ほ)め七つ教えて子は育つ」
『岩波ことわざ辞典』によれば「子供を叱るのは少しにし、多くほめてたくさん教えてやるのがよいということ」とあり、「可愛くば五つ教えて三(み)つほめて 二つしかりて善(よ)き人(ひと)にせよ」等の古歌などの影響もあるようだと付記されています。なお、同辞典の編集に携(たずさ)わった編集部が出した『ことわざの智慧』(岩波新書・別冊7)にはこうあります。
「誰しも叱られるより褒められる方がうれしいにきまっている。うれしければこれからも学んで行こうという気になろう。そういう気持ちを持ち続ける子がよく育たないわけがない。教育の極意というべきである。
三・五・七という奇数は良い数とされる。叱る、褒める、教えるそれぞれの割合を示しているのだが、厳密な比率をいうものではない。叱るのは褒めるより控えめに、といった程度の指標だろう」 (同書・155頁)
なお東京工大名誉教授の芳賀綏(はがやすし)氏は近著『日本人らしさの構造―言語文化論講義―』(大修館書店・平成16年11月刊)の中で、次のように指摘しています。
〈アジアも含めた諸外国の対人意識・文化が凸(とつ)型であるのに対して日本の文化・対人意識は概して凹(おう)型である。それは「やさしさの対人意識」であって、相手を傷つけたくない、相互依存を前提としている。そしてそれは相手を傷つけないかわりに自分へのいたわりを求める甘えも含んでいる〉(取意。正確には同書40頁以下参)。このように基本的に攻撃型ではなく受容型が日本人の意識・文化の特性だとすれば、相手にもよるでしょうが、実際上の現場での対人的な折伏・育成のあり方もよほど柔軟であることが求められていると申せましょう。
凹形・受容型で傷つき易い相手に対して、「手入れ」の感覚を取り入れた折伏というのは具体的にはどういうものでしょう。
例えば相手の誤りを注意する際、「これはどうしたの?あなたほどの人が」といった表現や姿勢はどうでしょう。これなら基本的には相手を認め、その人格を尊重しながらの注意ですから、決定的に傷つけることなく改良・発奮を促すことができそうです。

- ㊱「憶持不忘(おくじふもう)」と「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」(2)
- 2016年1月27日(水)
―「忍難弘経(にんなんぐきょう)」を覚悟の受持(じゅじ)―
○苦難を覚悟して持(たも)つ
前回は、「提婆達多(だいばだった)こそ善知識(ぜんちしき)」という見出しで、法華経提婆達多品第12や、日蓮聖人の『種種御振舞御書(しゅじゅおんふるまいごしょ)』の一節などをいただきつつ、特にお役中は、自分に対し、敵対し、迫害を加える人や逆境こそが、自分を鍛え向上せしめる「善知識」だと頂戴させていただくことが大切である旨申しました。
そして、その際注意すべき心得として、「いわゆる独善に陥(おちい)らぬよう、謙虚な自省心も忘れないように」とも記しました。開導聖人も「自見(じけん)によらば必ず謗法を起(おこ)す也」(一講一紙要談抄・扇全8巻106頁)とお誡(いまし)めのごとく、仏祖のみ教えをいただいているつもりが、実は凡夫の我見をまじえたものとなっていたら、それは誤りであり、周囲の反発はその誤りに対する当然の批判であって、それならその批判の方が正しいのですから、その場合は謙虚に批判を受け止め、自身が反省・改良せねばならないはずです。つまり謙虚さや柔軟性も大切なのです。
にもかかわらず、自分は常に正しいと思い込み、批判はすべて「善知識」であり、いわば「法難」だから、「これに屈せず一層頑張ろう」などと奮起されるのは、周囲にとっては実に迷惑な話です。
日蓮聖人にとっての「善知識」は、あくまでも正法たる法華経の教え、み仏の金言(きんげん)に随順し、常にそのみ教えに自身を照らし合わせながらのものでした。
例えば佐渡ご流罪中に認(したた)められた『開目抄』(文永9年・数え51歳・於塚原三昧堂)では次のように仰せです。
「又云(またいわ)く『数数見擯出(さくさくけんひんずい)』等云云、日蓮法華経のゆへに度度(たびたび)ながされずば、数数(さくさく)の二字いかんがせん。(乃至)末法(まっぽう)の始(はじめ)のしるし恐怖悪世中(くふあくせちゅう)の金言のあ(合)ふゆへに但日蓮一人(いちにん)これをよめり。(乃至)此等皆仏記(これらみなぶっき)のごとくなりき。(乃至)当世法華の三類(さんるい)の強敵(ごうてき)なくば誰(たれ)か仏説を信受せん。日蓮なくば誰をか法華経の行者として仏語をたす(助)けん。(乃至)経文に我身普合(わがみふごう)せり。御勘気(ごかんき)をかほ(蒙)ればいよいよ悦(よろこび)をますべし」(開目抄(上)・昭定560頁)
「数数見擯出」とは法華経勧持品(かんじほん)第13の中に「数数見擯出(さくさくけんひんずい) 遠離於塔寺(おんりとうじ)」(数数擯出[しばしばひんずい]せられ塔寺[とうじ]を遠離[おんり]せん)(開結365頁)とあり、「数数」は「しばしば」、「擯出」は「流罪」の意ですから「何度も流罪せられ、お寺から追い出される」という意です。「恐怖悪世中」というのも同じ勧持品の中に「於仏滅度後(おぶつめつどご) 恐怖悪世中(くふあくせちゅう)」(仏の滅度の後[のち] 恐怖悪世の中に於て)(開結363頁)とあり、「仏滅後の末法悪世の恐るべき時代においては」との意です。
つまりみ仏が法華経勧持品の中にその金言(仏語、仏記)として、「末法悪世は恐るべき時代であり、そこで妙法を弘通せんとする法華経の行者には必ずや『三類(さんるい)の強敵(ごうてき)』(①俗衆増上慢[ぞくしゅうぞうじょうまん] ②道門[どうもん]増上慢 ③僭聖[せんしょう]増上慢の三類。「俗衆」は世門世俗の人々、「道門」は仏門の僧侶、「僭聖」は世に聖人・生き仏等と尊崇されながら内実はそうではない権勢ある高僧のこと)に怨(あだ)まれ怨嫉迫害(おんしつはくがい)が相次ぐことが明記されているのです。
日蓮聖人は、この法華経の金言の一つ一つに、自身を重ね合わせ、それらの仏語のすべてに自身の迫害の種類や内容が合致するかどうかを検証されるのです。そして、「すでに他の迫害(悪口罵詈刀杖瓦石[あっくめりとうじょうがしゃく]、三類の強敵等)のすべてが経文通りに現実のものとなっており、ただ一つ残っていた『数数見擯出』も、先年経験した伊豆伊東の流罪に加えて、今回の佐渡流罪によって『数数』の二字を満たした。これで確かに仏の金言として法華経に記された全ての迫害を、経文通りに身に受けたのだから、これでまさしく日蓮が末法の『法華経の行者』だと申すことができる」、と仰せなのです。
「経文に我身普合(わがみふごう)せり。御勘気をかほ(蒙)ればいよいよ悦(よろこび)をますべし」とあるのは、まさしく、聖人ご自身が「これで勧持品の仏語のすべてに合致(普合とは普[あまね]く合致する意)した。それも今回幕府の怒り(勘気)によって、竜(たつ)の口(くち)の首の座から佐渡流罪となったことによって経文に普合することができたのだから、これは実に喜悦(きえつ)すべきことなのだ」と仰せになっているのです。
このように、日蓮聖人はすべてを法華経に示されたみ仏の金言に引き合わせ、検証を重ねておられるのです。「法華経の行者」と名乗られるのもその上でのことです。しかもなおその上で、さらに次のように仰せです。
「但し世間の疑(うたが)いといい自心(じしん)の疑ひと申し、いかでか天扶(てんたす)け給(たまわ)ざるらん。諸天(しょてん)等の守護神は仏前の御誓言(ごせいごん)あり。法華経の行者には〈乃至〉早早(そうそう)に仏前の御誓言をとげんとこそをぼすべきに、其義(そのぎ)なきは我身(わがみ)法華経の行者にあらざるか。此疑(このうたがい)は此書(このしょ)の肝心、一期(いちご)の大事なれば、所所(しょしょ)にこれをかく上(うえ)、疑を強くして答をかまうべし」(開目抄(上)・昭定561頁)
「法華経の行者を昼夜に守護すると、諸天善神がみ仏にお誓いをしている(諸天昼夜常為法故而衛護之[しょてんちゅうやじょういほうこにえいごし]―諸天は昼夜に常に法の為の故に而(しか)も之(これ)を衛護す・安楽行品第14・開結382頁)のに、日蓮とその弟子信者がこれほどの大難・迫害にさらされているのを、なにゆえ諸天は放置し救けてくれないのか。世間の疑いも、日蓮自身の心の疑念もそこにある。これは日蓮が真実の法華経の行者ではないということであろうか。この疑念(を晴らすことができるかどうか)はこの書(開目抄)の肝心であり、日蓮一期の大事であるから、このことに関してはこの書の随所に記するから、読む者も強く疑問を持ちつつ、日蓮が示す答えに相い対してほしい」との意です。
ご承知のように、日蓮聖人は上行所伝の妙法こそが末法の一切衆生を救済する唯一の大法だとの確信のもとに32歳で立教開宗をされ、以来20年間妙法弘通の一筋に邁進(まいしん)してこられました。けれども開宗以来のご生涯は文字通り相次ぐ迫害の連続であり、聖人ご自身はもとより聖人を信じ随(したが)ってきた弟子信者も怨嫉の中に身をさらし続けてきたのです。もちろん迫害を覚悟の上でのご奉公でしたが、今度の迫害は聖人の命(いのち)はもとより、教団そのものの壊滅をも企図するもので、文字通り教団全体に対する強権による大弾圧だったのです。しかもこの期に及んで諸天の守護も顕れないのであれば、それがもし聖人が真正の法華経の行者でないためだとすればこれほどの大事はありません。ご自身が誤ったことによって、弟子信者はもとより多くの人びとをも誤りに導き、徒(いたず)らに迷わせ苦しめてしまったことになります。「我身法華経の行者にあらざるか。此疑は此書の肝心、一期の大事なれば」と明記され、さらに「疑を強くして答をかまうべし」とのお言葉には、聖人の偽らぬ率直なお心が吐露されていると拝します。
少し長くなりましたが、ここで申しあげたいのは、聖人は決して独善的・狂信的な宗教者ではなかったということです。いやむしろ真摯(しんし)な求道(ぐどう)によって得た確信を以て開宗され、ご弘通をされた聖人であればこそ、真率かつ謙虚な自省心を持ち続けておられたのです。こうしたご自身に向けた疑念への真摯な問いかけを通じてこそ、それを超克しての本当のさらなる前進があるのだと拝察されるのです。『本尊抄』が「法開顕(ほうかいけん)の書」とされるのに対してこの『開目抄』が聖人の「人開顕(にんかいけん)の書」であり、「上行自覚(じょうぎょうじかく)」(本化[ほんげ]上行菩薩の後身[ごしん]だとのご自覚を示される)の書だとされるのも、この疑問を率直かつ真摯に自己に受けとめられ、厳しくその検証を重ねられる過程が如実に記され、そしてその上での新たなゆるぎない確信が示されているからに他ならないと存じます。
○「深い謙虚さ」と「ゆるぎない誇り」の兼備を
聖人は、もとより自らは「石中(いそなか)の賎民(しずたみ)が子」(善無畏三蔵抄)、「海辺の旃陀羅(せんだら)が子」(佐渡御勘気抄)、「片海(かたうみ)の海人(あま)が子」(本尊問答抄)であって、罪根甚重の凡夫であるとのご自覚を生涯にわたってお持ちでした。このいわば「凡夫日蓮」の自覚を持ちながら、同時にその一方で自己に対する厳しい内省と検証を重ねつつ「法華経の行者」、「地涌(じゆ)の菩薩」、「上行後身の如来使」との自覚を確立・開顕してゆかれるのです。聖人ご自身がこのような姿勢であられたということも、私共は決して忘れてはならないと存じます。
聖人は、『開目抄』(文永9年2月)の直後に記された『佐渡御書』(同3月)で、次のようにも仰せです。
「日蓮も、又かく責めらるるも先業(せんごう)なきにあらず。〈乃至〉何(いか)に況(いおう)や日蓮今生(こんじょう)には貧窮下賎(びんぐげせん)の者と生まれ、旃陀羅(せんだら)が家より出(い)でたり。心にこそ少し法華経を信じたる様なれども、身(み)は人身(にんしん)に似て畜身(ちくしん)也。〈乃至〉又過去の謗法を案ずるに誰(たれ)かしる。〈乃至〉宿業(しゅくごう)はかりがたし。鉄は炎打(きたえう)ちて剣(つるぎ)となる。〈乃至〉我が今度(こんど)の御勘気(ごかんぎ)は世間の失一分(とがいちぶん)もなし、偏(ひとえ)に先業の重罪を今生に消して、後生(ごしょう)の三悪(さんなく)を脱(のが)れんずるなるべし」(昭定614頁)
このように聖人は定業堕獄の凡夫との自覚を明確に持ち、過去の謗法の罪障をこの度の大難を受けることによって消滅し、後生に三悪道(地獄・餓鬼[がき]・畜生の三悪道)に堕することを脱することができるのだ、と受けとめておられるのです。
私共が『妙講一座』の「随喜段」(「あゝ有難や」の御文)の中で、先に「あさましや我身の上をかへりみれば(乃至)三毒強盛なり」と唱えつつ後に「本化上行の流類(りゅうるうい)読持此経(どくじしきょう)是真仏子(ぜしんぶっし)といはれ」と言上申しあげるのも同じ意です。ここには「三毒強盛の凡夫」でありながらも、こうして妙法を信受する佛立信者とならせていただいた身の上は「本化上行の流類・是真仏子」の大果報を頂戴している存在でもあるのだ、との悦びが表白されているのですから。ここにも「罪障の深い凡夫」の自覚と「上行流類・是真仏子」の自覚とを同時に持つべきことの大切さが明記されているのです。どちらか一方に偏(かたよ)るのではなく双方の自覚を同時に持つことが大切なのです。一方に偏るのは卑屈と傲慢(ごうまん)のどちらかに陥ることに他ならないのですから。苦難を真の「善知識」として受けとめつつ、双方の心を同時に持ち、それをいつも忘れない、そこにこそ「真の謙虚さ」と、苦難にもゆるがない「強固な誇り」との両者を兼ね備えた法華経の菩薩の姿があるのです。
実は、日蓮聖人が仰せになる「憶持不忘(おくじふもう)」の意も、「難に値(あ)うことを覚悟して妙法を受持する」ということが土台となっています。
○値難(ちなん)を覚悟の「憶持不忘(おくじふもう)」
『岩波仏教辞典』によれば、「憶持(おくじ)」とは「記憶して心に持(たも)つこと。心に記憶して忘れないこと。翻訳語としては憶念(おくねん)と同一。(中略)しかし、中国・日本で、憶念と区別して理解される場合、憶持には〈受持して忘失しない〉というニュアンスが濃い」とあります。
出典としては、法華経の結経(けっきょう)である『観普賢菩薩行法経(かんふげんぼさつぎょうほうきょう)』に「爾(そ)の時に行者、普賢の深法(じんぽう)を説くことを聞いて、其(その)の義趣(ぎしゅ)を解(げ)し、憶持して忘れじ。(解其義趣[げごぎしゅ] 憶持不忘[おくじふもう])」(開結610頁)があります。つまり「教えを聞き、理解して忘れない」という意味です。
「憶持不忘」の基本的な意味は右の通りですが、日蓮聖人の示される「憶持不忘」はそれだけではありません。「苦難・迫害に値(あ)っても妙法を受持し、決して退転しない」ということですから、通常の「憶持不忘」に「値難を覚悟して」の意が加わるのです。
日蓮聖人は四条金吾に宛てた御消息(ごしょうそく・お手紙)に次の如くお示しです。
「此経難持(しきょうなんじ)事。〈乃至〉此経(このきょう)をききうくる人は多し、まことに聞受(ききうく)る如くに大難来(きた)れども憶持不忘の人は希(まれ)なる也。受(うく)るはやすく持(たもつ)は難(かた)し、さる間(あいだ)成仏は持(たもつ)にあり。此経(このきょう)を持(たもた)ん人は難に値(あう)べしと心得て持(たも)つ也。〈乃至〉三世(さんぜ)の諸仏の大事たる南無妙法蓮華経を念ずるを、持(たもつ)とは云(いう)也。〈乃至〉天台(てんだい)大師の云(いわく)『信力(しんりき)の故(ゆえ)に受(う)け、念力の故に持(たも)つ』云云。又云『此経(このきょう)は持(たも)ち難(がた)し、若(も)し暫(しばら)くも持(たも)つ者は我即(われすなわ)ち歓喜(かんぎ)す、諸仏も亦然(またしか)なり』云云。火にたきぎ(薪)を加(くわう)る時はさかん也。大風吹(ふか)ば求羅(ぐら)は倍増する也。〈乃至〉法華経の行者は火と求羅との如し、薪と風とは大難の如し。〈乃至〉此より後(のち)は此経難持の四字を暫時(ざんじ)もわすれず案じ給べし」 (四条金吾殿御返事・昭定894頁)
この御消息は文永12年(建治元年)3月6日付ですから、日蓮聖人は54歳、前年の春赦免(しゃめん)されて佐渡から帰還し、身延へ入山された直後です。なお付言すれば、前年の文永11年10月には聖人の諫言(かんげん)通り、第一回目の蒙古襲来(文永の役[えき])が起こっています。
「信力の故に受(う)け、念力の故に持(たも)つ」の文は、天台大師の『法華文句(ほっけもんぐ』(第8・大正蔵34巻107頁C)の中の「信力故受念力故持(しんりきこじゅねんりきこじ)」の訓(よ)み下(くだ)しです。これは法華経の法師品(ほっしほん)第10に示される「五種法師(ごしゅほっし)」[受持(じゅじ)・読(どく)・誦(じゅ)・解説(げせつ)・書写(しょしゃ)のこと]の第一「受持」の義を釈したものであり、「此経難持」の御文は、法華経見宝塔品(けんほうとうほん)第11の結文(けちもん)となる偈文(げもん)で『妙講一座』にも採録されており、ご引用の「諸仏も亦然なり」云云の後には、「如是之人(にょぜしにん) 諸仏所歎(しょぶつしょたん) 是則勇猛(ぜそくゆみょう) 是則精進(ぜそくしょうじん)」(是[かく]の如[ごと]きの人[ひと]は諸仏の歎[ほ]めたまふ所なり。是[こ]れ則[すなわ]ち勇猛[ゆみょう]なり。是れ則ち精進[しょうじん]なり)と続きます。そしてさらに、そのような行者こそ「即(すなわ)ち為(こ)れ疾(と)く無上(むじょう)の仏道を得たり、〈乃至〉是(こ)れ真(しん)の仏子、淳善(じゅんぜん)の地(じ)に住(じゅう)するなり」(即為疾得(そくいしっとく) 無上仏道(むじょうぶつどう)〈乃至〉是真仏子(ぜしんぶっし) 住淳善地(じゅうじゅんぜんじ)と説かれているのです。
また「求羅(ぐら)」とは「迦羅求羅(からぐら)」の略で、想像上の虫の名であり、風を受ければ受けるほど大きく成長し、ついにはすべてを呑み込むとされます。『上野殿母御前返事』に「からぐらと申す虫は風を食(しょく)とす。風吹かざれは生長せず。〈乃至〉仏も亦(また)かくの如く法華経を命とし、食とし、すみかとし給なり」(昭定1817頁)とも仰せです。先の御消息では「法華経の行者はあたかも火と求羅のようなものだ。薪と風とは大難のようなものだ。だから法華経の行者は大難に値(あ)えば値うほど大きく成長するのだ」と仰せになり、「だからこそ『此経難持』の御文を常に忘れないようにせよ」と結ばれているのです。
日蓮聖人のみ教えにおける「憶持不忘」は「値難(ちなん)を覚悟」しなければならず、その意味で「此の経は持(たも)ち難い」けれども、そこを堪えて忍難弘経(にんなんぐきょう)を貫(つらぬ)く行者こそが「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」の真の法華経の行者であり、速やかに成仏を遂げる「是真仏子」なのだということです。
このように「値難を覚悟」し「此経難持」を前提とした「憶持不忘」は、実は同じく佐渡で著された『如説修行抄』に示される「されば此経(このきょう)を聴聞(ちょうもん)しはじめん日より思ひさだむべし。況滅度後(きょうめつどご)の大難三類(だいなんあんるい)甚(はなはだ)しかるべしと」(第1段)、あるいは「唱死(となえじに)」(第6段)
と示される決定(けつじょう)の信心と同義だということがわかります。
○「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」も難(なん)に屈せず貫(つらぬ)くこころ
「精進」とは梵語で「ビリヤ」といい、元の意に「勇気」という意味も含んでいます。ですから「勇猛精進」は「嫌気(いやけ)ささず、投げ出さず貫き通すこと」を意味しているのです。
法華経にも随所に見える語で、そのいくつかを挙げれば次のようにございます。
「勇猛精進」(序品[じょほん]・開結66頁)、「勤加(ごんか)精進」(信解品[しんげほん]・同187頁)、「昼夜(ちゅうや)常(じょう)精進」(従地涌出品[じゅうじゆじゅっぽん]・同408頁)、それに先の見宝塔品(けんほうとうほん)の「是則勇猛 是則精進」(同340頁)等です。「精」は「クワシク」、「進」は「ススム」とも解されますから、心をこめ、念を入れて進み続ける意でもあります。ただし、日蓮聖人の「勇猛精進」は「憶持不忘」「忍難弘経」の「勇猛」であり、「精進」なのだということを忘れてはなりません。
最後に開導聖人の御教歌と御指南もいただいておきます。
開導日扇聖人御教歌
○わすれてはおもひ出(いだ)して
はげめどもをこたりがちに成(なる)ぞくやしき
(本尊抄会読(三)・扇全6巻141頁)
○題・信者の一心の家の内に信謗(しんぼう)の二人主(あるじ)を争ふ
わすれぬをたもつといへば法華経の
かたきを責(せめ)よおのが心の
(十巻抄(一)・扇全14巻370頁)
御指南
「賞罰現証に感じて、本尊並(ならび)に尊像(そんぞう)を生身(しょうじん)にていますものと決信(けっしん)して月年(つきとし)を送れども忘れぬ。同じ調子なる人、諸組の中に随分あり。又日々(ひび)に遠ざかるは忘るゝ也。〔ワスルヽハ〕信心のゆるむ也。あさまし」(開化要談 用・扇全13巻403頁)
○せめて「心内の三類」に負けぬように
現代では憲法で「信教の自由」が保障されており、妙法を弘通したからといって強権の弾圧・迫害にあうことはまずありません。せいぜい身内や周辺からの反発がある程度でしょう。もちろん、それはそれで大変苦しい場合もありますが、せめてそれくらいの苦難は覚悟し、信心を決定(けつじょう)してご弘通に精進させていただきたいものです。また、それにも増して忘れてはならないのは、いわゆる「心内の三類」であり「おのが心の敵」です。凡夫持ち前の貪・瞋・癡(とん・じん・ち)の三毒(さんどく)や、疑迷(ぎめい)・不信(ふしん)・懈怠(けだい)の心に負けて信心を忘れ、精進を忘れて懈怠の謗法に陥らぬよう、お役中自身はもとより、ご信者相互に折伏し合い、励まし合う努力が求められているのです。
「無始已来」の御文で「今身(こんじん)より仏身(ぶっしん)に至(いたる)まで持奉(たもちたてまつ)る」と言上し、「宗風」の第2号【受持(じゅじ)】で「受持の一行に徹する」と教えられながら、御指南のごとく、たとえ現証によって一度は信心が決定(けつじょう)できたとしても、年月を経るとともに信心がゆるみ、御法から心が離れ、ついに忘れてしまうことが多いのも凡夫の常です。「憶持不忘」「勇猛精進」を、「せめて心内の三類に負けず受持(じゅじ)せよ」と誡めておられる教えとして頂戴するのは、現代のお互いに即しての、いわば「せめてものいただき方」ではないでしょうか。

- ㉟「憶持不忘(おくじふもう)」と「勇猛精進(ゆみょうしょうじん)」(1)
- 2015年12月3日(木)
―「忍難弘経(にんなんぐきょう)」を覚悟の受持(じゅじ)を―
○「提婆達多(だいばだった)こそ善知識(ぜんちしき)」
前回は、「逆縁正意(ぎゃくえんしょうい)と逆即是順(ぎゃくそくぜじゅん)」(2)―逆即是順・ご罰(ばち)即ご利益(りやく)―のテーマで、次のようなことを申しました。
「逆縁」がそのまま「順縁」になる「逆即是順」の理は、いわば転換・逆転の妙理であって、それが認められ説かれるのは、円融(えんゆう)・円満の最高の教え(円教[えんぎょう])である法華経なればこそのことであること。だからこそ釈尊に敵対し、殺害しようとまでした極悪人の提婆達多(だいばだった)でさえ成仏の授記(じゅき)を得られたのである。そしてこのことは、実は提婆に等しい罪根甚重(ざいこんじんじゅう)・定業堕獄(じょうごうだごく)の荒凡夫(あらぼんぶ)たる私共末法の衆生も、妙法の受持信唱によってこそ定業を能く転じて成仏の果報にあずかることができるということを示してくださっているのだ、ということなのです。また法華経の中に示された「逆即是順」の姿の例として「長者窮子(ちょうじゃぐうじ)の譬(たとえ)」(信解品)や「良医病子(ろういびょうし)の譬(たとえ)」(如来寿量品)の父と子の関係(仏と末法の衆生の関係)―反発・反抗(逆縁)を通じ、それが順縁に転じていく姿―も紹介させていただき、同じ妙理は「ご罰」がそのまま「ご利益」に転じる「ご罰即ご利益」の理法にも通底していることにも触れ、次のように結びました。
〈法華経の「逆即是順」の妙理は「ご罰即ご利益」はもとより、総じてダメだと棄(す)てられ、否定され、マイナス評価しか与えられなかったものを、活かし、肯定し、さらにはプラスの評価へと逆転せしめる、いわば「発想の転換」・「逆転の発想」を促すものなのです。「妙とは蘇生(そせい)の義なり」(法華題目抄・昭定402頁)とは、実に言い得て妙だと存じます〉。
こうした「逆を順へ」、「悪を善へ」、「罰をご利益へ」と転換せしめて受けとめていく積極的な姿勢や発想のあり方は、法華経の「善知識(ぜんちしき)」の把え方でもよくわかります。
「善知識」(ぜんぢしきとも)は、悪知識の対語で、単に「知識」ともいい、「善友(ぜんぬ)」「勝友(しょうゆう)」等とも申します。①正法を説き、人をして仏道に入らしめ、成仏へと導く人、②仏道に縁を結ばしめる人のことを意味する語です。いわば仏道における「よい先生」「指導者」のことです。
法華経には次のようにあります。
「爾(そ)の時の王とは則(すなわ)ち我が身是れなり。時の仙人(せんにん)とは今の提婆達多是(こ)れなり。提婆達多が善知識に由(よ)るが故に、我をして[中略]具足(ぐそく)せしめたり。等正覚(とうしょうがく)を成(じょう)じて広く衆生を度(ど)すること、皆(みな)提婆達多が善知識に因(よ)るが故なり」
(提婆達多品第12・開結346頁)
釈尊が前世に王であったとき、妙法を頂戴するために師として仕えた阿私仙人(あしせんにん)こそが提婆達多の前世の姿だったのです。その阿私仙が今は提婆と生まれ、釈尊に敵対し、迫害を加えているわけですが、「実は提婆達多こそが私の善き師であり、彼のおかげで私は成道して仏となることができたのである。さらには私がこうして広く衆生を済度しているのも、彼が善知識となってくれたおかげなのだ」と仰せなのです。この阿私仙に対して王が仕える様について経文には「法の為の故に精勤(しょうごん)し給侍(きゅうじ)して」、「情(こころ)に妙法を存(ぞん)ぜるが故に、身心懈倦(しんじんけけん)なかりき。普(あまねく)く諸(もろもろ)の衆生の為に大法を勤求(ごんぐ)して、亦(また)己(おの)が身(み)及び五欲(ごよく)の楽(らく)の為にせず。故(かるがゆえ)に大国(だいこく)の王と為(な)って勤求して此(こ)の法を獲(え)て遂(つい)に成仏を得ることを致せり」(開結346頁)等とあります。
王が妙法を勤求し、精勤給侍する姿については、このシリーズの⑦の「参詣の大事(3)―給仕について―」で、『身延山御書』(昭定1912頁)の御文も頂きながら、やや詳しく触れておりますのでご参照ください。なお「精勤」とか「勤求」の語も、後に触れる「精進」や「憶持不忘」とも関連がありますので、少しだけ心に留めておいてください。
日蓮聖人は次の如く仰せです。
〈相模守(さがみのかみ)殿こそ善知識よ。平左衛門(へいのさえもん)こそ提婆達多よ。(乃至)摩訶止観第五に云く「行解(ぎょうげ)既(すで)に勤(つと)めぬれば三障四魔(さんしょうしま)紛然(ふんぜん)として競(きそ)ひ起(おこ)る」文。(乃至)釈迦如来の御(おん)ためには提婆達多こそ第一の善知識なれ。今の世間を見るに人をよくなすものは、かたうど(方人)よりも強敵(ごうてき)が人をばよくなしけるなり〉
(種種御振舞御書・昭定971頁)
第8代執権(しっけん)・北条時宗(ときむね)[相模守]こそが、日蓮にとっては善智識である。また平左衛門尉頼綱(へいのさえもんじょうよりつな)こそが、日蓮にとっては釈尊における提婆達多の如き存在(つまり善智識)である。天台の『摩訶止観』にも、信行に精進し、信心増進すれば、必ず様々な怨嫉迫害(おんしつはくがい)が競うようにむらがり起こる、とあるのもそのような意でいただかねばならない。釈尊のためには提婆達多こそが第一の善知識であった。今末法の世相を見ても、真実に人を成長せしめるのは、その人の味方よりも、その人にとっての強敵・ライバルなのである、との意です。
北条時宗は、日蓮聖人当時の鎌倉幕府の政権担当者として、お祖師様とその教団に弾圧・迫害を加えた最高責任者ともいうべき立場にあった人ですし、平左衛門尉頼綱は、竜の口の法難をはじめ、直接弾圧を指揮した張本人です。でも、こうした迫害を加えた大敵ともいうべき人々こそが、聖人にとっては善智識であり、自分を鍛え、信心を増進せしめ、成仏と導いてくれた人なのだと仰せなのです。
常識的には、それこそが善知識・善友だと思われる自分の身内・味方である人よりも、一見「悪知識」としか思えない敵対・迫害する人の方が、実は自身にとっては善知識なのだという受けとめ方も、まさしく逆転の発想であり、ここにも法華経の説く「逆即是順」の妙理の具体的な姿と、その受けとめ方、頂き方が如実に示されていると存じます。
それでなくとも末法のお互い凡夫は、元来が易(やす)きに流れやすく、「善師をば遠離(おんり)し、悪師には親近(しんごん)す」(如説抄第1段)る傾向が顕著です。だからこそお役中は、願わくはこのみ教えを自身に学ばせていただき、さらに一歩を進めて、むしろ敵対する人、逆らう人、また自身にとっての逆境をこそ、いわば善知識として頂戴していただきたいのです。
ただ注意してほしいのは、いわゆる独善に陥らないことです。自身にとっての逆境や敵対・反発のすべてが自身の正しさの証明だとの思い込みは禁物です。やはり一方で謙虚な心を大切にしなければなりません。凡夫が自分の我見(がけん)に基づいて行動すれば、それは当然反発を招きます。もし自身が誤っていて、その為に周囲の反発をひき起こしているのだとしたら、その批判は謙虚に受け止め、自身が改良しなくてはならないのは当然です。にもかかわらず、自身は常に正しく、相手が誤っていると思い込み、その批判が即「善智識」であり、いわば「法難」だから、これに屈せずさらに頑張ろう、などと考え、反省するどころか、一層発奮されたりするのは、これは周囲にとって実に迷惑な話です。
釈尊や日蓮聖人における「善知識」のいただき方は、あくまでも正法たる法華経の教え、妙法の信心に随順しつつ、「自己反省」を忘れないあり方の中でのものだということを忘れてはならないのです。
我見をまじえた勝手で極端な考えを、あたかも絶対の正義のようにふりかざす行為が、ややもすると「原理主義」に同ずる危険性を有することについては、このシリーズの㉛「謗法を戒める―信仰の純正化(3)―原理主義に陥らぬよう―」で記した通りです。
「憶持不忘(おくじふもう)」等については次回で記します。

- ㉞「逆縁正意(ぎゃくえんしょうい)」と「逆即是順(ぎゃくそくぜじゅん)」(2)
- 2015年11月19日(木)
―逆即是順・ご罰即ご利益―
○逆即是順…転換・逆転の妙理
前回は、「縁起(えんぎ)[因縁生起(いんねんしょうき)]」の理法を始点として「順縁」と「逆縁」を説明し、妙法に対して「末法の凡夫はおしなべて逆縁の衆生」ではあるけれども、逆らい誹謗(ひぼう)せしめてでも妙法と縁を結ばしめ、それによって衆生の仏性を啓発・開顕せしめる「逆化折伏」の菩薩行が大切であることや、上行所伝の妙法は、そうした末法の逆縁の衆生をこそ救済し、成仏せしめんがために、み仏が上行菩薩に授けられたものであるから、その意味で、み仏のご本意も御題目自体も逆縁をこそ正意とする(逆縁正意)のであるから、佛立信徒、特にお役中はこの意を体してご奉公させていただくことが大事である旨申しあげました。
なお念のため申し添えさせていただきますと、このシリーズの㉜「自覚の宗教と啓示の宗教」では、仏教は基本的に衆生一人ひとりに、自己に内在する成仏の可能性・素質(仏性)の自覚を促そうとする宗教で、殊に上行所伝の妙法こそが私ども末法のすべての衆生の仏性を開く(開顕・啓発)いわば「マスターキー」であり、開く方法が妙法の受持信唱なのだということを申しあげました。㉝の「逆縁正意(ぎゃくえんしょうい)と逆即是順(ぎゃくそくぜじゅん)」(1)は㉜を受けてのもので、「仏性の自覚を促すマスターキー」とも言うべき「上行所伝の妙法」ではあるけれども、私ども末法の衆生は三毒〈貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)〉が強く、愚かであるため、折角の妙法なのに実際には反発こそすれ、これを素直に受持信唱できない「逆縁」の者ばかりであるため、み仏はそれをも見越されて、逆縁の者をこそ救済すべく上行所伝の妙法をお授けくださったのであり、したがって私どもは、自分自身もそうであるけれども、他の宗外者に対しても、反発を覚悟で、いやむしろこちらから進んで妙法を勧め、折伏し、反発・反抗を激発させることによって逆縁を結び、これを縁としてついにはお教化をさせていただく「逆化折伏」の菩薩行が大切であることを申したわけです。要は、「自覚を促す」といっても、現実には「逆縁」を結ぶことによって仏性が開顕・啓発されていくのだということです。そういう意味で、㉜と㉝は一連の内容となっていますので、その点ご承知おきください。
なお前回「毒鼓(どっく)の縁」に触れましたが、その説明がございませんでしたので捕足しておきます。この「毒鼓の縁」というのは『涅槃経』の如来性品(にょらいしょうぼん)に「譬へば人有りて、雑毒薬(ぞうどくやく)を以て用いて大鼓(だいこ)に塗り、大衆(だいしゅ)の中に於て之を撃(う)ちて声を発(いだ)さしむ。心に聞かんと欲すること無しと雖(いえど)も、之を聞けば皆死するが如し。(乃至)声を聞く者有れば、有らゆる貪欲(とんよく)・瞋恚(しんい)・愚癡(ぐち)、悉(ことごと)く皆滅尽す」とあるのがその典拠です。つまり「毒鼓の音を耳にした者がすべて死するように、正法(妙法)の声(おと)を聞かせることによって本人の意志にかかわらず縁を結ばせ、三毒を滅して成仏へと導こうとする教化法」なのです。ですから「毒鼓の縁」は、「逆縁を結ぶ」「逆化折伏」とほぼ同義の語として用いられるのです。
日蓮大士は次のように仰せです。
「謗法の者に向(むか)っては一向(いっこう)に法華経を説くべし。毒鼓の縁と成さんが為なり。例せば不軽菩薩の如し。(乃至)信謗(しんぼう)共に下種(げしゅ)と為(な)ればなり」
(教機時国抄・昭定242頁)
「当世の人、何となくとも法華経に背(そむ)く失(とが)に依(よ)りて、地獄に堕(お)ちん事疑ひなき故に、とてもかくても法華経を強(し)ひて説き聞かすべし。信ぜん人は仏になるべし。謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり」
(法華初心成仏抄・昭定1426頁)
当世末法の衆生は皆、過去久遠(くおん)以来今日(こんにち)まで妙法を信受したことがなく、このままだと必ず堕獄する「定業(じょうごう)堕獄の凡夫」ばかりなのであるから、とにかく強いてでも妙法を勧め聞かせることが大切である。もしも素直に信受する者は定業を能転(のうてん)して成仏することができるし、反発する逆謗・逆縁の者も、まさしく「毒鼓の縁」となって、ついに成仏へと導くことができるからである。常不軽菩薩の「不軽折伏」のご奉公もこれと同じ心である、との意です。なお、不軽菩薩の姿や「不軽折伏」については、このシリーズの②③、「不軽菩薩の心をいただく」(1)(2)を参照いただきたいと存じます。
さて、今回のテーマである「逆即是順」について申しあげたいと存じます。まずこの語の訓(よ)みは「逆即(すなわ)ち是(こ)れ順なり」で、「逆」は逆縁、「順」は順縁ですから、「逆縁がそのまま順縁である」つまり、「仏法に違逆・反抗することが、そのまま180度転じて、仏法に随順・帰依することになる」という意です。
この語の出典は、天台智顗(ちぎ)の『法華文句(もんぐ)』を扶釈(ふしゃく・解説)した妙楽湛然(みょうらくたんねん)の『法華文句記(もんぐき)』(巻8之4・大正蔵34巻312C)に、「唯(ただ)円教(えんぎょう)の意は逆即是順なり。自余(じよ)の三教(さんぎょう)は逆順定(さだ)まるが故に」とあるのがそれです。これは『法華文句』(巻8下)に、釈尊に敵対し殺害しようとまでした極悪人の代表ともいうべき提婆達多(だいばだった・デーヴァダッタ)が仏から天王如来の授記(じゅき)を得たことについて、「逆(ぎゃく)を行ずるに因(よ)って而(しか)して理順(りじゅん)ずるは即ち円教(えんぎょう)の意にして、余教(よきょう)の意に非(あら)ざるなり」(大正蔵34巻114頁C)とあるのを釈したものです。
「なぜ提婆達多のような仏法違逆の極悪人に成仏の授記があるのかというと、それは法華経が円教(えんぎょう)だからこそ逆即是順の理を認めるからである。法華経以外の余教[蔵教(ぞうきょう)・通教(つうぎょう)・別教(べっきょう)の三教(さんぎょう)]では順逆は固定されたものであって、逆即順などということは到底是認し得る道理ではないのだ」という意味です。
因みに「蔵(ぞう)・通(つう)・別(べつ)・円(えん)の四教(しきょう)」というのは、天台智顗が仏一代の説法を、その説かれた内容によって四種に大別したもので、これを「化法(けほう)の四教」といい、中では円教が最も円満具足・円融の教えであり、特に法華経こそは純円(じゅんえん)であると判定されるものです。「法華純円」「法華円宗(えんじゅう)」(「南無久遠の御文」に「円宗守護」とある円宗もこの意)等の語もあります。なお「化法(けほう)」というのは教化の為に説かれる教法(きょうぼう)の内容そのものをいい、これに対して、具体的な説き方、つまり化導の方法やあり方を「化儀(けぎ)」と申します。
さて話を元に戻します。要は、法華経以外の余経[方便(ほうべん)・権教(ごんきょう)、蔵・通・別の三教を説く経典等]では順縁の成仏は認められていても、逆縁の成仏は認められていない。その逆縁の成仏を「逆即是順」の理によって明らかにするところに法華円教の大きな特徴、余教に優れた有難さがあるということです。なぜなら、私共末法の衆生はすべて三毒強盛(さんどくごうじょう)・罪根甚重(ざいこんじんじゅう)で、提婆に等しい定業堕獄(じょうごうだごく)の逆縁の輩(やから)であり、純円の妙法の受持信唱によって逆即是順させていただく以外には、定業能転し成仏の果報をいただく道はないからです。
日蓮大士は仰せです。
「法華経の心は当位即妙(とういそくみょう)・不改本位(ふかいほんい)と申して、悪業を捨てずして仏道を成(じょう)ずるなり。天台の云く、他教は但(ただ)善に記(き)して悪に記せず。今経(こんきょう・法華経のこと)は皆(みな)記す等云云。妙楽の云く、唯(ただ)円教の意は逆即是順なり。自余(じよ)の三教は逆順定まるが故に等云云」
(波木井三郎殿御返事・昭定749頁)
法華経に示されたみ仏のご本意・お慈悲の有難さは、罪根甚重の極悪人である末法の荒凡夫であり、下根下機(げこんげき)で、余教では度(ど)し難い名字即(みょうじそくい)位の者を、その位のままに逆即是順して成仏せしめようとするところにある、との意です。
「逆即是順」の姿の代表は、先にも記した提婆のいわゆる「悪人成仏」の姿ですが、法華経には、基本的には同じ観点から拝見できる譬喩がいくつもあります。
「長者窮子(ぐうじ)の譬(たとえ)」(信解品第四)、「良医病子(ろういびょうし)の譬」(如来寿量品第十六)もそうです。
○「長者窮子(ちょうじゃぐうじ)の譬」と「良医病子(ろういびょうし)の譬」
・「長者窮子の譬」
信解品(しんげほん)は、その前の譬喩品(ひゆほん)第三の教説を受け、舎利弗(しゃりほつ)が授記(じゅき)を受けたことに随喜した迦葉(かしょう)・目連(もくれん)等の四大声聞(しょうもん)が、自身は小乗の教えをもうこれで最高だと思って満足し、菩薩の大乗の法を求めようとする志願も持たないでいたところへ、希有(けう)の大法を与えられたことを随喜し、その喜びを譬をもって述べる章で、有名な「無量珍宝不求自得(むりょうちんぽうふぐじとく)」[無量の珍宝、求めざるに自(おのずか)ら得たり]、「無上宝聚不求自得(むじょうほうじゅふぐじとく)」[無上の宝聚、求めざるに自ら得たり]の御文もこの品が出所です。なお当品の「無貪無著無復志願(むとんむじゃくむぶしがん)」[貪(とん)なく著(じゃく)なく復志願(またしがん)なし]の文は、開導聖人の師である無著日耀(にちよう)上人と、開導聖人の無貪清風のお二人の号の依文(えもん)だと拝されます。
さて「長者窮子の譬」の概要は次のようなものです。長者は仏、窮子は声聞等の小乗教徒をさします。
「金持の長者に一人息子がいたが、何の理由、何の不足があってか、幼くして親の家を出、困窮のはてに浮浪の乞食となって長年流浪する。父は子をさがし求めていたが、ある町に止(とど)まって大富豪となっていた。その大邸宅を通りかかった息子は父を識別することもできなかったが、父は一目で息子をそれと見、自邸に雇って便所掃除から始めさせる。長者は自身も便衣に身をやつし、息子に近付いては次第に啓発し、終(つい)には自覚を呼び覚(さま)して父子の関係を明かし、全ての財産を譲り与える」
ここで私が特に注意したいと思うのは次の御文です。
「譬へば童子、幼稚無識(ようちむしき)にして父を捨てゝ逃逝(じょうぜい)して遠く佗土(たど)に到りぬ」(開結191頁)
これは譬喩の冒頭で、ここから話が始まるのですが、ご覧のようになぜ恵まれた家と父を捨て、家出をすることになったのか、その理由の説明は極めて簡略で、ただ「幼稚無識 (ようちむしき)捨父逃逝(しゃぶじょうぜい)」とあるだけです。
思うに、折角自分に与えられている結構な境遇でも、本人は果報拙(つたなく)くしてそれと有難く受け止めることができず、却(かえ)って反発し遠離(おんり)しようとするということでしょうか。「幼稚無識」とはそういうことでしょう。それは「我見(がけん)」ばかり強く頑固で、世間のことも、父の心も、何も分っていないくせに、つまらぬ意地ばかり強情に張り、自分から幸せに背を向けてしまう「愚かさ」であり、「幼稚さ」だと存じます。自分でも自分のことがよく分っていない。それも含んでの「無識」なのでしょう。
折角の身に余る大法を与えられながら、果報拙くして拙劣な小乗の教えに執着し、御題目というこの上ない大法(無上の宝)に理由もなく反発し罪障を累(かさ)ねて末法まで生死流転を繰り返してきて、今やっと改めて妙法にお出値(であ)いすることができた私共も、いわばこの「幼稚無識」に他ならないと申せましょう。
さらに卑近な例を申せば、傍らから見ればそれなりに恵まれた家に居りながら、なぜか親や家族に不満を持ち、反発して家を出た息子や娘が、外へ出てはじめて家や親の有難さが身にしみ、それがきっかけで、家族関係が修復されるのも同じ理(ことわり)ではないかと存じます。
一度は違逆・反発しながら、その逆縁がきっかけとなり、それが転じてついには順縁となる「逆即是順」の姿はこういうところにも感得できるのではないでしょうか。そういえば、以前はけんかばかりしていた夫婦や友人同士が、後に却ってこの上ない固い絆で結ばれたり、幼い時は意地悪ばかりし合っていた男女が長じて結婚したり、悪人が自身の悪業を縁として改心するや、一転して普通以上の善人に生れ変わったり、ということも世間には少なくありません。こうしてみると「逆即是順」というのは本当に奥深い、法華経ならではの妙理だというのも、何となくうなずけるような気がいたします。
「良医病子の譬」についてはこのシリーズの㉓「妙法こそ大良薬(だいろうやく)」の中で既に概説もしてありますので、譬喩の概略はそれを参照いただきたいと存じます。ただここで注意しておいていただきたいのは、まずこの譬の中でも、父である良医の留守に子が毒薬を飲んだ理由は全く示されていないこと、また帰宅した良医が最高の毒消しの良薬(妙法のこと)を与えて飲むように勧めるのに、反発してどうしても飲まない点です。経文には次のようにあります。
「余の心を失へる者[余失心者(しっしんじゃ)]は(乃至)而(しか)も肯(あえ)て服(ふく)せず。所以(ゆえ)は何(いか)ん。毒気深く入って[毒気深入(どっけじんにゅう)]本心を失へるが故に此の好(よ)き色(いろ)ある薬に於いて美(よ)からずと謂(おも)へり。(乃至)毒に中(やぶ)られて心皆顛倒(こころみなてんどう・しんかいてんどう)せり」(開結424頁)。
大良薬(妙法)を飲まない(信唱しない)のは、重度の中毒(三毒強盛・毒気深入)のため錯乱状態で正しい判断や行動ができず、良薬を素直に認識できないで疑ったり反発したりしている、いわば逆さまにしか見ることができない愚かさ(心皆顛倒)の中にあるからです。けれども、そんな彼らも良医である父が旅先で死んだ〈実には非滅現滅(ひめつげんめつ)の入滅―仮りの入滅〉と知らされるや、深い悲しみの中ではじめて父の真の慈愛の心に思い到り、やっと素直な心になって〈常懐悲感(じょうえひかん) 心遂醒悟(しんすいしょうご)〉良薬を服(の)み、さしもの苦しみからも救われる〈即取服之(そくしゅぶくし) 毒病皆愈(どくびょうかいゆ)〉のです。
父が名医でありながらその子が毒を服んだのも愚かなことなら、名医たる父の最高の処方の良薬に文句をつけて逆らい、素直に服まないのも実に愚かなことです。でも逆縁とはそういうものなのでしょう。しかし、そうした反抗・違逆が縁となって、却って父の深い慈悲心を知ることとなり、一転して父の教えに随順し、良薬を服んで苦悩から救われるのですから、これも「逆即是順」の姿でしょう。三毒強盛・定業堕獄の末法の凡夫が、妙法に反発しながら、しかもついには妙法を信唱することによって成仏の果報をいただくのも同じです。それは、良医たる父をみ仏に、毒気深入の失心者で心皆顛倒の子を末法の荒凡夫たる私共に、それぞれ置きかえてみれば何となく腑(ふ)におちることではないでしょうか。
○逆転の発想―「ご罰即ご利益」
「逆即是順」を少々荒っぽく換言すれば「逆転の発想」・「転換の妙理」だとも申せるのではないかと存じます。普通なら「もうダメ」と定まった事が、それ自体を機縁とし、一転して素晴らしい方向に進む転換点となるのですから。例えば信者とは名ばかりで信行に背を向けていた人が、医者にもサジを投げられるような重病を患い、もうダメだという時になってはじめて必死に御題目にすがり、それで奇跡的に助かって、これが機縁で本物の信心をつかみ、それからは別人のような強信者になるというようなこともありますね。また、もし仮りに助からなかったとしても、本当の信心を決定(けつじょう)することができて、見事な臨終の姿をあらわすということもあるでしょう。
開導聖人は御教歌に仰せです。
○逆縁は御罰(ごばち)あたりて信心の
おこるところを御利益といふ
「逆即是順」の妙理は「ご罰即ご利益」ということにも通底します。
逆縁の凡夫が妙法に反抗し、結果御宝前からのお折伏たるご罰をいただいた。それで終ってしまえばご罰も単なるご罰で終わってしまう(いや、そのままだと更に悪い方向に進む)けれど、ご罰によって本人が自らの誤りに気付き、懺悔(さんげ)・改良して本当の信心を起こすことができれば、そのご罰は単なるご罰ではなく、そのままご利益に転じるわけです。これは、世法の上でもよく分ることです。例えば何か失敗をしたときのことを考えてください。学生が模擬試験で失敗した。それは失敗には違いないけれど、その失敗をただ悔やんでいるのではなく、失敗によって自分の弱点に気付き、反省して努力精進した結果、大事な本番では成功した、となれば先の失敗がそのまま成功の基(もとい)だったことになります。
なお付言すれば、「罰」というのは決してみ仏が私共を憎いと思って当てられるものではありません。「罰が当たる」、「罰を当てられた」などと申しはいたしますが、実のところ凡夫がみ教えに背き、勝手に誤った道を進むから、自身で苦境に陥(おちい)るのです。
御教歌にも仰せです。
○うかうかとする故どぶへはまる也
罰は仏がおあてなさらぬ
さらに次のような御教歌もございます。
題・折伏は御慈悲の最極(さいごく)
○罰といふ御(おん)折伏のなかりせば
われらに信は起(おこ)らざらまし
(十巻抄第三・如説抄拝見 完・扇全14巻416頁)
同じ「ご罰」でも受け止め方で実に180度違ってきます。叱られたり、注意されたりするのは誰しも歓迎し難いものですが、よくないことをしている、誤った道を進んでいるのに、注意も忠告もしてもらえないよりは、忠告してもらった方が有難いはずです。
「ご罰」はいわばみ仏・御宝前からの有難い忠告・折伏なのです。「ご罰」は「折伏」であり、「折伏は慈悲の最極」だと受けとめさせていただくことができれば、「ご罰即ご利益」となるのです。
世法の商業活動などでもこれは申せます。例えば、従来は単なる産業廃棄物として捨てられ、そのことが企業の不利益となり重荷になっていた物が、視点を変えて見ると、同じ物が大いに価値のある物として生まれかわり、利潤をも生み出すことができるというようなことはいくらでもあります。卑近な物では生ゴミもそうです。生ゴミを生ゴミとしてしか見なければ、回収、焼却、二酸化炭素やダイオキシンの発生など全てがマイナスへばかり向うのですが、これを微生物等で処理すれば却って価値のある有機肥料になって、すべてがプラスに転じますね。ゴミが有用な資源になるのですから。
法華経の「逆即是順」の妙理は、「ご罰即ご利益」はもとより、総じてダメだと棄(す)てられ、否定され、マイナス評価しか与えられなかったものを、活かし、肯定し、さらにはプラスの評価へと逆転せしめる、いわば「発想の転換」・「逆転の発想」を促すものなのです。
「妙とは蘇生(そせい)の義なり」(法華題目抄・昭定402頁)とは、実に言い得て妙だと存じます。

- ㉝「逆縁正意(ぎゃくえんしょうい)」と「逆即是順(ぎゃくそくぜじゅん)」(1)
- 2015年10月20日(火)
―「そしるにさへや香(か)にうつるらん」―
○「逆縁」と「順縁」
前回は「自覚の宗教と啓示の宗教」―仏性の開顕…妙法こそ「マスターキー」―のテーマで、仏教は「自覚の宗教」であり、特に法華経は、閉ざされているすべての凡夫(ぼんぶ)の心を開き、眠っていた仏性(成仏の素質)を覚醒せしめ、凡夫にその自覚を促そうとするみ仏のご本意が示されたものであり、上行所伝の御題目こそが末法のすべての凡夫の心の中の仏性を開顕せしめるいわば「マスターキー」であること、その開く方法は妙法への帰依であり、妙法の受持(じゅじ)信唱であることを法華経の御文や、日蓮大士(だいじ)の御妙判に基づきつつ、また染織家・志村ふくみさんの媒染(ばいせん)に関する文章なども援用させていただきながら説明申しあげました。そして次のように記しました。
「同じく媒染を受け、あるいは帰依(きえ)するなら、私たちにとって最高のものをいただかねばなりません。それが末法の凡夫にとっては上行所伝の御題目なのです。
信仰の本質はまさしく帰依・帰命(きみょう)することに他なりません。最高の御本尊・み仏のたましいたる御題目に帰依し、すべてを捧げることです。〈中略〉
妙法に帰依し、受持信唱させていただくのは、一見すると自分の外の存在に向かっているようですが、実はそうではないのです。外なる妙法(御本尊)に帰依し口唱することが、実はそのまま自分の内なる妙法(仏性)を呼び顕わす(開き、啓発する)ことに他ならないのです。〈中略〉最高の御本尊(妙法)に帰依し妙法を口唱することによって、実はお互いの内に秘めた最高の素質(妙法・仏性)を開き、啓発させていただくのですから」
「帰依」ということが、自己の「外なるもの」に向かうものでありながら、実は自己の「内なるもの」を啓発するものだということは、日蓮大士が『法華初心成仏抄』の中に譬(たとえ)として挙げられた「籠(かご)の内と外とで鳥が鳴き交わす」例でもよくわかるのですが、これはもっと一般的にも申せることです。
どういうことかと申しますと、例えば名画や名曲などの芸術作品や自然の草花の風情に触れて心を打たれ、深く感動したとします。もちろん他の人物でもかまいません。いずれも「自己の外なるもの」、「外界の対象」によって、「自己の内なるもの」が感応したわけですね。ではこの感応する「内なるもの」はどこから来たのでしょう。外から、相手から与えられたのでしょうか。そうではないはずです。
それは媒染も同様です。煮汁等で染めた糸や布の色が媒染で発色し、別の色が現れるのだって、元の布や糸に媒染に反応し、触発されるものが何もなければ、いくら媒染しても新たな色が発色することはないのですから。
外界の存在が私たちの感覚器官を通して認識されるには違いないのですが、でもそれだけで感動するものではありません。すべてに同じように感動するわけではないのですから。
何かに特に心をゆさぶられ、深く感動するというのは、よく考えてみれば、例えば「ああ、何て美しい!」「何て素晴らしい!」と感応し、触発され、感じ取るものが私たちの側にもなければならないはずです。ある日何かを見たとき、思いがけず突然心が奪われるような、心がふるえるような感動をした、というとき、それは自分でも意識していなかった内なる何かが、外からの刺激や働きかけに触発され、感応して引き出されたのです。仏教で「感応道交(かんのうどうきょう)」と申しますが、その基本的なあり方は同じだと存じます。み仏のたましいと凡夫の仏性とが感応するわけです。
もともと私たちの心に何もなければ、外界の美に感応することもないはずです。世間でも「どうせ何かを見るなら、本物の最高の物を見なさい」というのも当然だと存じます。私たち凡夫の心には「十界」というように、地獄の心から仏の心まであるのですから、変なもの、劣悪なものに触れ、うっかりそれらと感応して触発されれば、当然内なる劣悪なものが開かれ、引き出されてしまうのですから。前回の「鳥が内外で鳴き交わす」譬えの解説の際、「メジロにはメジロ、ウグイスにはウグイスが」と私の経験もまじえて記した理由はここにあります。
久遠のみ仏のたましいである最高の御本尊(妙法)に帰依してこそ、私たち凡夫の心のうちにある最高の仏性(妙法)が感応し、触発し、啓発されるのです。それが誤って間違ったものに帰依したらどうなるのでしょう。悪人を崇拝すればその当人も悪人になる道理です。「帰依の対象は最高のものでなければならない」というのはそういうことです。同じく帰依をするのなら、自分を最も高めてくれるものに帰依したいものです。
さて今回は「逆縁正意と逆即是順」というテーマです。
仏法は「縁起(えんぎ)[因縁生起(いんねんしょうき)]の法」だとも申します。すべての存在も現象もこの縁起の理法に貫かれているわけです。この「縁」を仏法に対するあり方でいえば「順逆二縁(じゅんぎゃくにえん)」があります。宇井『仏教辞典』でみると、まず「順縁」とは「よきできごとが仏道に入る因縁となること」とあり、「逆縁」とは「仏に抗し、法を謗(そし)る等の違逆(いぎゃく)の事が、却(かえ)って仏・菩薩の化益(けやく)を受け、道に入る因縁となること」と記されています。これは順逆の「縁」それ自体を説明したものですが、当宗では「縁」それ自体を指す場合と、「そういう縁を有する人」を指す場合との両方の意で用います。したがって、御題目との関係で「順縁」といえば「最初から素直に御題目を信じ、随順して入信できるご縁。そうしたご縁を有する人」を指し、「逆縁」は「なぜか御題目に反抗・敵対し、妙法を謗る縁。しかしその縁がもととなって却って入信するご縁。またそういうご縁の人」ということになります。そして末法現代に生まれてくる私共は原則としてすべてが妙法に対して「逆縁」の凡夫だとされるのです。
○末法は「逆縁正意」
―妙法は逆縁救済の法
なぜ末法の衆生は「逆縁」なのかと申しますと、み仏の教えによれば、末法に生まれ合わせてくる衆生は皆、み仏のご在世はもとより、過去久遠以来(無始已来)無数の生死を繰り返す間、一度も妙法を信じ唱えたことのない[これを「本未有善(ほんみうぜん)」―本(もと)未(いま)だ善(ぜん)有(あ)らず―と申します]衆生ばかりだからだとされます。私たちが常に「無始已来謗法罪障消滅」と、今日までの妙法逆謗の罪を懺悔(さんげ)言上申しあげるのは、このことを踏まえているわけです。このことを頭で理解するのは困難なことですが、現実に私たちは仮りに信者であっても、やはり我[我執(がしゅう)]が強く、貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)・愚癡(痴・ぐち)の三毒(さんどく)が強盛(ごうじょう)で、そのため互いに争い、苦しんでいます。そのことを思っただけでも「逆縁」「違逆」の衆生であり凡夫であるということはわかるはずです。三毒は「貪(むさぼ)り」「いかり」「愚か」ということですが、その根本には深い愚かさがあります。
念のため申しておきますが、仏教でいう「愚癡」というのは世間でいう「グチ」とは大分意味が違います。「愚癡」とは「み仏の説く因果の道理に従った判断と行動ができないこと」です。「因果の道理」とは「こうすればこうなる」という因果関係ですが、み仏の教えは過去・現在・未来の三世に通達(つうだつ)し、これを見そなわされての因果の道理で、単に目前のものではありません。実にすべてを踏まえての道理であって、目先の欲に目がくもった凡夫の判断や見方とは異なります。それだけに、凡夫はみ仏の教えを素直に頂戴できにくいということもあります。こうした因果の道理が「理解できない」、あるいは「理解できたとしてもその教えに従った行動ができない」で、結果苦しむことになる。これが「愚癡」ということです。
けれどもこのように我執が強く、愚かな末法の私共「逆縁の衆生」をこそ救おうとされるのがみ仏の慈悲であり、そのために法華経を説かれ、その本門八品で御題目を示され、「末法の衆生を救済せよ」と上行菩薩にその御題目をお授けになられたのです。そういう意味で上行所伝の妙法は、特に「逆縁」の衆生を救済することをこそ本意・目的としているのであって、これを「逆縁正意(ぎゃくえんしょうい)」と申します。
この「逆縁正意」に関してもう少し説明しますと、まず第一に、「末法の衆生はおしなべて逆縁の衆生」なのですから、宗外者はもとより信者たる自分も基本的にそうなのだということを自覚しなければなりません。
第二に、宗外者はもとより、他のご信者も、妙法に反抗し、素直に従わないのも当然だと覚悟して、そうした逆縁・逆謗の縁によって却って妙法とのご縁を結び、深めることによって正信に導かれるのだと受けとめ、そのご縁を大切にすることが大事だということにもなります。
第三に、これを一歩進めると、仏祖のご本意を体認すれば、むしろこちらから他の人に御題目をお勧めする。そうすれば当然相手は反発するけれども、そのようにして逆縁を喚起・激発せしめる[これを「毒鼓(どっく)の縁」とも申します]ことにより、それを縁として教化に導くという姿勢になります。菩薩・如来使としての「逆化(ぎゃっけ)」(違逆・敵対せしめることを通じての教化の意。仏・菩薩が衆生を教化するに、却って誹謗し敵対せしめて化益を成ずるをいう「宇井・仏教辞典」)折伏のご奉公です。
開導聖人は仰せです。
御教歌 題・逆縁正意
①さかさまに結ぶゑにしも法(のり)の花
そしるにさへや香(か)にうつるらん
(三界遊戯抄一・扇全6巻346頁)
②さかさまに結ぶ縁(えに)しも道たえぬ
せむるこゝろのおとろへしより
(信心に活[かつ]を入れるの事・扇全18巻355頁)
③折伏の慈悲のめぐみをさかさまに
いかりにくむも縁(えに)し也けり
(開化要談(教)・扇全14巻32頁)
御指南
「謗法人を見るたびに、顔にむかい一辺なりとも、御題目を唱へて御縁をむすばせてやりたき事、これ大慈大悲なり」
(釈迦御一代記実録・扇全2巻313頁)
「さかさまに結ぶ縁[えにし]」とはまさしく「逆縁」のことであり、「法の花」は「妙法・御題目」のこと、「そしる」は「誹謗(ひぼう)」のことです。妙法を謗る逆縁もその縁に結ばれることによって妙法の感化を受けるのだから、逆縁正意、逆化折伏のご奉公を大切にせよ、というのが①の御教歌で、そうした逆縁を結ぶご奉公ができなくなったというのは、慈悲の折伏の思いが衰えたからだ、そんなことでどうするのだ、と活を入れられたのが②の御教歌です。
御指南の方は、宗外の謗法の人(当然逆縁の人)に対しては、顔を見る度ごとに、せめて一辺でも御題目をお唱えして耳に聞かせてやりなさい。御題目の音声(おんじょう)自体[法体(ほったい)]に逆化折伏の経力があり(これを「法体(ほったい)の折伏」という)、逆縁を結ぶことができるのだから、との意です。
○蓮の花の香りが移る
―ベトナム王宮秘伝「ハスの花茶」
「香りが移る」「色が移る」ということは諺(ことわざ)その他でもよく言われますし、私どもの日常生活の中でも折にふれて経験することですが、先日偶々(たまたま)テレビを見ていて「ハスの花茶」なるものがあることを初めて知りました。
それは8月1日夜10時から放映された「世界ウルルン滞在記」(毎日テレビ)。以前、NHKの「朝の連続テレビ小説」『こころ』のヒロイン役をつとめた女優・中越典子さんが、ベトナムに滞在し、ベトナム王宮に秘伝として伝わっていた「ハスの花茶」を伝承者の婦人に学び、一緒に作る一部始終でした。
西湖という古く大きな湖があり、そこには昔から香りのいいハスの花(蓮華)が季節になると沢山咲くのです。「ハスの花茶」というのは、このハスの花の優雅な香りを移したお茶のことです。作り方は、まず早朝、小さな舟を出してハスの中をこぎ回り、咲く直前のつぼみを約1000個ほど集めます。その花のオシベが香りのもとなので、ハチの巣のようなメシベの周囲にあるオシベの先端部分[葯(やく)]だけを集めます。1000個の花からでもほんの少量しか集まらないのですが、それを器の中で1.5キロのお茶と交互に重ねて1日置き、翌日フルイにかけてオシベだけ取り除き、そのお茶を匂いだけは残して茶葉は乾燥させる特別な方法で1日置きます。同じことを続けて3回行いますから、最低でも六日間かけて香りをお茶に移すのです。出来上がったお茶の外見は普通の茶葉と全く変わらないのですが、このハス茶にお湯を注ぐと、その時えもいわれぬハスの花の上品で優雅な香りが馥郁(ふくいく)として立ち昇るのです。大変な手間をかけ、6日間でやっと1.5キロの品しかできず、しかも季節も限られているのですから、これは実に貴重なものだと存じます。一度でいいから飲んでみたいと存じます。
それはともかく、御題目(妙法)の香りもいわば蓮華の香り、最高の香りで、これは私たち凡夫の心に移るのです。そして移そうと思えば、毎日でも、いつでも、何度でも移せるのです。開導聖人は先の御指南で「一辺なりとも」と仰せでしたが、繰り返せば繰り返すほど濃く、深い香りが移り、染まっていくのだと存じます。しかも、単なる茶葉と違って、私たち凡夫の心にはそれ自体にまだ開いていない蓮華(妙法・仏性)があって、外からの触発・媒染を待っているのです。蓮華で蓮華を開くのですから、これ以上の香りはないでしょう。たとえ最初は反発したとしても、ついにはそのように香り立ちたいものだと存じます。
「逆即是順」については次回で記します。

- ㉜「自覚の宗教」と「啓示の宗教」
- 2015年8月6日(木)
―仏性の開顕…妙法こそ「マスターキー」―
○「自覚の宗教」と「啓示の宗教」
前回まで3回にわたって「謗法を戒める…信仰の純正化」のテーマで記しました。
その(1)では「根本謗法」である「妙法不信」の意味内容について説明し、その(2)では「謗法の態様」についての略説を、そして(3)では「謗法を戒め信仰の純正化の努力をする」ことが誤って「原理主義」に陥らないよう、いわゆる「原理主義」との対比をまじえつつ説明いたしました。
ただ、全体を通じて、具体的な謗法の個別的な説明にはあまり触れませんでした。
その点はややご不満かと存じますが、個々の具体例となるとそれこそ無数にありますし、その程度等の問題もありますから、事例によってはいわば臨界線上のものもあろうかと存じ、これは具体的な状況に応じて、現場の御導師やお教務方にご相談いただき、そのご判断に従っていただいた方がいいのではないかと考えたのが、具体例にあまり触れなかった一番の理由です。
中でも最も問題になり易いと思われるのは「習俗」「風習」との関係です。
例えば「クリスマスツリー」や七夕の「笹飾り」、正月の「しめなわ」「門松」、節句の「ひな飾り」等は事相上でも問題となります。いずれも一般世間ではほぼ「習俗」化しており、特に「宗教」的なものとしては考えていないとも申せますが、厳密に申せばやはり、宗教的な意味を有しています。
「門松」は神道の神の「よりしろ」ですし、「しめなわ」「しめ飾り」もやはり神道のものです。クリスマスはもちろんキリスト教のものですし、「ひな流し」となればこれも「穢(けが)れを祓(はら)う」意味を持ちます。しかし、幼稚園でクリスマスツリーや笹飾りを作ったからといって目くじらを立てるのもどうかと思われますし、「ひな飾り」も「女の子の遊び」だと把(とら)えればムキになる程のことではないでしょう。
けれども、門松やしめ飾りは、当宗の寺院はもとよりのこと、ご信者宅でもまず用いないはずですし、お寺でクリスマスツリーを飾ったり、クリスマスパーティーを開くことは決してありません。「ひな飾り」等でも、ご信者宅の御宝前のすぐ横に御宝前よりも立派で大きな飾り段を設けるのはどうかと思います。その他節分の行事の「豆まき」や大阪の風習の、一定の方角(恵方)を向いての「巻寿司の丸かぶり」、各地の祭礼、地蔵盆等もちろん問題になります。また観光や修学旅行等で神社仏閣へ立ち入ることについても幾分問題があります。
開導聖人は、門祖日隆聖人の御修行参詣が25日の北野神社の縁日詣でと紛れぬよう、24日に御修行をお勤めになられましたし、かつては当宗のご信者は鳥居をくぐるのも忌避した程です。ただ、あくまでも私見ですが、修学旅行や観光で、他宗堂社を見るのは「文化財や美術品の見学」という観点からなら大目に見てもいいのではないかと思っています。もちろん、賽銭(さいせん)を投げたり、拝んだり、札守(ふだまも)りの類いを土産に買ったりするのは論外です。その他「相似の謗法」に類する具体例は多々あろうかと存じますし、世間的あるいは商売上のつきあい等でもいろいろな事例があろうかと存じます。各種の占いも謗法です。気になる点は所属の寺院の御導師やお教務にご相談いただくのが一番だと存じます。
さて今回のテーマは「自覚の宗教」と「啓示の宗教」です。
実は「宗教」の定義は大変難しく、「宗教学者の数だけある」ともいわれます。世界には、それほど多種多様な宗教が存在しているわけです。けれども大きく類別すると「創唱宗教」と「自然宗教」、「自覚の宗教」と「啓示の宗教」という区分はできるとされます。「創唱宗教」「自然宗教」というのは、その宗教の起源、発生に関する類別で、「創唱宗教」というのは、その宗教に創唱者が存在しているのに対して、「自然宗教」はそうした特定の創唱者や創始者となる教祖がなく、いわば自然発生的に成立した宗教のことです。
例えば仏教には釈尊、キリスト教にはイエス、イスラム教にはマホメット(ムハンマド)という創始者・創唱者がいますから「創唱宗教」だとされ、ヒンドゥー教や日本の神社神道(しんとう)などには特定の創始者はなく、いわば自然発生的に成立しているので「自然宗教」だとされます。アニミズムも自然宗教の典型です。
神道でも、天理教、金光教、黒住教、大本教等の教派神道は教祖・開祖がいますし、日本の仏教の各宗派も開祖が存在しますから「創唱宗教」だということになります。
また別の区分では、「一神教」(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教等)と「多神教」(ヒンドゥー教、神社神道等)という類別の仕方もあります。しかしいずれにせよ、これも極めて大雑把な区分ではあります。
これらの類別に対して「自覚の宗教」と「啓示の宗教」というのは概略次のような区分です。
「啓示の宗教」というのは、例えば、ユダヤ教はエホバ(ヤハウエ)の神の啓示を受けたモーゼがその啓示の内容(これを神の「預言(よげん)」・「預託(よたく)」といいます)を基として人びとに伝えた宗教ですし、キリスト教はイエスがゴッドから示された啓示のことば(預言)によって伝道したものであり、イスラム教はアッラーの神の啓示を受けたマホメットが、その啓示を記したとされる聖典『コーラン』によって布教したものです。モーゼにせよ、イエスにせよ、マホメットにせよ、いずれも神の託宣を聞いてそれを伝えたのであって、その内容は自分の外から与えられたものです。自身の内なる声でもなければ、自身が悟ったものでもありません。そういう意味で「啓示の宗教」というのです。『新・旧約聖書』や『コーラン』のような『啓典』を聖典とするため、「啓典の宗教」ともいい、またこうした宗教を信ずる人びと、民族を「啓典の民(たみ)」とも申します。
オクスフォード大学教授で、東洋の宗教・倫理学の権威であるR・C・ツェーナーによれば、これらセム族の一神教に共通するのは、「神によって与えられたと信じる啓示に服従し、その啓示の内容に従って神を崇拝する」という思想だとされます(森本達雄著・中公新書『ヒンドゥー教』30頁)。
これに対して仏教は「自覚の宗教」です。釈迦族の王子ゴータマ・シッダールタは、神の声を聞いて啓示(預言)を受けたわけではなく、自らがこの宇宙の理法(ダルマ)を悟り、自覚し、その理法を説いたのであって、法を悟って仏(ブッダ・釈迦牟尼仏・釈尊)となったからです。その意味で、仏教は「仏の教え」であると同時に「仏になる(成仏の)教え」でもあるわけです。
これは先のユダヤ教、キリスト教、イスラム教の各宗教の唯一絶対神(エボバ、ゴッド、アッラー)が人間とは隔絶した存在であり、人間は決して神になれず、神との契約を守ることによって恩恵を受け、神の国に召されるのとは基本的に異なります。仏教(特に大乗仏教なかんずく法華経)では、人間も仏になることが可能なのです。
○“開く”ということ
―「四仏知見(しぶっちけん)」と不軽菩薩の礼拝行―
このように、仏教は元来が「自覚を促す」宗教です。これを法華経によって拝見しますと、まず方便品(ほうべんぽん)第2には次のようにあります。
「諸仏世尊は唯一大事(ただいちだいじ)の因縁(いんねん)を以ての故に世に出現したまふ。[乃至]諸仏世尊は、衆生をして仏知見を開かしめ清浄(しょうじょう)なることを得せしめんと欲するが故に、世に出現したまふ。衆生に仏知見を示さんと欲するが故に[乃至]。衆生をして仏知見を悟らしめんと欲するが故に[乃至]。衆生をして仏知見の道に入らしめんと欲するが故に、世に出現したまふ」
(開結100頁~101頁)
これは、仏がこの世に出でたもう目的は一切衆生をして仏自身と同じく「仏知見」を「開・示・悟・入(かい・じ・ご・にゅう)」せしめんがためであることを明らかに示される御文で、これを「開示悟入の四仏知見」と申します。
この「四仏知見」の第一、最初が「開仏知見」―つまり「衆生をして仏の知見を開かしめる」ことなのです。
次に常不軽菩薩品(じょうふきょうぼさっぽん)第20には次のごとくあります。
「是(こ)の比丘(びく)凡(およ)そ見る所ある比丘・比丘尼(びくに)[乃至]を皆悉(みなことごと)く礼拝讃歎(らいはいさんだん)して是(こ)の言(げん)を作(な)さく。
我(われ)深く汝等(なんだち)を敬ふ、敢(あえ)て軽慢(きょうまん)せず。所以(ゆえ)は何(いか)ん。汝等(なんだち)皆(みな)菩薩の道(どう)を行じて、当(まさ)に作仏(さぶつ)することを得べしと」
(開結488頁)
この不軽菩薩の礼拝行については、この「入門シリーズ」の②③(平成14年2・3月号)で「不軽菩薩の心をいただく」(1)(2)としてやや詳しく記させていただいておりますので、参考にしていただけたらと存じます。
「我深敬汝等(がじんきょうにょとう)」以下の御文は漢字で24文字ですが、その心は御題目の心と同じだと日蓮聖人も『顕仏未来記』に仰せです。
御文の心は「あなたは菩薩行をすれば必ず仏と成る素質(仏性)を秘めておられるのですから、どうかご自身でそのことに気がついてください」と、行き会うすべての人びと(所見〈しょけん〉の人〈にん〉)を仏として礼拝し「仏性(ぶっしょう)の自覚」を促されたものに他なりません。しかも、み仏は同じ不軽品の中で仰せです。
「爾(そ)の時の常不軽菩薩は豈(あ)に異人(ことひと)ならんや。則(すなわ)ち我が身是(こ)れなり」
(開結492頁)
つまり、この不軽菩薩は他でもない釈尊自身の前世の姿なのだと仰っているのです。
この不軽の24字にせよ御題目にせよ、お唱えすることによって、閉ざされ、眠っていた凡夫の心を開き、仏性に目覚めさせるものだということを知らねばならないのです。
○「妙」とは「開」―妙法こそマスターキー
日蓮聖人は仰せです。
「妙とは法華経に云く、方便(ほうべん)の門を開(ひらい)て真実の相(そう)を示す云云。(乃至)妙と申す事は開(かい)と云事(いうこと)也。世間に財(たから)を積める蔵(くら)に鑰(かぎ)なければ開く事かたし。開(ひらか)ざれば蔵の内の財を見ず」
(法華題目抄・昭定396頁)
「我(われ)日本の眼目とならむ」
(開目抄・下・昭定601頁)
「日蓮が慈悲嚝大(こうだい)ならば南無妙法蓮華経は万年の外(と)未来までもながる(流布)べし。日本国の一切衆生の盲目を開ける功徳あり」
(報恩抄・昭定1284頁)
「開発(かいほつ)」という語も元来は「人間の内に眠っている最も尊い素質(仏性)がみ仏の慈悲によって目覚め、ぱっと開かれ発動・発展する」という意味です。
妙法の本質は「開」であり、上行所伝の御題目こそが、末法のすべての衆生の心の中に閉ざされている仏性を開顕するいわば「マスターキー」なのです。
○妙法への帰依(きえ)による仏性の開顕・啓発を
染織家の志村ふくみさんに次のような文章があります。
「親のもとで成長した息子や娘が年頃になって結婚し、就職し、環境によってそれぞれの色彩に変わってゆく。もちろん人間の場合はそれほど単純ではないが、それもある種の媒染(ばいせん)である。自分の持っている素質と遭遇(そうぐう)した事実との関わり合いでどんな色彩に変わってゆくか。(中略)でき得るならば、人間の場合も、自分にもっとも適した媒染を受けて、その素質を伸ばしてゆきたいものである。
植物の場合、もっとも自然な美しい色彩を得るには梅には梅の灰汁(あく)、桜には桜の灰汁で媒染するのがよい。みずからの灰で、みずからを発色させる。人間の場合はどうなるのか。自分で自分を媒染する。さらには自分を何ものかに捧(ささ)げ、あるいは帰依(きえ)するとき、最高の色を発色するのではあるまいか」
(岩波カラーグラフィックス『色と糸と織と』より)
媒染とは、糸を草木を煮出すなどして染めた色を灰汁や石灰や鉄などの媒染剤をくぐらせることによって、元の色とは違った色を発色させ定着させる染織技術です。
それが桜の木で桜色を発色させるには、同じ桜の木の灰汁が一番自然な美しい色を発色させるのです。
人間の場合は「自分で自分を媒染する。さらには自分を何ものかに捧げ、あるいは帰依するとき、最高の色を発色するのではあるまいか」と言っているのです。これは志村さんという一流の染織家が、自身の仕事を通じて感得した卓見だと存じます。
ここで日蓮聖人の御妙判をいただきます。
「凡(およそ)妙法蓮華経とは我等衆生の仏性と(乃至)三世の諸仏の解(さとり)の妙法と一体不ニ(いったいふに)なる理(ことわり)を妙法蓮華経と名づけたる也。故に一度(ひとたび)妙法蓮華経と唱ふれば一切の仏(乃至)一切衆生の心中の仏性を唯一音(ただひとこえ)に喚(よ)び顕(あらわ)し奉る功徳無量辺也。我が己心(こしん)の妙法蓮華経を本尊とあがめ奉りて、我が己心中の仏性南無妙法蓮華経とよびよばれて顕れ給ふ処(ところ)を仏とは云ふ也。譬(たとえ)ば籠(かご)の中の鳥なけば空をとぶ鳥のよばれて集るが如し。空とぶ鳥の集れば籠の中の鳥も出(いで)んとするが如し。口に妙法をよび奉れば我身の仏性もよばれて必ず顕れ給ふ」
(法華初心成仏抄・昭定1432~3頁)
同じく媒染を受け、あるいは帰依するなら、私たちにとって最高のものをいただかねばなりません。それが末法の凡夫にとっては上行所伝の御題目なのです。
信仰の本質はまさしく帰依・帰命(きみょう)することに他なりません。最高の御本尊・み仏のたましいたる御題目に帰依し、すべてを捧げることです。
「南無」とは梵語(ぼんご)で「帰依」を意味する語の音写(おんしゃ)です。妙法に帰依し、受持信唱させていただくのは、一見すると自分の外の存在に向かっているようですが、実はそうではないのです。外なる妙法に帰依し口唱することが、実はそのまま自分の内なる妙法(仏性)を呼び顕わす(開き、啓発する)ことに他ならないのです。
それを日蓮聖人は籠の中の鳥と外の鳥とが鳴き交わす様(さま)に譬えておられるのです。しかも、妙法でなければ妙法(仏性)は呼応しないのです。志村さんは「自分で自分を媒染する」「あるいは帰依する」とき最高の色を発色するのではないか、と言っていますが、妙法の口唱はこの一行に両方の意味を兼ね備えているとも申せましょう。最高の御本尊(妙法)に帰依し妙法を口唱することによって、実はお互いの内に秘めた最高の素質(妙法・仏性)を開き、啓発させていただくのですから。
鳥が呼び交わす譬えは、本当によくわかります。
筆者も、少年のころ田舎で育ちましたから、メジロやウグイスを同じ方法で捕えました(現在はそんなことをすれば違法で、罰せられますが)。よく鳴く鳥を一羽籠に入れて森に行き、木の枝に吊るして、その周囲にトリモチを付けた細い棒を何本か仕掛けておくと、野生の同種の鳥が集まってきて、内と外で鳴き交わしているうちにトリモチにかかるのです。メジロにはメジロ、ウグイスにはウグイスが集ってくるのです。
日蓮聖人も、もしかしたら少年時代にそんな経験がおありだったのかもしれません。いずれにせよ、これは当時の民衆にもよく知られていたことなのでしょう。
開導聖人が御教歌に次のようにお示しくださっているのも同じ意かと存じます。
妙法の声をよそにやきゝぬらん
おのが心の名ともしらずて
(拝要抄(下)・扇全12巻167頁)
「凡夫の心の中に眠っている仏性の名が実は他でもない御題目なのだから、御題目を唱えるということは、実は自身の仏性に呼びかけているということなのだ。そのことに早く気付き、自覚してほしい」と仰せなのです。自分の名を呼ばれた方が、目も覚め易いのはもちろんですね。

- ㉛謗法を戒める―信仰の純正化(3)
- 2015年7月22日(水)
―「原理主義」に陥(おちい)らぬよう―
○「原理主義」について
前々回来「謗法を戒める―信仰の純正化」のテーマで2回にわたって記し、その(1)では「根本の謗法」である「妙法不信」について説明し、その(2)では「謗法の態様」について略説いたしました。(2)では、謗法に対する折伏に関して、まず最初に整理・区分しておく必要があるものとして、「信者(宗内)」と「宗外者」とがあり、これを混同してしまわないように注意するべきである旨申しあげました。宗外者はもともと謗法の人ではあるものの、それは致し方のないことであり、むしろ教化して正法に帰入せしめ、真の幸せへと導くべき人であるのに対して、信者は既に入信し、妙法に帰依(きえ)した人だからです。「信仰の純正化」というのは、主として信者を念頭に置いたものであり、例えば宗風の各号、特に第4号(決定[けつじょう])の「妙法に一心帰依」とか、同第3号(止悪[しあく])の「習損[ならいそんじ]を戒め、謗法を折伏する」等は、当然ながら「信者を対象」とするものなのです。
注意を要する例として、親は強信者(ごうしんじゃ)であっても、当人は「ご信心から離れていた信者の子弟」を挙げましたが、同様のことは「宗外から信者に嫁いできた女性」等にも申せます。「信者と結婚した以上あなたも信者だ」という思い込みや決めつけは要注意です。そういった子弟やお嫁さんに対しては、むしろ宗外者を教化し、育成していくのと同じ姿勢で臨むべきではないかと存じます。
一概には申せませんが、家族・親族や、周囲のご信者にもそういう配慮が求められているのではないでしょうか。こうした場合、無意識のうちに「あなたも信者だ」と決めつけて、ややもすると信者に対するのと同様の視点で折伏をしてしまう例もあるようで、そうなると思いがけない無用の反発を誘発してしまうことにもなりかねません。むしろ「宗外者と同じなのだから」くらいに思い、「これから教化育成だ」という姿勢で臨んだほうが失敗が少ないように存じます。
さて、今回は「謗法を戒め信仰の純正化の努力をする」ことが、誤って「原理主義」に陥らないように、というテーマです。
そこでまず、いわゆる「原理主義」とはどういうものなのかを概説しておきます。
ご承知のように米国での同時多発テロ事件が発生して以来、「イスラム原理主義」という言葉があらゆるメデアを通して私達の耳目に触れるようになりました。この「原理主義」(ファンダメンタリズム)というのは、概して「何事であれ、一つの原理原則を金科玉条(きんかぎょくじょう)と決め込んで、それを他者に向けて強硬に主張する」というあり方だとされます。また、その共通の特色として、その内部では自分達の主張が「原理主義」だとは考えていません。例えば『コーラン』を絶対視し、そこに記されている通りのことを現代にも実践・実現し、それ以外の社会現象のすべてを否定しようとするのが「イスラム原理主義」ですが、当のイスラム原理主義団体の側には「イスラム原理主義」という言葉はありません。言葉すら無いということは、当然その自覚もないわけです。
東京外国語大学教授(比較宗教学)の町田宗鳳(そうおう)氏は近著の『なぜ宗教は平和を妨げるのか』(講談社+α[ぷらすあるふぁ]新書)で次のように記しています。
〈すべての信仰には、それぞれ独自の「宗教の原理」があるが、それは個々の宗教を特徴づけるものであって、決して有害なものではない。(中略)「宗教の原理」が問題となるのは、それが柔軟性を失って、硬化したときである。(中略)
信仰が純粋であればあるほど、異教の「宗教の原理」との心理的境界線が太くなり、まるで異人種でもあるかのように異教徒を見はじめる。それがいわゆる原理主義であるが、信仰の異なる者に対して排他的になり、やがてその立場を暴力的にでも否定しようとする〉(同書162頁)
また解剖学者・養老孟司(たけし)氏も近著『いちばん大事なこと』(集英社新書)の中で次のように言っています。
〈環境問題について、これまで私が発言したくなかった理由の一つに、環境問題の活動家たちのあいだに「環境原理主義」とでも呼ぶべき思想があったことがある。たとえば、グリーンピースという世界的な環境保護団体がある。かれらはクジラを絶対に食べるなという。(中略)それなら増えすぎたクジラは食べてもいいじゃないかと思うが、そういう話は通じない。(中略)
かならずしも予測が可能ではないこの世界では、「絶対」ということはありえない。(中略)現代社会で私が不安に思うのは、そこの理解である。たとえば宗教が提示する「絶対」に従う人間があんがい多い。宗教上の原理主義はそれである。近年ではオウム真理教の問題がそれだった〉(同書48頁~49頁)
○比較不能な価値観の対立と原理主義
東京大学法学部教授(憲法学)長谷部恭男(やすお)氏は、最新刊『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書)で次のようにいいます。
〈人生の意義にかかわる二つの根底的な価値観、たとえば2つの異なる宗教は、両方を比べる物差しが欠けているという意味で、比較不能である。それぞれの宗教は、それを信奉する人にとっては、その宗教こそが最善の宗教である。2つの宗教の価値を比べる物差しはない。(中略)
比較する客観的な物差しのないところで、複数の究極的な価値観が優劣をかけて争えば、ことは自然と血みどろの争いに陥りがちである。それぞれの人生の意義、宇宙の意味がかかっている以上、たやすく相手に譲歩するわけにはいかない。しかも、人の能力はさほど異なるものではなく、一方の陣営が必ずしも圧倒的な優位に立ちうるわけではない。宗教の対立が戦争を生み出しがちなのは、自然なことである。
哲学者のリチャード・ローティは、旧ユーゴスラヴィア等で民族や文化の対立が内乱を引き起こすとき、対立する者同士は、相手をそもそも「人間」とみなさない傾向があると指摘する。ボスニアのセルビア人にとって、ムスリムはもはや「人間」とはいえない。自分たちが人間として生きる上でこの上なく大切だと思う文化や価値を重んじない人間が現れれば、それを自分たちと同じ「人間」として扱わないということも生じうるであろう〉(同書55頁~57頁)
このような「価値観の比較不能性」が持つ意味をよく理解すれば、まず求められる課題は〈宗教的にも、哲学的にも、また道徳的教理の点でも正義と公正にかなった社会を確立すること〉であり、〈そして、これが課題として意識されるにいたった背景には、宗教改革とそれを発端とする宗教的寛容に関する論争がある〉(同書187頁)
とあります。
実は西欧の宗教戦争に対する反省に基づく、「価値観の比較不能性」を踏まえた「宗教的寛容」の思想こそ、立憲主義に相当する発想の基点の一つだとされています。だからこそ、日本国憲法も「信教の自由」を厳格に保障し、宗教に対して国及びその機関が中立・公正であり、宗教が国家権力から自由であることを明定しているわけです。
先程来、少々難しい引用をしていますが、全体としてご理解いただきたいのは、まず第1に、宗教には元来原理主義的な要素が内在していること、しかし、そのこと自体は決して有害なものではなく、むしろ個々の宗教を特徴づけるものだということです。しかし第2、にそうした宗教の原理が硬化し、柔軟性を失い、尖鋭化して、他者に対して排他的、暴力的になる(オウム真理教やイスラム原理主義、キリスト教原理主義等がその例)とこれは大きな問題となります。そして第3に、こうした宗教的原理主義が政治・経済の原理や民族の原理と結び付き、さらに権力と結び付いた場合には、紛争や戦争さえ引き起こしかねません。そうした危険から市民を守るための制度が、立憲主義であり、信教の自由の保障であり、政教分離原則なのです。国家権力の宗教に対する中立性・不介入や、政治的な権力と宗教との分離が求められる原点はここにあります。この背景として第4に、「価値観の比較不能性」(例えば思想や宗教や文化の価値の優劣を計る客観的な物差しは無いこと)に基づく「宗教的寛容」(他の宗教の存在を互いに容認しようとすること)も、権力側には強く求められているということも理解しておく必要があるのです。
○当宗の謗法観―原理主義との対比
では当宗の謗法観とはどういうものでしょう。開導聖人の御指南には、
○「法に背(そむく)を謗と云(いう)也」
(このシリーズ㉙で引用。扇全14巻23頁上欄)
○「仏祖の御意(みこころ)に背(そむ)く事をすればみな謗法也と知るべし」 (扇全7巻74頁)
とあるごとく、基本的に「妙法に違背すること」また「妙法(正法)を正しく教導された仏祖のみ教えに背くこと」はすべて正法を謗(そし)る「謗法」なのです。なぜなら妙法こそこの全宇宙の真理であり、生命であり、唯一根本のみ仏であり、全ての諸仏諸天善神を包摂する絶対の理法だからです。この妙法に帰依し、信奉する佛立信徒にとっては、妙法こそが唯一絶対・最高の教えです。唯一絶対の仏であり教えである以上、これを信受すべきであり、それができなかったり、その教えに違背するあり方は、当然すべて謗法だということになります。これがいわば当宗の謗法観の根本です。ここには当然ながら佛立宗としての「宗教原理」が存在します(例えば「佛立開講150年奉賛歌」の歌詞・参)。
しかし、町田氏も指摘するように、宗教は元来独自の宇宙観、世界観、価値観を有するものであり、真理の体系を持っていて、それが絶対のものであると主張するものです。むしろ、そうした教義体系は各宗教の独自性を特徴づけるものであって、それなしには宗教としての一宗の存在意義も認め難いとも申せます。
各宗教の価値の優劣を計る客観的基準がないため、国家権力等が宗教問題には介入しないのは当然といえば当然です。しかし、宗教・宗派間ではそうは参りません。各宗教が布教活動を行うにあたっては、当然ながら自宗・自派の優越性を主張します。当宗でいえば、宗外者に対する教化・折伏に際して、佛立宗の正当性や優位性を主張するのは、布教活動の一環としても当然なのです。ただその場合にも、次の諸点はよく心得ておく必要があろうかと存じます。
まず第1に、既に一定の思想なり信仰なりを持っている人に対しては、一概に真っ向からそれを否定したり、「謗法で間違ったもの」だと決めつけたりしてしまわないことです。まずは一応そうした信仰や思想の存在を認めた上で、なおかつ、例えば、すべては妙法の真理の中に包摂されてしまい、すべては御題目にこもるのだから、その他に別の教えを信奉する必要はないのだ、といった方向で説得する必要があります。
第2に、それでも、論理的・教義的な面での説得には限界があります。それは先に記したように、各宗教は独自の教義体系を有していて、その客観的な優劣を決定する共通の物差しはなく「比較不能」であるため、異なる宗教間ではいわば「議論の土俵」そのものが異なっており、いわゆる「水掛け論」の応酬となってしまうからです。「教義的な論争(法論)は不毛だから、むしろ客観的・具体的な事実(現証)の説得力を重視し、これで勝劣を決せよ」という先師の教えは、こうした法論の不毛性を踏まえたものなのです。当宗が「現証」を重視し、「現証布教」を大切にする理由もここにあります。
第3に、たとえ相手が反発しても、それでも何とか助けたいと思う心や姿勢が求められます。反発や攻撃に対して怒りの心を起し、こちらも反撃するということは許されません。教化折伏は慈悲に基づく菩薩行だからです。それなのに、こちらが正しいからといって、相手を正義に反する敵として攻撃したりすれば、それこそ「原理主義」に陥ってしまいます。それは慈悲を根とする「不軽流の折伏」ではありません。反発し暴力的な相手をも尊敬し、礼拝して、ついに正法に帰依せしめようと努力すべきだ、という姿勢が求められているのです。み仏も、不軽菩薩も、蓮・隆・扇三祖もみな暴力的な迫害や弾圧を受けられましたが、決して暴力的な応酬はなさっておらず、むしろ迫害を加えた人たちを「善知識(ぜんちしき)」(自身の信仰を高め、導くもの。よき教師の意)だと受けとめておられるのですから。
国家が各宗教に対して介入せず、中立を守ることを求めることの基礎となった「宗教的寛容」は経験に学んだ極めて大切な思想です。しかし、これは各宗教間ではそのままではありえません。各宗教が自宗以外の宗教を「そのまま是認する」とすれば、自宗の独自の存在価値もなくなってしまうことにもなるからです。無論そこでは「折伏」も必要ないことになってしまいます。そういう寛容さは、誤りをもそのまま正すことなく是認し、目をつむって受容していく、いわゆる「摂受(しょうじゅ)」になってしまいます。これは信仰の純正化を大切にする当宗の呵責謗法(かしゃくほうぼう)・折伏の教えに反するものです。
開導聖人は御指南に仰せです。
○「されば末法悪世には宗論問答何の詮(せん)かあらん。現証利益こそ御弘通の道也」
(開化要談・体・扇全13巻318頁)
○「経力を以て諸宗の学匠に勝ち、利生を以て人を助くる経力宗也」
(開導要決・扇全27巻239頁)
宗外者に対しては教義的論争ではなく、妙法の経力つまり現証利益という事実による折伏・説得が教化の直道(じきどう)であるとの御指南です。
また宗内に対しては次のように仰せです。
○「信者互に懈怠、不参、不行儀等を責合(せめあ)ふが持戒(じかい)なるを、責(せめ)ずして彼が為(ため)の悪友となるをかたく謹みて、臆病(おくびょう)なく、にくまるゝ迄に実意(じつい)をもて責るは当宗の持戒なる事」
(百座一句・扇全14巻357頁)
○「瞋恚(しんに)をおこさず実非(じっぴ)を糾明(きゅうめい)して、ことおだやかに取り計らひ(乃至)互ひにいさめあひて云々」
(三組講頭披露異体同心教誡状・扇全2巻380頁)
ご信者間で信仰の純正化のため折伏する場合であっても、相手を思う慈悲の心をもととし、真心をこめて折伏することや、「ことおだやかに取り計らひ」「互ひにいさめあ」うことが大切な心得だと仰せなのです。
これは宗内外いずれを通じてもいえることですが、いくら正しいことでも、言葉荒く、怒りにまかせて相手をなじっては、相手は腹を立て、反発を招くばかりで、それでは折伏も通りません。これは折伏の失敗という他はありません。開導聖人も、そんな折伏は「折伏の仕損じ」だと仰せです。やはり、信者間での謗法の折伏も、時と場所や状況をよく踏まえ、無用に相手を傷つけず、相手が得心し、腑(ふ)におちるよう、慈悲の心でさせていただくことが大切なのです。
○「人をうらめば我に罪あり。他を助くれば我に福あり。因果応報とは是なり」
(人を拝むに慈悲深かれの事・扇全17巻21頁)
との御指南もあり、また高祖日蓮大士の御妙判にも次のように仰せです。
○「かゝる重病をたやすくいや(癒)すは独(ひと)り法華の良薬(ろうやく)也。只(ただ)須(すべから)く汝(なんじ)仏にならんと思はゞ、慢(まん)のはたほこ(憧)をたをし、忿(いか)りの杖(つえ)をすてゝ、偏(ひとえ)に一乗に帰(き)すべし。(乃至)上根(じょうこん)に望めても卑下(ひげ)すべからず。下根(げこん)を捨(す)てざるは本懐(ほんかい)也。下根に望めても憍慢(きょうまん)ならざれ」
(持妙法華問答抄・昭定278頁)
「末法現代の衆生はすべて貪瞋癡(痴)[とんじんち]の三毒の重病に苦しむ定業堕獄(じょうごうだごく)の凡夫である。こんな重病を癒すことができるのはただ御題目という良薬だけなのだ。どうかあなたも慢心や忿怒(ふんぬ)の心を捨て、妙法に帰依されよ。(中略)自分より優れた人に対して卑屈(ひくつ)になったり、劣った人だからといって傲慢(ごうまん)になったりしてはならない。救い難く度(ど)し難い人を救済することこそがみ仏の本懐であり、私達の第一の願いなのだから」、とのお心です。
こうしたみ教えのおこころを常に忘れないで宗内の信仰の純正化に努め、宗外者の教化折伏に臨ませていただけば、当宗の「謗法に対する折伏」が間違っても原理主義に陥ることはないと存じます。

- ㉚謗法を戒める…信仰の純正化(2)
- 2015年6月19日(金)
―「原理主義」に陥(おちい)らぬよう―
○謗法―その中身と態様
前回は「謗法を戒める―信仰の純正化(1)」として「根本の謗法」である「妙法不信」について説明し、この「不信」とは「積極的に妙法を信じ行ずる以外のすべて」、つまり「積極的に妙法を誹謗(ひぼう)し敵対する」ことはもとより、「信ぜず行ぜぬ」状態や、さらには「無関心」や「妙法を知らない」状態をも含む旨申しあげ、開導聖人の御指南もいくつか紹介させていただいた上で、〈要するに、当宗においては、上行所伝の妙法の受持信唱こそが信行の根本なのであり、妙法の一向口唱、一心帰依が肝心なのであってこれに反するもの、不純なものはすべて「謗法」となり、そうなると現証の利益はもとより、成仏の果報など到底いただけないことになるのです。
「謗法を戒める」ということは、そういう意味で「信仰の純正化」を意味するわけです。「妙法不信」という根本的な謗法がもととなって、懈怠(けだい)をはじめ信行ご奉公の具体的なありようにつき、さまざまな謗法が生じてきます〉と記しました。
今回は、この「根本謗法」に基づいて生じてくる謗法の中身ないし態様について極く概略の説明をさせていただき、次回では、特に「謗法に対する折伏」が、誤っていわゆる「原理主義」に陥(おちい)らないための用心について言及したいと存じます。
なお、まず最初に整理をしておかねばならないと思うのは、「信者」(宗内)と「宗外者」(宗外)との区分です。
「信者」も、「無始已来」の御文で常に言上申しあげるように、元来は妙法に違背してきた謗法の人だったのですが、入信して妙法に帰依してそれ迄の謗法を懺悔し、仏祖のみ教えに随順して罪障消滅を志す者です。その信行の道を歩むについて道を誤ることのないよう(つまり謗法を犯さぬよう)信心の純正化を心掛けるわけです。
これに対してまだ当宗に入信していない宗外の人びとは、当人の知・不知は別として、まだ妙法に帰依していないのですから、その意味で皆すべて「謗法の人」なのであり、一日も早く正法に随順せしめるべく折伏・教化をさせていただくべき対象に他なりません。宗外者を指して「謗法人」と一括して呼ぶこともありますが、それはそういう意味ですから、宗内でこそ許されるとしても、宗外者に向かって使用すべき呼称ではありません。
また同じく「謗法に対する折伏」でも、信者に対するときは主として「信行の改良や育成」を目的とするものであり、宗外者に対するときは「教化」を目的とするものなのです。こんなことは当然のことですし、よく分かっていることだとは存じますが、それでもややもすると混同してしまうようなこともあるようですから、やはり注意が必要です。宗外者に対して、あるいは本人はまだ信者の自覚を持っていない人に対して、こちら側はまるで「信者のごとく」思い込んで折伏をしてしまうようなこともあるわけです。
例えば、ご信者の家族・子弟で、幼い頃は親と共に薫化会やお寺に参詣していたものの、成長してからは信心から離れ、いわば宗外者同然になっている人に対してはどうでしょう。少しは当宗のことを知っているにしても、当人の意識なり自覚なりの上では信者とは言い難いのですから、そういうことをよく踏まえ、むしろ宗外者に準じた対応をする配慮が必要でしょう。
それなのに「あなたの親は立派な強信者だった。あなたもこうしなければ謗法だ」などと言ってしまったら、相手は到底受け入れ難いのではないかと存じます。これに類したことは他にもいろいろとあると存じます。「混同しないように」というのはそういうことです。
「謗法」はもちろんすべての衆生に基本的に該当するものであり、その折伏・改良も同様です。けれども、すでに信者となった者に対する場合と、宗外者に対する場合とでは、その折伏・説得のあり方も手順も当然異なるのだということをよく弁えておく必要があります。開導聖人の御指南をいただく際も、その点は留意する必要があるわけです。因みに開導聖人の御指南で謗法に関するご教誡の多くは、やはり信者に対するお折伏であり、信心の純正化に関するものだと申せます。
○「謗法」の種別と態様
謗法の種別と態様については、実に様々なものがあり、具体的な場面での細かな区分や類別をしていけば、文字通り際限がないと存じます。そこでここでは極く極く基本的な概説のみでお許しいただきたいと存じます。
①妙法不信(違背)、疑迷〔ぎめい〕、懈怠〔けだい〕
○「妙法不信」は既に記したごとくいわば「根本の謗法」です。そこから、意識的にせよ、無意識的にせよ、あらゆる謗法が派生してきます。「疑迷」は妙法や仏祖のみ教えに信順せず、これを疑ったり、道に迷ったりすることです。これは主として凡夫の考え・我見〔がけん〕(世間のいわゆる“常識”も含む)が邪魔をしているわけで、その意味では凡夫の「我」(が)こそが「信」を妨げる根源だと申せます。またこれは「自分の我見が仏祖のみ教えより優先する」ということで、これを「慢心」「憍(驕)慢〔きょうまん〕」と申します。そしてこうした心がもととなり「懈怠」が生じます。凡夫は元来が怠りがちなものですが、正しい信心のあり方、角度を定めても、これに向かって進む(精進〔しょうじん〕)ことを怠けるわけですから、これではご利生もいただけません。
○開導聖人が御教歌に
御利益のいたゞけぬみち四(よ)ついかに
うたがひまよひほこるをこたる
と仰せなのは正しくこの点です。
○「法華経は一切経の中の王也。南無妙法蓮華経の五字は一部(いちぶ)の御意(みこころ)也。故に万法具足の秘要法と申也。何(いず)れの経々の功徳も、何れの仏菩薩等の御利生(ごりしょう)も、みなみな此(この)一大秘法にこもれり。故に余宗余経(よしゅうよきょう)をたのむ心あるを謗法の疑迷(ぎめい)といふ也。御利生なし、御罰あり。」
(如四観三意抄・扇全13巻11頁)
○「もろもろの薬を薬とおもひて、上行所伝の要法(ようぼう)《良薬》を不信のものは、宗内の謗法人也。大良薬(だいろうやく)の外(ほか)に諸(もろもろ)の薬を求るは謗法也。」
(御弟子旦那抄上・扇全14巻75頁)
右の御指南は共に「疑迷」の具体的かつ代表的な例で、要は妙法に一心帰依のできていない姿です。また次のようにも仰せです。
○「信者謗法を改めずしていか程口唱に励むとも御利生ある事なし。云はゞ風呂のつめをせずして水を汲入(くみい)るゝが如し。」
(十巻抄第三・如説抄拝見完・扇全14巻411頁上欄)
妙法はすべての功徳が不足なく具(そな)わっている大良薬なのだから、ただ一筋に妙法の受持信唱をさせていただくいことが肝心。それなのに疑迷等の謗法があっては、いくら妙法を口唱しても御経力をいただくことなどできない。それはあたかも栓(せん)の抜けたままの風呂に水をためようとするようなものだ、と戒められるのです。
②「事相の謗法」と「心の謗法」
「事相の謗法」とは外見からそれと見える謗法、外形的に認知できる謗法のことであり、「心の謗法」とは内心の謗法で、外見からはそれと認識しにくい謗法を指します。
開導聖人は御指南に仰せです。
○「病(やまい)のつらさに謗法の札守(ふだまもり)等は払(はら)ふと云へども、其(その)心に若(もし)思ひ引(ひか)るゝ事かくし有る謗法等あるときは御感応(ごかんのう)なし。猶(なお)責(せ)めて用ひざれば助行する事なかれ。」
(和国陀羅尼〔やまとだらに〕・扇全14巻317頁)
右の御指南は次の御教歌のお書き添えです。
○おぼつかな折伏うけて謗法を
はらへど人をうらみがほなる
病人を折伏して入信せしめ、他宗堂社の札(ふだ)や守(まもり)等、外形からそれとわかる謗法(事相の謗法)は何とか払う(これがいわゆる「謗法払〔ほうぼうばらい〕」)ことはどうにかできたのだけれど、まだ心底では得心していないらしく、いかにも未練(みれん)がましい表情をしている(つまりまだ「心の謗法」は残存している)。これでは本当の入信・帰依ができていないのだから、ご利生をいただくこともおぼつかない。この点を再度よく折伏し、得心させてからでないとお助行も効果がなく、無駄になってしまい、結果却(かえ)って妙法を疑い軽しめることにもなりかねないから、そこをちゃんとするまではお助行もしない方がいいぞ、との意です。
概して「事相の謗法」は外形上のものですから折伏して払うこともある面で容易ですが、「心の謗法」は内心のもので外から認知しにくいため払いにくいとも申せます。余程ことを分けて穏(おだ)やかに、よくよく説明して、得心させる必要があるわけです。
③「言語の謗法」「所作の謗法」「心の謗法」
これはいわゆる「身(しん)・口(く)・意(い)三業(さんごう)」で犯す謗法です。こういう類別もあるのです。
御指南には次のようにございます。
○「先(まず)自(みず)らをつゝしむの一段。
われと謗法を改むるに大なる功徳をうる也。
さんげして口唱すれば所願速(すみやか)に成就す。
一 言語の謗法
二 所作の謗法
三 心の謗法也。(後略) 」
(一紙一座法門抄・扇全6巻428頁)
これは何れも「自身の改良」を促された御指南ですが、信者一般や相互にもあてはまります。
(1)「言語の謗法」は三業のうち「口」の謗法です。自身が嘘をついたり、謗法がましいことを口にするのはもちろんですが、同時に他の信者が口の謗法(悪口〔あっく〕、両舌〔りょうぜつ〕、妄語〔もうご〕等)を犯しているのを見聞きしながら折伏しないのも「与同(よどう)の謗法」(与同罪とも。自身が直接謗法を犯すのではないが、見てみぬふりをし、折伏しないのは直接犯しているのと同じ、いわば共犯だというのが「与同」の意)だと戒めておられます。
(2)「所作の謗法」は身体の振舞での謗法ですから、三業では「身」の謗法です。所作のすべてにわたりますが、例えば「他宗の堂社の前にて足袋(たび)のひもを結ぶ等」、心ではそうでなくても外形から見て謗法と紛(まぎ)らわしい所作振舞(これを「相似〔そうじ〕の謗法」と申します。気持は全くそうでなくても、他から見て間違われかねないような行動)も可能な限り避けよ、と諭されています。いわゆる「李下(りか)に冠(かんむり)を正さず。瓜田(かでん)に履(くつ)を納(い)れず」(文選〔もんぜん〕)ということです。
(3)の「心の謗法」は意業によるもので、内容は既に説明した通りです。なお、(1)と(2)は「事相の謗法」でもありますね。

佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.