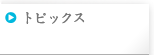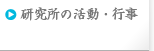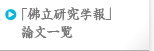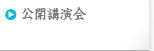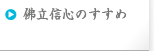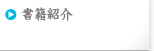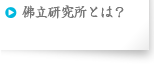-
- 2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
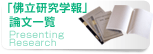
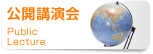
- ㉗平等と差別(不二[ふに]と而二[にに])(1)
- 2015年2月17日(火)
─「ジェンダー・フリー」に寄せて─
○「差別」と「区別」「差違」
前回は「無常」について『徒然草(つれづれぐさ)』の一節なども引用しながら、「自身も含めてすべては無常であるが、だからこそ一日一日を大切に」ということを申しあげました。ただ、前回は触れませんでしたが、「諸行無常」といえばすぐに生命の無常、生老病死の迅速(じんそく)であることに意識が向かいますが、「無常」によって感得すべきものは、決して悲観的な価値観や感懐だけではありません。「無常だからこそ今が大切」という、現在の価値を高からしめる価値転換はもちろんのこと、もう一つ「すべては遷(うつ)り変り、変化する」からこそ、例えば「現在が苦しくとも、それが善い方向に変わっていくことも可能」であるというプラス方向での受け止め方もできるのです。
つまり、「冬はいつかは春になる」という把(とら)え方もできる訳です。「すべては変化する」とはそういうことでもあります。何時かは知らないが、刻一刻臨終に近づいているのは厳然たる事実ですが、だからこそ今を大切に、というのと同時に、今と未来をよりよい方向に変えていく、それを自身の努力はもとよりのこと、妙法の経力を頂いてさせていただこうというところに、このご信心の妙味があるのだと存じます。
さて今回は「平等と差別」というテーマです。これも随分大きな問題ですから、そのほんの一部を、特に役中さんにも必要だと思う範囲で触れておきたいと存じます。最初にちょっとお断りしておきたいのは「差別」という言葉の意味です。現代の用語で「差別(さべつ)」というと「法の下(もと)の平等」に反するような、人種、性別、家柄等による非合理的ないわれのない差別、つまり人種差別とか女性差別等の社会的、文化的、心理的な偏見に基づく蔑視や不平等なあり方を指しますが、仏教でいう「差別(しゃべち)」は、決してそういう意味ではなく、現代用語で言うなら「差違」「相違」「区別」等の意味で用いています。この点どうか誤解のないようにお願いします。私もできるだけそうした誤解を招かないよう、注意はいたしますが、どうか混同・誤解をなさいませんよう、この点よろしくご注意ください。
○「不二(ふに)」と「而二(にに)」
前回にも引用させていただいた開導聖人の御指南に「能所(のうじょ)不二(ふに)の上に而二(にに)なりの事」(扇全17巻338頁)という出典がありました。これは「道場」に関する御指南で、法華経如来神力品第二十一の中の「若於僧坊(にゃくおそうぼう) 若白衣舎(にゃくびゃくえしゃ)〈乃至〉是中皆応起塔供養(ぜちゅうかいおうきとうくよう)〈乃至〉当知是処即是道場(とうちぜしょそくぜどうじょう)」[若(もし)は僧坊においても、若は白衣の舎(しゃ)にても、〈乃至〉是中(このなか)に皆塔(みなとう)を起(た)て供養すべし。〈乃至〉当(まさ)に知(しる)べし、是処(このところ)は即(すなわち)これ道場也](『妙講一座』所収)の「即是道場」の理解の仕方についての説明でもあります。
どういうことかと申しますと、この御文は、み仏が、寺(僧坊)であろうと、在家の信者の家(白衣舎)であろうと、山や谷間や曠野(こうや)であろうと、それがどこであっても、御題目(御本尊)をおまつりして御題目をお唱えすれば、そこは皆「道場」なのだと仰せになっているという御文です。この「即是道場」とあるのを根拠に、「自宅にも御宝前があるのだから、これもお寺と同じく道場に違いがないはずだ。だから、特にお寺や御講席に参らなくても自宅でしっかりお看経(かんきん)をあげていれば十分で、何もわざわざ遠くまで参詣しなくてもいいでしょう」、というご信者の質問に対して、「いや確かに道場という意味では同じ一つのもの(不二)だけれど、同じ道場でもその中にも能所(のうじょ)という違い、区別がある(而二)のだよ」、というのが「不二而二[ふににに]」(不二にして二)ということなのです。
「能所(のうじょ)」というのは、このシリーズの通番の⑤(平成14年5月号)で少し説明したように、「能」は元来が漢文の「能(よ)く……す」という能動の意であり、「所」は「……せ所(ら)る」という受身・受動の意に基づくもので、例えば「能化(のうけ)」は化導をする側、「所化(しょけ)」は化導を受ける側であり、仏と衆生、師匠と弟子等もそれぞれ能所の関係になるわけです。前回で「本(もと)」と「末(すえ)」と記したのも、こういう意味に基づく「本末(ほんまつ)」です。念のため申しますと、み仏においても久遠の本仏は「能」、他の諸仏・迹仏(しゃくぶつ)はすべて「所」ですし、み仏に対すれば衆生は、すべて「所化」です。
末法のお互い衆生はすべて三毒強盛・定業(じょうごう)堕獄の凡夫なのですから「師弟(してい)ともに凡夫」であることは同じ(不二)ですが、その同じ凡夫であっても師弟という違い・区別はやはりある(而二)ということになります。仏教でいう差別(しゃべち)というのは原則としてこういうことです。
もっとも小乗仏教はもとより大乗仏教でも法華経以前は五逆(ごぎゃく)罪を犯した極悪人はもとより、声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく)の二乗(にじょう)、女人(にょにん)等は成仏できないとされていました。これはやはり不平等で差別的な教えだといわれても致し方ないと存じます。しかし法華経はそうではありません。極悪人も、二乗も、もちろん女性も、誰であろうと妙法を信じ唱えて菩薩行に励めば、すべて成仏できるのだと申します。その意味で「平等」です。ただし、先にも記したように、末法のお互いはすべて未下種(みげしゅ)の凡夫ですから、妙法を受持信唱しない限りは定業(じょうごう)通り堕獄する、という点でも平等です。こういう基本的な平等の上での「師弟」であり、「教講」であり、「役中」と「一般信者」という能所の別・差違・区別があるわけです。さらに申せば、同じ役中や信者でも、十人十色で皆違います。これも「而二」です。
これを世間でいえば老若男女おしなべて人間であるという点においては全く同じ(不二)だけれど、その中でも老幼、男性と女性、親と子といった違いもあれば、さらに個性もあるということですね。もっとも、この違いが「男女の性別で上下がある」という考え方になると、これはいわゆる「女性差別」に他なりません。これは誤った考え方ですが、程度の差はあっても、どこの社会にも、そうした差別が現代でも存在しています。これを正しい方向に変えていこうとするのが「女性学」であり、いわゆる「ジェンダー・フリー」という概念です。
現代のお役中はこういった問題もある程度承知しておく必要があり、それは今後ますます重要になってくると存じます。私自身、この問題に関していえば、改良すべきところが多々あるわけで、決して偉そうなことは申せません。文字通り「一緒に入門」ということで、極く基本的な理解だけでもさせていただきたいと存じます。○「女性学」と「ジェンダー・フリー」
いわゆる「女性学」や「ジェンダー・フリー」に関する書籍は、少し大きな書店へ行けば専門のコーナーが設けられており、関係書はそれこそ山ほど刊行されています。ちなみに私が参考にさせていただいたのは『女性学教育・学習ハンドブック=ジェンダー・フリーな社会をめざして』(新版・国立女性教育会館 女性学・ジェンダー研究会編著 有斐閣[ゆうひかく] 2001年刊)です。
同書によれば、「女性学は1960年代末の第二フェミニズム運動の中から生まれたが、女性差別の撤廃(てっぱい)は、『国連女性の十年』をつうじて世界の女性たちの共通目標となり、『女性差別撤廃条約』や『北京行動綱領』へと結実していった」ものです。そして「女性学が誕生以来、ここ四半世紀の間に生み出した主要概念の一つが『ジェンダー』(社会的・文化的な性別・性差別)である」とあります。したがって「女性学」でいうジェンダー概念は「男女の上下、優劣、支配服従の関係を維持するための装置」なのです。もう少し説明すると、「ジェンダー」(Gender)とは、「一般に、オス、メスといった生物学的な性のあり方を意味するセックス(sex)に対して、文化的・社会的・心理的な性のあり方をさす用語として使われている。(中略)『男らしさ』『女らしさ』といった固定的な『らしさ』を意味する。セックスは自然が生み出したものだが、ジェンダーは、人間の社会や文化によって構成された性であり、文化や社会において、また歴史の展開に対応して変化する」とあり、さらに「このジェンダーの構図は、家庭・地域社会・学校から職場まであらゆる生活領域において構造化されることで、男性優位の支配メカニズムを支える大きな要因ともなっている」ということです。「ジェンダー・バイアス」とは「ジェンダーに基づく固定的な決めつけ・偏見」等を意味し、こうした「ジェンダーの束縛(そくばく)から自由になった、固定的な性別にとらわれない状況」が「ジェンダー・フリー」なのです。「ジェンダー・フリー」に関する講座は、既に多くの大学や短大等に設けられており、自治体・企業・地域等でも研修会などが広範に開催されています。
どうでしょう。この問題に関するお役中の理解は、これからのご奉公の上でもとても大切になってくると思われませんか。次回ではもう少し具体的に申しあげたいと存じます。

- ヒマラヤ・ユキノシタです。
- 2015年2月12日(木)

- ウチのクリスマス・ローズです。
- 2015年2月12日(木)

- ㉖「無常」を忘れずに
- 2015年1月8日(木)
―だからこそ日々を大切に―
○「諸行無常」―今の大切さを知って―
前回は「御講こそ弘通の根幹」のテーマで『年頭のことば』の一節もいただきながら、「御開講の本旨(目的)」や「御講の本義」、「開講聖地」等について触れました。その際「付記」として末尾にこの「新役中入門」シリーズの既出のテーマの中で、特に参照しておいて欲しいと思うものをいくつか掲げさせていただきました。
その中でも「参詣の大事」(1)~(3)(シリーズ通番⑤~⑦・平成14年5月号~7月号)はもう一度併読いただければと存じます。特に「参詣の大事」(1)で触れた「道場の能所(のうじょ)」と「環境の大切さ」については、お役中にはよく心得ておいていただきたいと存じます。そこでくどいようですが念のため、このシリーズの⑤で紹介させていただいた御指南の一部を再度引用いたしておきます。それは平たく言えば「なぜお寺や御講席まで参詣することが必要なのか」「自宅でのお看経とどう違うのか」という疑問に対する開導聖人の回答とも申せます。それが(A)「道場の能所(のうじょ)」と(B)「環境の大切さ」ということです。
(A)については次のように仰せです。
「御法門心得(こころえ)違(ちがい)せる人の曰(いわく)
遠き所を日参は無益(むやく)の事也。我家(わがや)に本尊あり、道場と云(いう)。家内にありと云々。 道場に能所(のうじょ)ある事を知らず。」
(能所不二[ふに]の上に而二[にに]なりの事・扇全17巻338頁)
お寺や御講席と平生の自宅の御宝前の間(ま)とは、なるほど「道場」という点では同じ一つのもの(不二)だけれど、同じ道場でも能所[のうじょ](本[もと]と末[すえ])の区別がある(而二)。道場という名はなるほど同じだが、やはり本を大切にするということを忘れてはならない、という意です。
(B)に関する御指南は次の通りです。
「(乃至)されど家にありては心の散事(ちること)多し。又、歴縁対境紛動(りゃくえんたいきょうふんどう)す。凡夫(ぼんぶ)の向ひ奉る所、必ず其(その)向ひ奉る境(きょう)によりて信の起る故に、参詣には利あり。」
(三界遊戯抄一・扇全6巻333頁)
「歴縁対境紛動」の語は天台・妙楽の釈に記されている語です。要は凡夫は縁により環境によってすぐ心が紛(まぎ)れ動くことを申します。因みに「境」は「智」に対する語で、一般的に「場所・環境」を意味します。「智」は意識・知覚を持つもの、つまり生き物をさします。「智」を「主体」とすれば「境」は「客体」に相当するとも申せます。仏教では「境智一如(きょうちいちにょ)」といって環境とそこに住む生物とは、実は相互に深い対応関係があり、一体のものだと把(とら)えます。例えば仏と寂光、凡夫と娑婆という対応関係です(だから凡夫が成仏すれば、娑婆も寂光となるわけです)。人と環境とは元来こういう相応関係があり、相互に大きな影響を及ぼし合っているわけですから、お寺の本堂や御講席という環境に身を置いているときと、自宅に居るときとでは、同じ人でも自然に心のありようが違ってくる。だから参詣すれば「必ず其向ひ奉る境によりて信の起る」という効果があることを知らねばならないよ、と諭されるのです。「なぜ学校へ通う必要があるの。家でその分勉強した方が合理的だ」などという生徒に対しても同じ観点からの回答ができそうですね。
こうしてみると、お寺や御講席の環境は随分大切ですね。御講席のあり方や雰囲気(ふんいき)等、広い意味での「場づくりの大切さ」も、お教務やお役中を中心に改めて考え、見直し、大切にしてゆく必要があります。参詣した人が信心を起こし、増進してゆく環境であることが求められているのですから。
さて今回は「無常を忘れずに」というテーマです。無常は「諸行無常(しょぎょうむじょう)」つまり宇宙も含めたこの世のあらゆる存在・現象はすべて常なく変化し、一瞬もとどまることなくうつろっていくものである、という真理です。もちろんこの「すべて」の中に自分自身も当然含まれています。
この「諸行無常」は元来、仏法が、他の教えと異なる「仏法としての範疇(はんちゅう)」を判定する基準とする「三法印(さんぼういん)」(諸行無常印、諸法無我[むが]印、涅槃寂静[ねはんじゃくじょう]印)の第一印(いん)で、いわば仏法が他の教説に対して仏法たることを示す「旗印(はたじるし)」ともなるべき根本的な、そして基盤として立脚する真理です。日本にも当然仏教と共に伝わり、その「無常観」は特に平安期以降一般にも広く伝わっていきます。「無常観」が『源氏物語』から『平家物語』を経て『奥の細道』に至るまで、多くの日本文学の底流をなす大きな思想となっていることも周知の通りです。
その一例として『徒然草(つれづれぐさ)』の一節を見ておきたいと存じます。
○『徒然草(つれづれぐさ)』に見る無常観
『徒然草』はご承知の通り吉田兼好[よしだけんこう](1283?~1350)の随筆で、研究によれば1330年~1332年の頃の執筆だとされています。高祖日蓮大士[だいじ](1222~1282)の御入滅の翌年ころ生まれ、門祖日隆聖人(1358~1464)がご誕生になる35年前に亡くなっていますから、高祖と門祖のちょうど中間あたりを生きた人です。
『徒然草』は全部で243段からなっていますが、全体を通じて看取される基本的な思想の一つはやはり仏教の無常観です。例えば次のようにあります。
○第百五十五段
「生(しょう)・住(じゅう)・異(い)・滅(めつ)の移りかはる実(まこと)の大事は、たけき河のみなぎり流るゝが如し。暫(しばし)も滞(とどこお)らず、ただちに行(おこな)ひゆくものなり。されば、真俗(しんぞく)に付けて、必(かなら)〈ず〉果(はた)し遂(と)〈げ〉んと思はん事は機嫌(きげん)をいふべからず。とかくのもよひなく、足を踏(ふ)み止(とど)むまじきなり。
春暮〈れ〉て後(のち)、夏になり、夏果てて、秋の来るにはあらず。(中略)生・老・病・死の移〈り〉来(きた)る事、またこれに過〈ぎ〉たり。四季はなほ定〈ま〉れるついであり。死期(しご)はついでをまたず。死は前よりしも来(きた)らず、かねて後(うしろ)に迫(せま)れり。人皆死ある事を知〈り〉て、まつこと、しかも急ならざるに、覚(おぼ)えずして来(きた)る。沖(おき)の干潟遥(ひがたはる)〈か〉なれども磯(いそ)より潮(しお)の満つるが如し。」
(岩波・古典文学大系30・218頁)
※「生住異滅(しょうじゅういめつ)」(四相)…物が生じ、止(とど)まり、変化し衰え、滅する現象。※「たけき河」…水勢の激しい川。※「行ひゆく」…実現してゆく。※「真俗」…真諦[しんたい](仏法)と俗諦[ぞくたい](世俗)のこと。※「機嫌」…好機・潮時。
※「もよひ」…ためらい。※「ついで」…順序。
「四季にはまだ順序というものがあるが、人の生老病死、特に死期には順序はない。決して前から予告して次第に迫ってくるのではなくて、いつのまにか自分のすぐ背後に迫っているのだ。人はいつか必ず臨終のあることを知ってはいるのだが、まだまだだと思っているうちに突然の死が訪れるのだ。それはあたかも遠浅の海辺で沖の干潟はまだまだ遠く広がっていると安心していたら、あろうことか自分の居る岸辺の磯の方から潮が満ちてきて足もとをすくわれ、驚き慌てるようなものだ。」(概訳・向井)というのです。実に分かり易く説得力のある文章で、『徒然草』の中でも名文の一つとされるのも当然だと思います。なお、遠浅の海での満潮の譬えも、海辺で海水浴や潮干狩をしたことのある方なら、自分の経験に照らしても得心というか、よく腑(ふ)に落ちる例かと存じます。
○第二百四十一段
「望月(もちづき)のまどかなる事は、暫(しばら)〈く〉も住(じゅう)せず、やがてかけぬ。心とゞめぬ人は、一夜(ひとよ)の中に、さまでかはるさまもみえぬにやあらん。病(やまい)のおもるも、住する隙(すき)なくして、死期(しご)既に近し。されども、いまだ病(やまい)急ならず。死におもむかざる程は、常住平生(じょうじゅうへいぜい)の念に習ひて、生の中におほくの事を成(じょう)じて後、閑(しずか)に道を修せんとおもふほどに、病をうけて死門にのぞむ時、所願一事(いちじ)も成ぜず。いふかひなくて、年月(としつき)の懈怠(けだい)を悔(く)〈い〉て、この度若(もし)たちなほりて命をまたくせば、夜を日につぎてこの事かの事、おこたらず成じてんと、願をおこすらめど、やがておもりぬれば、我にもあらず取〈り〉みだしてはてぬ。このたぐひのみこそあらめ。この事、まづ人々いそぎ心におくべし。
所願を成じて後、暇(いとま)ありて道にむかはんとせば、所願尽くべからず。如幻(にょげん)の生(しょう)の中に、何事をかなさん。すべて所願皆妄想(もうぞう)なり。所願心にきたらば、妄心迷乱(もうしんめいらん)すと知〈り〉て、一事をもなすべからず。直(ただ)〈ち〉に万事を放下(ほうげ)して道にむかふ時、さはりなく、所作(しょさ)なくて、心身(しんじん)ながくしづかなり。」 (同288頁)
※「いふかひなくて」…われながら不覚だと悟って。※「道」…仏道。※「所願」…ここでは目先の欲望や願い。※「如幻」…幻(まぼろし)の如くはかない意。十喩の一つで、他に「聚沫(しゅまつ)、泡、夢、影、浮雲」等がある。※「放下」…関係を断ち放つこと。※「所作」…ここでは身口意三業(しんくいさんごう)が発動した結果。また、それによる煩(わずら)いのこと。
「大概の人は皆、目前の欲望や願いを追って、結果何一つ物事を成就せぬまま死を迎えるのだから、この事をまず急いで心に銘じておかねばならない、あれもこれもと思う心はすべて妄想で自分を迷わせ惑乱(わくらん)させるものだと知って一切関わらないようにし、直ちに仏道に専念すべきだ」(概訳・向井)と強く明言しているのです。
高祖の御妙判は、ほぼ同意のことをさらに徹底して示されます。
「夫(それ)以(おもんみ)れば日蓮幼少の時より仏法を学び候ひし(学びし候)が、念願すらく、人の寿命は無常也。出(いず)る気(いき)は入(い)る気(いき)を待(まつ)事なし、風の前の露尚(なお)譬(たとえ)にあらず。かしこき(賢)もはかなき(愚)も、老(おい)たるも若きも定め無き習(ならい)也。されば先(まづ)臨終の事を習ふて後(のち)に他事(たじ)を習ふべしと思ひて云々」
(妙法尼御前御返事・昭定1535頁)
「無常」ということを私共の人生の上でとらえ対処しようとすれば、当然こうなるわけです。言われてみれば本当にこの通りなのですが、頭で理解していても、さて現実問題となると、これは難しい。「そうはいっても」というのがお互い凡夫の本音かと思われます。しかし、死期・臨終は厳然としてあり、それは高祖が『如説修行抄』(第六段)で「昨日(きのう)は人の上、今日(きょう)は身の上なれば[乃至]霜露(そうろ)の命(いのち)の日影(ひかげ)を待(まつ)ばかりぞかし」と仰せられ、さらに「一期(いちご)をすぐる事程(ほど)なし。[乃至]命のかよはんきはゝ南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経と唱へて唱死(となえじに)に死ぬるならば」と仰せのように信心を決定(けつじょう)することが実に大切になるわけです。
○「無常」だからこそ大切な一日
このように私共の命は無常です。「光陰矢の如し」であり「歳月(は)人を待たず」です。開導聖人も次の如く仰せです。
「信者の心得は気(汽)車の出るをまつ間の修行の事。○一生に一度の臨終也。
〈御教歌〉
常(つね)のなき娑婆(しゃば)の修行ぞ大事なる気車をまつまのごとくおもへば
娑婆の五欲にめ(目)をくれて、もしや乗(のり)おくれたらましかば又次のといひがたし。詮なかりけり。」
(名字得分抄(中)・扇全14巻142頁)
「舟待ち」に譬えた同趣旨の御指南もございます。これもよく分かります。いつ出るかわからない、しかしいやでもどうでも乗らねばならず、しかもたった一便しかない自分専用の汽車や船を待っているのが私共だというのです。それに各自が乗る便は皆違うのですから、これは考えてみると大変なことです。だからこそ次のようにも諭されるのです。
御教歌
題・無常覚悟肝心(むじょうかくごかんじん)何時(なんどき)がしれぬもの故(ゆえ)信行の
人が油断をせぬもよき哉(かな)
(開化要談(教)・扇全14巻32頁)
御教歌
としたけていかにくゆともかへらぬを
しりてつとむるわが身ともがな
(拾遺)
御指南
「人間一生御弘通用の日数(ひかず)を一日もあだにくらさじと工夫(くふう)して御用を勤(つと)むべし。」
(百座法門一の二・扇全12巻213頁)
高祖御妙判にも次のように仰せです。
「一日の命(いのち)は三千界の財(たから)にもすぎて候なり。[乃至]命は三千にもすぎて候。而(しか)も齢(よわい)もいまだたけさせ給(たま)はず。而(しかし)て法華経にあわせ給ひぬ。一日もいきてをはせば功徳つもるべし。あらを(惜)しの命や、をしの命や。」
(可延定業〈かえんじょうごう〉書・昭定864頁)
※「三千界」「三千」…ここでは「全宇宙・全世界」という程の意。
なお開導聖人は翌明治23年7月のご遷化を控えた明治22年の年末頃次のような御教歌を示され、さらに後掲のお書き添えをなさっておいでです。
御教歌
まかせても猶(なお)願ひある身也けり
御法(みのり)の為に無病息災(むびょうそくさい)
「まかせては身に願ひとて更(さら)になし よきもあしきも法(のり)のまにまに とよみし事を([明治22年]11月7日によめり)。此頃(このごろ)思い出(いだし)て、さては菩薩の慈悲うすし。本因妙(ほんにんみょう)のためにも無病息災ならでは、御奉公心(こころ)に任せず。云々」
(名字得分抄(中)・扇全14巻141頁)
最晩年の開導聖人が、少々体調もくずされた明治22年の11月に「法のまにまに」の御教歌を示されたあと、いや御法にお任せするにしてもただ任せ切りでは心得違いだった。何も自分自身の欲ではない、人助けの菩薩行のために、一日でも無病息災でご奉公をさせていただきたいと願うのが本来あるべき姿だったと、自ら反省され、詠(よ)み改められたというのです。
これは実に大切なみ教えだと存じます。聖人ご自身が身を以て私どもに佛立信者のあるべき心得をお示しくださっているのですから。
○長寿高齢社会の中でのお役のご奉公は
昨年(平成15年)末、世界保健機構(WHO)が2003年度報告として世界192ヵ国を調査し、世界の国の平均寿命を発表しました。それによると、日本は男女平均しての平均寿命が81・9歳、平均健康年齢が75歳で、いずれも世界一でした。ちなみに最下位はアフリカのシエラレオネという国で、平均寿命は男女平均で34・9歳です。
こうしてみると、日本はシエラレオネの何と2.5倍近くの長寿であり、平均健康年齢でさえ平均寿命の2倍以上あるのです。それだけ恵まれた豊かないい条件に恵まれて私たちは暮らしているわけです。でももう少し考えてみれば、では日本人はシエラレオネの人の2倍も3倍も善い事を行い、有意義で幸せな人生を送っているかというと、必ずしもそうではないのではないかと思うのです。確かに大きな事業や仕事をやり遂げるためにはやはり少しでも長い時間がなくてはならないということもあります。しかし、30代で死ぬ人は有意義な人生を送れず、百まで生きれば意義ある人生だ、とも申せません。要は、願わくは少しでも健康で長生きをさせていただくと同時に、その与えられた時間をできる限り意義あるものたらしめたい、ということになるでしょう。これを佛立信者として申せば、せっかく人と生まれ、真実の大法にお出値いできたのだから、この御題目を自身がしっかり受持信唱させていただくと同時に、一人でも多くの人に伝えて、自他の真の幸せを求めたい、それこそが人と生まれ、凡夫でありながらも菩薩(ぼさつ)としての喜びと果報を頂く道であり、これに勝る大きな人生の意義はない、という人生観・価値観になるわけです。
お役中は、願わくは、それぞれの限られた時間と人生の一日一日を、こうした意味で、無常を知り、また「だからこそ」、と大切にしていただきたいのです。これは信者として、あるいはお役中としてのご奉公はもとよりのこと、世法のあらゆることにも通じる大切な教えだと存じます。

- どうだんツツジが紅葉しました。
- 2014年12月28日(日)

- 裏庭の南天の実が赤くなりました。
- 2014年12月16日(火)

- 「姫リンゴ」が紅くなりました。
- 2014年12月12日(金)


佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.