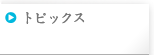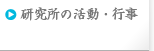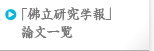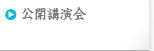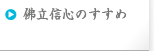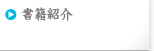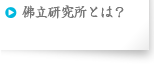-
- 2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
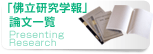
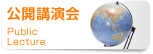
- 今年もフクシャが咲きました。
- 2014年8月26日(火)
例年通り、フクシャが咲きました。ほったらかしだけど…。
インド辺りが原産のジンジャーの仲間らしいから、葉っぱも根っこもショウガみたいです。ゲットウ〔月桃〕とも同じ仲間みたいですね。
夕方には芳香が強くなります。
九州も天気が不安定で雨が多いけど…やはりちゃんと開花して…。健気です。(J・M)
- ㉒「少欲知足(しょうよくちそく)」の教えをいただいて
- 2014年8月21日(木)
―自他の幸せと共存・欲の制御の智慧―
○「求不得苦(ぐふとっく)」と「少欲知足(しょうよくちそく)」
前回では「笑顔と喜びを大切に」というテーマで「無財の七施(むざいのしちせ)」の中の「和顔施(わげんせ)」(和顔悦色施[わげんえつじきせ])の教えに基づきつつ「笑顔の効用」とその活用法について記しました。その際、「無財の七施」を「いずれも金銭や財物を与えなくてもさせていただける布施」と記しましたが、出典である「雑宝蔵経」(第六・七種施因縁)の原文には「仏説に七種施有り。財物を損(そこな)なわずして大果報を獲(う)。一に眼(げん)施と名づく(乃至)。二に和顔悦色施(乃至)云々」(大正蔵第4巻479頁上。訓(よ)み下しは筆者)とありますから、より精確(せいかく)には「自己の財物を何も減損することなく大果報を獲得できる七種の布施」というべきかと存じます。
いずれにせよ「笑顔」は、財物は全く与えず、自分の物は何も減らしはしないのに、しかも周囲に対する大きな布施となり、同時に自身にも大きな果報がいただけるものなのです。この「笑顔」が自他に及ぼす優れた効果について、現代的な新しい観点の一つとして「表情分析学」でいう「笑顔の四つの効用」も紹介させていただいたわけです。
前回記したごとく、組なら組長さんの「笑顔」が次第に周囲を染め、引きつけて、組全体が明るく前向きに歩んでいく原動力ともなっていただければと願っています。そういう意味で「笑顔」は、結縁、育成、法燈相続はもとより、組内、家庭内、社内等あらゆる組織の活力や円満、そして自他の若返りに大きな効果を発揮するに違いないと存じます。
さて今回は「欲」をいかに制御すべきか、み仏はそれをどのように教えておられるか、というテーマです。
仏教では人間の根源的な欲を「五欲(ごよく)」とします。
①財欲[ざいよく](財物・金銭の獲得欲)
②色欲[しきよく](性欲・性殖欲)
③飲食欲[おんじきよく](食欲)
④名聞欲[みょうもんよく](見栄・体裁・名誉欲)
⑤睡眠欲[ずいめんよく](睡眠・横になって休みたい欲・嗜臥[しが])
この五つの欲はいずれも人間の生存に直接必要な、生命の維持と種の存読に不可欠な欲望だとも申せます。色欲、飲食欲、睡眠欲はもとより、財欲や名聞欲も他の欲を満たし、それらを有利に獲得するためのものと申せます。
この五欲について小乗仏教では概して極力制限し、できれば無くしてしまうことを理想としました。でもこれを徹底すると生物としての人間は死んでしまう他ありません。つきつめれば生存そのものの否定(これを灰身滅智[けしんめっち]と申します)にさえつながるわけですから、これは極端というものですし、人びとにそれを求めることは無理というものです。
大乗仏教、特に法華経の教えはそうではありません。「欲を抑え、本当に必要な程度で満足せよ。それが自他の幸福の根本だ」と教えました。それが「少欲知足」の教えです。
考えてみれば「欲」のすべてが悪いわけではありません。財物も正しい方法で必要なだけ得、それを正しく活用することは決して悪ではありませんし、性欲も正しく用いられることは種の存続のためにも必要であり自然です。総じて欲は善用されれば、自他を生かし、向上させる大切なものなのです。それはあたかも川の水の流れにも譬えられます。適量の水が、川筋にそって然るべく流れていれば、この水はあらゆるものを生かし、活用される有益なものです。ところが、これが枯渇(こかつ)したり堤(つつみ)を破って決壊(けっかい)・氾濫(はんらん)したりすると一転して大変な災厄(さいやく)をもたらすわけです。財欲、性欲、食欲、名誉欲はもとよりですが、睡眠も、これが高じていつもダラダラ横になって、ものぐさ、懈怠となれば、自他の難儀を招きます。要は何事においても両極端でなく丁度いい、適正・適度であることが大切で、これを「中道(ちゅうどう)」と申します。この適度さを超えてあるが上にもさらに得ようと求める貪(むさぼ)りの欲が「貪欲(とんよく)」です。生(しょう)・老(ろう)・病・死の四苦に「求不得苦(ぐふとっく)」「愛別離苦(あいべつりく)」「怨憎会苦(おんぞうえく)」「五陰盛苦(ごおんじょうく)」を加えて八苦と申しますが、何にせよ「求めて得られない」、総じて「自分の思い通りにならない」というのがあらゆる苦しみの根本です。これは四苦八苦のすべてに通底しています。だからこそみ仏は法華経で次の如く諭されるのです。
○「諸苦所因貪欲為本(しょくしょいんとんよくいほん)」(諸苦の所因[しょいん]は貪欲これ本[もと]なり)
(譬喩品[ひゆほん]第三・開結156頁)
○「少欲知足(しょうよくちそく)」(欲少くして足ることを知る)
(普賢菩薩勧発品[ふげんぼさつかんぼっぽん]第二十八・同596頁)
文字通り「諸(もろもろ)の苦の原因は貪欲こそが本(もと)である」「欲を少くして少ししか得られなくてもそれで満足することが大切」だとの意です。
因みに仏法の根本理である「四諦(したい)」(苦諦(くたい)・集諦(じったい)・滅諦(めったい)・道諦(どうたい)[いわゆる八正道]=苦集滅道[くじゅうめつどう])や「十二因縁[十二縁起]」(無明[むみょう]・行[ぎょう]・識[しき]・名色[みょうじき]・六入[ろくにゅう]・触[しょく]・受[じゅ]・愛[あい]・取[しゅ]・有[う]・生[しょう]・老死[ろうし])においても「苦」をいかに制し、離れるかが基本命題です。例えば「十二因縁」の「愛(あい)」は「苦を避け楽を求める根本的な欲求」であり、「取(しゅ)」は「自己の欲求するものへの執着」を意味します。そしてその上に「有」(生存)があり「生」と「老死」がある、とするのです。けれども「苦を避け楽を求め、欲するものに執着する」のは人間の生存の根本ですから、その理由がわかったからといって、それを完全に制することなどほとんど不可能なことです。それは先に申した通りです。やはりここは「少欲知足」の他はないでしょう。でも、この「少欲知足」さえ、凡夫には実際困難なことです。
○欲には際限がない―便利・快適・体裁―
際限のない欲に流され、あくせくと生きる戦後から今日までの日本人の姿を堺屋太一氏はその著『風と炎と』(産経新聞社刊・第2部24頁以下)の「便利・快適・体裁」という章で、ほぼ次のように指摘しています。
・人間が財物やサービスを求め、消費する目的
①「生存と繁殖」…戦中戦後の食糧難期
②「便利さ」…1950年以降「三種の神器(じんぎ)」(洗濯機・テレビ・冷蔵庫)を求め、インスタント食品が脚光(きゃっこう)を浴びた。
③「快適さ」…60年代から。「3C」(カラーテレビ・自動車[カー]・クーラー)が人気を博し、 “使い捨ては美徳”に。
④「見栄(みえ)と体裁(ていさい)」…特に80年代以降。ブランド商品・高級車・高級マンション・海外旅行などがもてはやされた。
その後のいわゆる「バブルの崩壊」で少しはその勢いにかげりが出たとはいえ、①~④へとそれこそ際限なく追い求めてきた日本人の姿は、まさしく「生涯衣食(えじき)の獄(ごく)につながれ名利(みょうり)の網(あみ)にかゝりて……」(妙講一座)の御文の通りです。
開導聖人は御教歌に仰せです。
①何ごとも気に入らぬこと(が)おほし これがうきよと観念をせよ
[十巻抄(四)・四五抄拝見(完)・扇全14巻450頁]
②何よりも達者(たっしゃ)でくらす御利益を こんなもうけはなしとよろこべ
[鄙振[ひなぶり]一席談・扇全9巻154頁]
③とるならば貪(とん)をはなちて信をとれ 信をはなちて貪をとるなよ
[開化要談(宗)・扇全13巻383頁]
②の御教歌の御題等
御題・経云、諸苦所因貪欲為本文
○貪欲は我身(わがみ)を破る斧(おの)也。
御書添え
○少欲知足「悦ぶべきは人身(にんしん)を得、時機相応の大法にあふ事也」
③の御教歌の御題等
御題・貪欲苦因。諸苦所因貪欲為本文
御書添え「信をとらば諸苦一時に破る」
開導日扇聖人御指南
「迷ひの人の上のつたなさ愚かさは、唯(ただ)衣食住の三つ、名聞利養(みょうもんりよう)のためのみに一生を送りて、朝夕(ちょうせき)に営む所(ところ)多くは皆(みな)貪利(とんり)の為のみ。我等の上から之(これ)をみれば不便(ふびん)也。折伏せずしてあられんやは」[扇全13巻147頁]
「末代(まつだい)の愚人(ぐにん)は少欲知足を信唱にかふれば所願具足(しょがんぐそく)也」 [此三冊(上)・扇全11巻 298頁]
門祖日隆聖人御聖教
「欲には斉限(際限・さいげん)なし云云。されば貪欲をば水に譬(たと)ふるなり。何(いず)れも流行(るぎょう)を能(のう)として更に留(とどま)る処を知らざるなり」
[名目見聞抄第十二・刊527頁]〈欲を追い求めても満たされることはなく、そのために苦しみを増すばかりである。際限のない欲に振り回されぬように心せよ。何といっても人間に生を受け、しかもこの真実の大法にお出値(であ)いして、堕獄の定業(じょうごう)を転じ、現当二世の大願を成就させていただける大果報をいただいた佛立信者となったのである。これほどの喜びはないと知らねばならない。「少欲知足」ということは難しいが、そこを御題目の受持信唱によって自然(じねん)に感得させていただくことが大切なのだ〉とのお意(こころ)です。
○思い通りにならなくても腹を立てない
お役中のご奉公についていうなら、自分自身のことはもとよりですが、例えば、受持(うけもち)の組内のご信者が、中々思い通りにならない、折角の心が通じない、といったことがあったとしても、それで腹を立てて投げ出したり、叱り散らしたりしても、それではどうにもならず、却って事態が悪化してしまうことにもなりかねません。思い通りにならなくても、たとえほんのわずかでも得るところがあれば、まずそれを喜ぶ心を大切にする、そういうあり方も「少欲知足」のあり方の一つではないかと存じます。焦っても仕方がないのですから。そういう時こそ、落ち着いて、じっくり対処し、一歩一歩進んでゆくことも大切なのです。
○「少欲知足」の智慧こそ21世紀の人類共存の規範
バングラデシュの貧(まず)しい村の出身で、自身も飢餓(きが)を経験し、後に世界の飢饉(ききん)に関する研究でノーベル経済学賞(1998年)を受賞したアマーティア・セン氏は、次のように指摘しています。
〈近年は、ほんとうの食糧不足が原因で飢饉が起こったことはなく、別の地域では余っている食糧が、それを必要とする人たちのところへうまく届かないせいで餓死者が出ているのだ〉
これは戦争や紛争はもとより、大国や先進国のぜいたくやエゴのため、分け合えるものも分けない独占が起こり、そのために貧しい国や途上国の人びとが苦しんでいるという現実の矛盾を指摘したものです。ある試算によると、日本人は平均して最も貧しい国の人の約30倍ものエネルギーを消費して生活しているともいわれます。しかもそれでも満足せず、不満を持っているのですから、このままでは文字通り罰が当たっても当然かもしれません。何億人もの人が一日1ドル以下の総生活費で生きているというのに、同じその世界でありながら、一方ではペットまでが肥満で苦しむ、それが今日のこの世界なのです。
宮崎駿(はやお)氏の作品『千(せん)と千尋(ちひろ)の神隠(かみかく)し』などが一貫して訴えているのも、実はこの「少欲知足」ではないかと存じます。氏は言います。「お互いに気を配れば、少しずつでも変わるんですね。(中略)誰かのせいにする方便はありますが、この社会っていうのはみんなの欲の集まりで出来上がっているんです。その欲をちょっとずつ抑えたら、ずっと改善されるのに」(毎日新聞 平成13年8月7日朝刊・「21世紀のレオナルド・ダ・ビンチ~地球を守る次世代へのメッセージ~第3回」より)
そういえばあのアニメでは、ご馳走を貪(むさぼ)り食べた両親は豚になってしまい、それを救う千尋は、幼いながらも風呂掃除などをいとわない心や、財物にとらわれない心を身につけていく、そんなありようが基調にありました。
「中外(ちゅうがい)日報」の社説(平成13年7月28日)にも、「新たな人類の指針として、東洋の思想、とくに仏教の『少欲知足』の智慧が注目されている」として、足利工大教授・安原和雄氏の「少欲知足の智慧をどう実践するかが21世紀の日本の行く末を決める重要なポイント」だとの提言(『仏教経済研究』第29号所掲)が紹介されています。
「少欲知足」の教えは、佛立信心の身近な教え、規範としてはもとより、この世界の未来をも左右する大きな力・影響力を持っているのです。
○「小欲懈怠(しょうよくけだい)」はいけない
「少欲知足」の教えの大切さはこれまで記した通りですが、だからといって「小欲懈怠」はいけません。
この「小欲懈怠」というのは同じく法華経の御文で「小欲懈怠なりと雖(いえど)も、漸(ようや)く当(まさ)に作仏(さぶつ)せしむべし」(五百弟子授記品第八・開結283頁)とあるのがそれです。
欲を出すなといっても、それは求める対象によるわけで、二乗の如く、自分は小乗の教えで十分であり、それでも立派なものだと満足し慢心する一方で、「自分はどうせそんなものだ」と卑下し、「大乗の教えで自他の成仏を」という望みを持たず、小法に甘んじてそれでよしとしているのは、慢心と卑屈とが同居している心であって、それではいけない、それはやはり懈怠なのだと戒められる御文です。
欲が貪欲となっては害であり(貪欲[とんよく]・瞋恚[しんい]・愚痴[ぐち]が人を害する三毒とされるのはこの意)これは抑制しなくてはいけないけれど、一方欲そのものは生存と向上の基礎、原動力でもあり、特に自他の救済・成仏を求める菩薩の願いは、それがいかに大願であろうとそれは自他を真に利するものですから、これを抑制する必要はないわけです。そこを誤解・混同してはいけないということです。
なお「少欲知足」について付言すれば、
「未得(みとく)の事法(じほう)に於て多く求めず貪(とん)せざるを少欲といい、已得(いとく)の事法に於て少しく得るも満足するを知足という」(長阿含第十二)とある他、少欲知足の語は法華経以外にも大般涅槃経その他多くの経論に見られます。
またさらに申せば、法華経が漢訳される以前の中国の老子(紀元前6世紀頃の人)の『老子道徳経』(現在最古のものは前3世紀頃までの成立)にも次の如くあります。
「甚だ愛(あい)すれば必ず大いに費(つい)え、多く蔵(ぞう)すれば必ず厚く亡(うしな)う。足るを知れば辱(はずか)しめられず云々」(講談社学術文庫『老子』145頁)
「足るを知る者は富む」(同書113頁)
こうした「知足」の教え自体は東洋の智慧の底流として古くから存在したのです。

- 裏庭にキノコが出て来ました。
- 2014年8月6日(水)
雨が続いたせいか、かなり大きいサイズです。種類も名前も不明ですから、食べません。
ところで、今日は、69年目の広島平和祈念式典の日ですね。長崎の原爆忌は8月9日だったかと。どちらも、経験を伝える「かたりべ」の養成が大切だって。概して戦争の悲惨さの経験者がだんだん亡くなって、戦争経験が風化仕掛かっているのが問題なのですね。「ひめゆり部隊」も…。現在の政府や内閣の要人も、多分、戦争の経験者ではなくなっているかと存じます。由々しいことですね。
もしかしたら、信心の相続や後継者の育成も…。(J・M)
- 今年も風蘭が咲きました。
- 2014年7月31日(木)
裏庭の柿の木に着床している風蘭で、数年前に次男が巻き付けていったのが増殖し、毎年花を付けます。
いつも、開導日扇聖人の「枯〔かれ〕るなら枯よと思ひ捨〔すて〕たりし 庭の風蘭花さきにけり」の御歌を思い出します。因みに、向かって左側の背後の大きな葉はフクシャ〔ショウガの仲間。白くて芳香のある花を咲かせます〕の葉です。(J・M)
- ㉑笑顔と喜びを大切に
- 2014年7月22日(火)
―お役中は周囲の太陽たれ―
○「和顔施(わげんせ)」と「笑顔の効用」
前回まで三回にわたって「法燈相続の大事」(―「あとつぎづくり」と「信教の自由」―)のテーマで記しました。特に前回は少々固い内容でしたから、興味を持っていただきにくかったかもしれません。でも「信教の自由」の内容やその限界については、お役中ともなれば一通りの基本だけは理解しておく必要もあろうかと存じます。知っておけば、自信をもって対応できることにもなるからです。
さて今回は少し柔らかく「笑顔の大切さとその効用」について記したいと存じます。
仏教に「無財(むざい)の七施(しちせ)」という教えがあるのをご存知の方は多いと存じます。
①眼施〈げんせ〉(まなざし)
②和顔施〈わげんせ〉[和顔悦色施〈わげんえつじきせ〉](表情)
③言辞施〈ごんじせ〉(言葉)
④身施〈しんせ〉(体の奉仕)
⑤心施〈しんせ〉(慈悲の心)
⑥床座施〈しょうざせ〉(席を譲る)
⑦房舎施〈ぼうしゃせ〉(部屋や家の使用のための提供)
(雑宝蔵経第六「七種施因縁」大正蔵第4巻479頁)
以上の七つで、いずれも金銭や財物を与えなくてもさせていただける布施ですね。
「和顔施」はその二番目ですが、端的にいえば周囲に対し笑顔や慈悲の表れたよい表情で接することですから、当然ながら①の「眼施」(まなざし)も関係しますし、そのもととなる「心」のありようも深く影響します。
この「笑顔」は、実はお役中にとっては殊(こと)に大切なものだと思うのです。それは周囲のご信者の教導はもとより、結縁、育成、法燈相続をはじめ、家庭内の円満の秘訣(ひけつ)の一つだとも申せます。では笑顔にはどんな効用があるのでしょう。
○「笑顔の効用」を生かす
以前NHKテレビで『オモシロ学問人生』というシリーズ番組がありました。毎回ちょっと変わった研究をしている学者さんとその研究内容が紹介されるのですが、その中の一つで、「表情分析学」という聞き慣れない学問を研究している工藤 力(つとむ)教授が紹介された(1999年3月2日・NHK総合)のです。タイトルが「顔は口ほどのものをいう」でした。この工藤先生、最初は別の研究をしていたのですが、当時ある女性を好きになり、やっと初デートにこぎつけることができて、一日のデートをしたのです。ところが、それまでそうした経験が全くなかったところへもってきて根が真面目でカタブツだった先生は、カチカチになってしまい、少しは言葉を交(か)わしたものの一日中固く強(こわ)ばった表情のまま過ごしてしまいました。そのまま別れ際になったとき相手の女性は「あなたは私と一緒に居ても少しも楽しくないのですね。もうお会いしない方がいいと思います」と言った由で、彼女とはそれっきりになってしまいました。この失恋にショックを受けた先生は、改めて表情の大切さに気がついたのです。いくら心の中で相手を好ましく思い、一緒に過ごせることをうれしく思っていても、表情にそれが出ていないと、決して伝わらず、誤解さえされてしまうことを思い知らされたわけです。それで先生は発奮して、当時研究が進んでいた米国の大学へ渡り、表情分析学を修めました。その成果もあってか、帰国してからの恋愛には成功して、今の奥さんと結婚することができたのだそうです。
さてこの工藤教授の研究によれば、人と人がコミュニケーションをする際、特に面と向かって会う場合、客観的な「言葉そのもの」の伝達力は意外にも全体のほんの数パーセントの効果しかないのです。それが「活字」と全く違うところだというのです。むしろ、声音(こわね)とか、身体全体の雰囲気とか、特に顔の表情、目、顔色などのほうがずっと大きな伝達力を持っているのです。そういえば「どうぞごゆっくり」と言いながら人を追い出すこともできますね。そして表情の中でも最も影響力があるのが「笑顔」なのだそうです。先生は「笑顔の効用」として次の4つを挙げます。
①笑顔は伝染する。
②笑顔は引きつける。
③笑顔は明るい話題になる。
④笑顔は7~8歳若く見える。
①の「笑顔は伝染する」というのは、例えば電車の中などで向かい側の席に赤ちゃんがいてニコニコ笑っていると、大概の人はつられてほほがほころびますね。「貰い泣き」というのはつられて泣くことですが、笑顔の方が伝染力は強いのです。いい笑顔は周囲を笑顔に染めていく強い力を持っているのです。
②の「笑顔は引きつける」とは、笑顔のある所や人の周囲には他の人が引き寄せられ、集まってくるということです。怒った顔や気難しそうな顔、悲しく暗い表情を好きな人はありませんから、必要のない限りそんな所には近寄らないように、自然になっていくのが普通です。
③の「笑顔は明るい話題になる」とは、暗く陰気な表情や、怒ったような顔で会話や話し合い、会議などをしていると、どうしても話の傾向やその場の雰囲気が消極的で非生産的な方向に趣(おもむ)いてしまい、大概はロクでもない結果にしかならないのに対して、笑顔を大切にして会話や会議を進めていくと、不思議に明るい方向、積極的で生産的な方向に話題が向かい、善い結果を得られることも多いという意味です。
最後に④の「笑顔は7~8歳若く見える」とは、人は地球の重力を受けて生活しているため、生まれて以来加齢とともに筋肉も皮膚も下に向かって垂れ下がってゆくのですが、にっこり笑うとアゴの筋肉やほほ全体が上に引き戻されるので、その分必ず表情は数歳から7~8歳は若返る道理だということです。実際同じ人の写真でも笑顔の方が感じもよく、若々しく、イキイキとして見えますね。
開導日扇聖人は御教歌に仰せです。
いか計(ばかり)うれしき事のあるやらむ
みるにゑまるゝみるにゑまるゝ
「あの人はあんなにうれしそうにニコニコしているが、一体どれほどのいいことがあったのだろう。それにしても見ている私までもがつられて自然にほほえんでしまう。いやほんとうに結構だなあ」というほどの意でしょうか。「こちらまでうれしくなってついつい目が離せない」という雰囲気ですね。見ているこちらに文字通り「笑顔が伝染」し、「笑顔に引きつけられ」ており、「なぜだろう」と興味・関心を喚(よ)び起こされてしまっているわけです。
笑顔の大切さは、女子マラソンの高橋選手に対する小出義雄監督の言葉にもあります。〈小出監督はいつも言っていた。「嫌(いや)な顔をしてやっちゃいかん。楽しんでやれ。ニコニコしている顔に出会うと、こっちまでうれしくなる」高橋選手がけがをしたり、風邪(かぜ)をひいて焦(あせ)っていると、「“せっかく”風邪をひかせてくれた。せっかくお腹(なか)が痛(いた)くなったのだ。ありがたい。そう思う心が大切なのだ」と小出監督は書いている。(『君ならできる』幻冬舎)〉[毎日新聞・2〇〇〇年9月26日『余録』]
笑顔の効用の素晴らしさは以上の通りですから、まずは形から、事相(じそう)・外見からなりとも笑顔の稽古をすべきですが、もちろん本物で自然な笑顔には、そのもととなる心のありようがやはり大切だというのは当然です。深い喜びや感謝の心があれば、自然にそれが目に、表情に、雰囲気に表れてくるでしょうから。ただそれでも工藤教授の失敗のような例も一方ではあるのですから、やはり努力や工夫も大切なのでしょうね。稽古や喜びと感謝の心の大切さについては、これまでに記した「稽古の大切さ」(新役中入門⑯⑰)や「懺悔の大事」(同⑬)の中の「随喜段」の説明等で既に触れておりますから、参照してください。
「まれな人間に生まれ、その上真実の大法にお出会いできた。そのおかげで堕獄の定業(じょうごう)を能転(のうてん・よく転じ)して現当二世の大願を成就させていただける。これほどの喜び、うれしさがあろうか」という最も根源的な深い喜びを感得させていただけるのが佛立信者なのです。これさえ忘れなければ、きっと大丈夫だと存じます。
○お役中は周囲の太陽たれ
『妙講一座』の「日月の御文」やイソップの「北風と太陽」の寓話(ぐうわ)ではありませんが、お役中はやはり周囲のご信者にとって太陽のように明るく暖かい存在であってほしいと存じます。そのためにもまず笑顔を大切にしてほしいのです。
先の工藤教授の4つの「笑顔の効用」にあるように、組なら組長さんの笑顔が次第に周囲を染め、引きつけて、その組全体が明るく前向きに歩んでいく原動力ともなっていくのだと思うのです。

- ツマグロヒョウモンの幼虫です。
- 2014年7月22日(火)
ツマグロヒョウモン〔タテハ科だっけ?〕は、スミレの仲間が食草で、三色スミレやビオラと共に増殖しているように見えます。
ウチのお寺の三色スミレのプランターにも、毎年この時期になるといつの間にか産卵されて幼虫が出てきます。4回くらい脱皮してからサナギになりますが…こんな怖い感じの幼虫が、綺麗な蝶々になるなんて不思議です。幼虫からサナギになるのが変身なら、サナギから成虫の蝶になるのは大変身かな?(J・M)
- ホテイアオイ〔ウォーターヒアシンス〕が咲きました。
- 2014年7月8日(火)
先ごろ、ご信者さんから頂いた布袋葵に花が咲いているのに、今朝気が付きました。 ホテイアオイにも大小の種類があるようで、普通、金魚屋等で売ってるのは小さい種類だけど…ウチのは大きいサイズの方みたいです。もっとも、これが用水路や溜め池の水面を覆って一斉に咲くと、一面が青くなって、それはそれで壮観ですが…。ウチのは、小さなビオトープに入れて、メダカを入れ、後はほったらかしですから、何か可哀想です。(J・M)

- 皇居蓮〔コウキョレン〕が咲きました。
- 2014年7月7日(月)
やっと咲きました。昨年に続き、2年連続の開花です。小さなビオトープで頑張ってます。但し、2輪がほぼ同時の開花になったから、多分、7月9日には散ります。ハスは基本的に4日間しか咲かないから。因みに、皇居蓮は、中型で紅色の花を付ける古代バス系のハスです。(J・M)
[上の写真は7月6日撮影・下の写真は7月7日撮影]
佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.