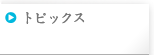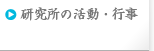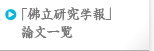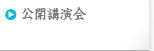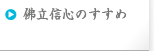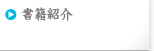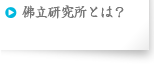-
- 2019
2016
2015
2014
2013
2012
82011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
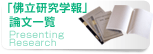
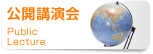
- トピックスの過去の記事
- 2019年 9月
- 2016年 5月
- 2016年 4月
- 2016年 3月
- 2016年 1月
- 2015年 12月
- 2015年 11月
- 2015年 10月
- 2015年 8月
- 2015年 7月
- 2015年 6月
- 2015年 5月
- 2015年 4月
- 2015年 3月
- 2015年 2月
- 2015年 1月
- 2014年 12月
- 2014年 11月
- 2014年 10月
- 2014年 9月
- 2014年 8月
- 2014年 7月
- 2014年 6月
- 2014年 5月
- 2014年 4月
- 2014年 3月
- 2014年 2月
- 2014年 1月
- 2013年 12月
- 2013年 11月
- 2013年 10月
- 2013年 9月
- 2013年 8月
- 2013年 7月
- 2013年 6月
- 2013年 5月
- 2013年 2月
- 2013年 1月
- 2012年 12月
- 2012年 11月
- 2012年 10月
- 2012年 8月
- 2012年 6月
- 2012年 4月
- 2012年 3月
- 2012年 2月
- 2012年 1月
- 2011年 12月
- 2011年 11月
- 2011年 10月
- 2011年 7月
- 2009年 12月
- 2009年 8月
- 2009年 7月
- 2009年 6月
- 2009年 5月
- 2009年 4月
- 2009年 2月
- 2009年 1月
- 2008年 12月
- 2008年 11月
- 2008年 10月
- 2008年 9月
- 2008年 7月
- 2008年 4月
- 2008年 3月
- 2007年 9月
- 2006年 11月
- 2004年 3月
- 2003年 9月
- 1990年 3月
- ⑥参詣の大事(2) ―親近と給仕について―
- 2012年8月23日(木)
○「参詣」の要素①……「親近(しんごん)」
前回は、当宗信行の根幹の一つである「参詣の大事」(1)として、「道場の能所(のうじょ)」や「身体的に“腑に落ちる”こと」の大切さ、「場(ば)」や「つながり」のあり方を見直すことの大切さを申しあげました。 今月は、「参詣」にともなう大切な要素である「親近(しんごん)」と「給仕(きゅうじ)」のうち、まず「親近」について申しあげます。
はじめに高祖日蓮大士(だいじ)の御妙判をいただきます。「法華経の文字は六万九千三百八十四字、一一(いちいち)の文字は我等が目には黒き文字と見え候へども、仏の御眼(おんまなこ)には一一に皆御仏(みほとけ)也。[中略]玉泉(ぎょくせん)に入(いり)ぬる木は瑠璃(るり)と成る。大海に入ぬる水は皆鹹(しわゆゆ)し。須弥山(しゅみせん)に近づく鳥は金色(こんじき)となる也。[乃至]何況(いかにいわんや)法華経の御力(おんちから)をや。」(本尊供養御書・昭定1276頁) 右の御文は建治2年12月、55歳のお祖師さまがご信者の南条平七郎に宛てられた御消息(ごしょうそく・お手紙)の一節です。
玉泉に入った木は、ただの木でも瑠璃と変じ、須弥山(シュメール・妙高山とも。仏教の世界観の中央の山)に近づいた鳥は自然に皆金色の鳥になるといわれる。ましてや法華経の御本尊・御宝前に近づいた者は、それが凡夫であっても、御題目をお持(たも)ちし、御宝前に親近した功徳は計りしれず、大果報を頂戴することができるのだ、と仰せです。「親近」は「親しく近づく」ことですが、「親」は「まのあたり」とも訓(よ)み、まのあたりにできる位置まで近づく意でもあります。参詣は、道場に親近し、御宝前・み仏に親近し、御住職・お教務・ご信者方(つまり善師・菩薩方)に親近し、お仕え(お給仕)することでもあるわけです。
「親近」しなければ先月学んだような種々の功徳もいただけないわけですから、まず近づく、それもできる限り数多く近づき、できる限りおそばに居らせていただくことが大切なのです。
法華経法師品に「若親近法師(にゃくしんごんほっし) 速得菩薩道随順是師学(そくとくぼさつどうずいじゅんぜしがく) 得見恒沙仏(とっけんごうじゃぶつ)」(若し法師に親近せば速(すみ)やかに菩薩の道(どう)を得(え) 是(こ)の師に随順して学(がく)せば恒沙の仏を見たてまつることを得ん)と示されるのはこのことを仰せなのです。(もっともここで「法師」とあるのは必ずしも出家の僧のみをさすのではなく、在家・出家にかかわらず、妙法を持(たも)ちご弘通に励む人こそまことの菩薩・如来使であり、そうした人はすべて法師だとされています)○「親近」における注意点・・「悪狎(わるな)れ」
正しいご信心、信行のあり方を学び、感得させていただくためには、道場に参詣し、御宝前に近づき、善き「法師」に親近させていただくことが極めて大切であることはこれまで申しあげた通りです。本堂や御講席などでも「できる限り席を前に進みなさい」と教えられるその理由も、御宝前から遠く離れた所で、御本尊も親(まのあた)りに拝めず、御導師の顔も見えず、御法門の声も遠くて聞きとりにくいようではやはり残念です。参詣者や場所の関係でやむを得ないときは致し方ないでしょうが、前に進もうと思えば席もあるのに、遠く後ろの席を好むのは「親近」ではなく「遠離(おんり)」で、もったいないですね。遠慮も時と場合によるわけです。厚かましさとは別です。できるだけ早く参詣して、親近できる場所を求めるのが本来の姿です。 自分の好きな映画や観劇なら、自然に欲も出て親近するはずです。お役中は、まず自身が「親近」の大切さをよく感得し、組(部)内一般のご信者にも優しくそのことを教えてほしいのです。ただ「親近」にも1つ注意点があります。それは「近づき過ぎて、あるいは近づいている間に、ついつい馴(な)れ馴れしくなってしまう」、「悪狎(わるな)れ」してしまうことです。
誰しもあることですね。最初は「私のような者がもったいない」という気持ちがあり、緊張もし、相手を敬う心もあるのですが、しばらくして慣れてくると、緊張感も失われ、相手も身近になって「何だ、こんなものか」といった心が起こってきて、敬う気持ちが失せてしまうことがあるのです。「慣れる」ことはそれ自体決して悪いことではないのですが、それがいい意味での熟練・ベテランの方向に向かうか、悪狎れ、馴れ馴れしさ、慢心の方向に向かうかは、一にかかって本人の自戒の有無によります。
人間関係でも、少し離れた遠くから見ていたときは、とても素晴らしい人だと思い、憧(あこが)れたり尊敬したりしていたのに、親しく近づいてお付き合いをさせていただいているうちに、今までは見えなかった人間くささや、欠点などが目に付くようになり、そうなると、憧れも尊敬もなくなり、「なあんだ、こんな人だったのか」などと急に心がさめて、敬うどころか反対に軽べつさえしかねない、そんなことがありますね。それは恋人が結婚して夫婦になったとき、職場の上司と部下、友人同志といった間柄でもありうることです。 でも、ほんとうの相手には、それでも優れた点もあり、尊敬すべき点や学ぶべき点は沢山あるはずなのです。近づき過ぎて却(かえ)って見失ってしまうものがある。見えなくする心が自分の中に生じてしまうことがあるわけです。
この点につき『論語』に次のような言葉があります。(イ)「子(し)の曰(のたま)わく、民の義を務(つと)め、鬼神を敬してこれを遠ざく、知と謂(い)うべし」「先生はいわれた、『人としての正しい道をはげみ、神霊には大切にしながらも遠ざかっている。それが智といえることだ』」(岩波文庫ワイド版・118頁・雍也(ようや)第六)
(ロ)「祭ること在(いま)すが如くし、神を祭ること神在すが如くす」「御先祖のお祭りには御先祖がおられるようにし、神々のお祭りには神々がおられるようにする」(同書・59頁・八佾(はちいつ)第三)いずれも孔子の言葉で、儒教の教えですから、もちろんすべてをそのまま受取るわけではありませんが、参考として学ぶ面はあります。因(ちな)みに(イ)は「敬遠」の、(ロ)は「如在(じょさい)」(如才)の語の典拠ともされます。「鬼」というのは、中国では元来亡くなった人の霊魂のことであり、「神」というのは「神霊」のことであって、いずれも生きた人間の力を超えた力を有するとされます。「それらを敬い大切にはするが、馴れ馴れしく近づいてもてあそぶことのないように」というのが「敬してこれを遠ざく」つまり「敬遠」の元来の意味なのです。現在の私たちの「煙たがって離れている」意とは随分違います。孔子は、決して「煙たがって離れていよ」と言っているのではなくて、むしろ「敬う心を大切にするため、あまり狎(な)れ親しんではならない」と言っているのです。
「如在」は「在(いま)すが如く」という意ですから、祖先の霊や、神々を祭(まつ・祀)るということは、姿は見えなくてもあたかも目の前にその方がおいでであると思い、その如くにさせていただくことが大切だ、と言っているのです。当宗でいう「冥(めい)の照覧(しょうらん)」(冥は冥闇の冥でうすぐらく、こちらからはさだかに見えないこと。顕(けん)・明(みょう)に対する語。み仏のお姿は凡夫からはそれと見えないが、み仏はすぐそばからすべてを明らかに御覧になっていること)と似た意ですね。「如才」は〈在〉が〈才〉に転訛したもので、「いつもそばにおいでだと思って油断しないこと」が元の意。これが転じて「如才なく」が「遺漏なく、油断なく」になったのです。 孔子は「敬いを失くさぬよう、あまり近づかない方がいい」しかし、「そこに在すと思ってお祀りせよ」と言いました。しかし、当宗はそうではありません。「親近」しながら「恭敬(くぎょう)」せよ、と教えられるのです。何といっても親近しなければみ教えを感得し難いからです。ただその際やはり、近づき親しみ過ぎて悪狎れをしたり、慢心を起こしたりすることのないよう、これは十二分に自(みずか)らを戒め、尊敬の心、恭敬の心を失わぬように注意をさせていただかねばならないのです。難しいことですね。そこに大切になってくるのが、み仏やお祖師さまのお姿はそれと見えなくても、すべて照覧なさっているという「冥の照覧」の教えであり、それを忘れぬようにしてこそ本来の意味での「如才ない」信行をさせていただくことができるのです。
「給仕」については次回で申します。
佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.